DiaryINDEX|past|will
| 2007年12月31日(月) | Niseko-Rossy Pi-Pikoe |
みなさま、よいお年を。
Jazz Tokyoで年間ベスト■を発表しました。
執筆陣が増えてますね。
うおお。伝説の編集者・杉田誠一が!登場している。しかも、この選盤、この文体。ジャズ・イズ・スティル・アライブだ。
どのレビューも面白い。
こないだ丘山万里子さんに会って、こんなに耳のいい女性がいるのかと、ほんとにわかった。この盤は買うぞ。
稲岡さんも切れること書いてるなー。プー・ファンク。おれも聴いてたけど■、そうかー、マイルス『コンプリート・オン・ザ・コーナー』なんてあるのかー。
とつぜんの25にちの夢見で。「ニセコロッシ・ピーピコ。 Niseko-Rossy Pi-Pikoe 」という名まえを、ぼくはぼくに名付けたのだった。
それで、「音楽を守護するガーディアン」、なんだと。まじかね。アニメ「しゅごキャラ」、そのまま影響しているだけだし!というわけで、ただまさのりは、キャラなり、で、ニセコロッシ・ピーピコ、に、変身します。
| 2007年12月24日(月) | NHK東京児童合唱団の「ユースシンガーズ第1回演奏会」 |
クリスマスイブ当日はNHK東京児童合唱団の「ユースシンガーズ第1回演奏会」。
おめあては3月30日に名古屋で聴いた「詩篇頌詠」■。
ユースシンガーズというのは、児童合唱団(小学生が主体だな)を中学2年で卒団したメンバーでさらに深く合唱に取り組みたいこたちが一般の応募者とともにオーディションを受けて構成されるという。
「どこかで春が」「うみ」「赤とんぼ」「雪」「故郷(ふるさと)」といった、聴く前からあくびが出そうなタイトルのナンバーを!
クイーンのハーモニーやらパット・メセニー的映像音楽やら、こいつはぜったい20年前にゃ池袋西武アールヴィヴァンに通っていたに違いないと思わせるミニマルミュージック的アレンジやら、なんとも編曲者が秀逸すぎっ!・・・NHK、さすがいい人材を揃えてるナ。
こういったまさに音楽的な先進性を楽曲に取り入れ、それでいて古典が生き生きとした表情をみせる。
こういうのをどういった形容をするのだっけ?
新しい器(うつわ)で古いなんとかかんとか?ちがうな・・・
そ、それを14さいから15・6さいの女の子たちが制服を揺らしたり、手拍子をしたり、さ、さ、39にんだぞ!
そ、それはずばり“ボーノ!×13”のレベルであり、彼女たちの素朴な感情までが音楽を揺らしているという点では、
も、もしかして、音楽ってそのようなものだったんじゃないか?と、なみだ目になる。
楽器は肉声に近づく、とか、音楽の本質にあるのは楽譜でも感覚ジャッジ神さまでもなくそれが放つヴォイシング=固有の声である、という、技法的に還元できない音楽のなぞの欠片。そして、音楽は揺れるのだ。スイングという技法でも分析家御用達の“ゆらぎ”でもない。
そうそ。ガキが歌ってるだけにしか聴こえないひとはひと。統一されない技巧の稚拙がさきに見えるひとはひと。
アンコールでレノンの『ハッピー・クリスマス(戦争は終わった)』なんてサイテーな曲をいたいけな乙女たちに歌わせて、思わずあんたらボブゲルドフの手下か!ブッシュのイヌか!と虫唾がはしったのはその発案者はどうせ45くらいのチンケなおやじに相違なく。
しかしながらそのあとにやってくれた音楽の神さまのしもべのようなおばちゃんが振った最後のアンコール曲(曲目わかんねー!)のすがすがしい美しさはなんだ。
エンディングは39にんのボーノ!たちが「メリー・クリスマス!」と一斉に、そして会場に天国が降ってくるような39の投げキッス。
いやー、おれはおれなりにあまり知られていない音楽とかをどう誰かに伝えようかと、それによって音楽の神さまにフェイスを尽くそうかと、それなりに工夫をこらしてみたんだが、21世紀にもはやおれはいらなかった。
このコンサートについやされた多くの職人たちのきちんとした仕事、彼女たちが二度とない時間を結晶にして輝かせたような音楽の響き。
おれはこのコンサートシリーズのコンプリートコレクターになるぞ。年末年始を13連続夜勤で寒い夜に耐えるちからをぼくはもらった。欺瞞なキリスト教がきらいなわしじゃが、帰りの電車でメリー・クリスマスとつぶやいてしまったぞ。ありがとー、おんがく!
○「N児が選ぶ日本の歌50選 第2集」(委嘱初演)
編曲:北爪道夫、大竹久美、鷹羽弘晃
○「詩篇頌詠」
作曲:三善 晃
○「Toca taca tia...」(ルーマニア民謡)
○「Dies sanctificatus」
作曲:Huszar Lajos
○「Merry Youth Xmas」
そりすべり 南安雄 編
クリスマス 谷川俊太郎 詩/林光 曲
プチパパノエル 蓬莱泰三 詩/南安雄 編
キャロルによるカノン 高嶋みどり 編
| 2007年12月23日(日) | 成田亨の展覧会 |
ウルトラマンやレッドキングやメフィラス星人などの怪獣をデザインした美術家である成田亨の展覧会が足利であった。
怪獣たちのデザインの原画は、まさに神々の痕跡のようなものを感じさせる。
円谷プロを飛び出してからの成田亨の人生。
37・8さいに果たしたウルトラマンに関する仕事、が、生涯にわたって彼の創造を枠に嵌めていっているのがわかった。一瞬だけ輝いて、その栄光、自己規定から逃れないで余生を過ごしていた。その表現に幸福なもの、創造的な何ものかはまったく感じられない。痛々しい生きざまをみてしまった。
カミソリのように切れる発言もある。
「新しいデザインは必ず単純な形をしている。人間は考えることができなくなると、ものを複雑にして堕落してゆく」(模型誌「B-CLUB」1986年11月号)
ウルトラマンを成功に導いたのは成田亨のデザインだけではなかった。
当時の現代音楽と直結した怪獣の咆える大音量を検証した展覧会も期待したい。
| 2007年12月22日(土) | まちがいない。おれのちだ。 |
高校2年の長男が、わたしが図書館から吹奏楽の年代ごとの課題曲を収めたCDを借りて車に載っけているのをめざとく見つける。
「なんでおとうちゃんが吹奏楽のCD聴くん?」(群馬のイントネーション)
「おれの好きな作曲家が書いている曲があるから・・・」
「ふうん。だれ?」
「みよしあきら」
「みよしあきら、いいよね。」(平然と)
「んぐ!、お、おまえ、みよしあきら知ってるのか!」
「交響三章、かっこいいだろ」
「ほえ?・・・かっこいいのか?」
「聴いたことないん?」(群馬のイントネーション)
吹奏楽の課題曲でマーチはどれもつまらない、と、なかなかの見解を述べておる。まちがいない。おれのちだ。
中学3年の次男が、校内合唱コンクールの実行委員長をつとめて、自分のクラスを校内優勝に導き、さらに市内の中学校合唱コンクールにまで出て優勝した、と、こともなげに話す。
お、おれも中学2年んとき函館市港中学校の合唱コンクールで指揮者をつとめ、自分のクラスを校内優勝に導いた経験がある。これは断じて事実である。
おいおい、30年以上も前の北海道のハナシなんていくらでも偽造できると真顔で抗弁するエクスワイフよ、これはホントだ。
家族で桐生の回転寿司屋に行って、おれと次男は打ち合わせ無しでドリンクバーを、カルピスとコカコーラを混ぜたものを飲みながら皿を重ねていた。
カルピスソーダのボタンもあるのにどうしてそんなブレンドさせて飲んでいたのだおめーは。おれもだが。
ちだ。
まちがいない。おれのちだ。
| 2007年12月21日(金) | ひだりがわの白いシャツにネクタイの鈴木愛理(すずきあいり)13さい |
Buono!の「ホントのじぶん」をライブでみてえー。■
こないだははしゃいだだけだったが、今回はまじめに書こう。
3にんともそれぞれに、文脈的には少女、虚構、成熟と三方向にある、しかもそれぞれに臨界値を越えるほどにいい声をしてんのだけど、
いやいやこの3にんの声がコーラスごとに交代して耳に聴こえることもよくて、3にんがハーモニーするパートもよくて、もうたいへんだ。
で、アイドルの歴史を検証するに、ダンスと振り付けについてしっかりとした分析成果がないというのは、わが国のポピュラー音楽文化研究において見落とされている分野である。
ひだりがわの白いシャツにネクタイの鈴木愛理(すずきあいり)★13歳/℃-ute★中学1年生★生年月日:1994.4.12★血液型:B型
このコの声もひときわ輝いているが、このコのダンスと振り付け、表情とのコンピネーション、四肢の関節の柔軟性、
まさに、これは今しか出来ない、1000ねんに一度のほとけさまの顕現にひとしいものがある。
さて、この曲のワンフレーズごとに彼女の振り付けのキュートな部分、悩殺なポイント、を指摘してみよう。
あ、いけない。そろそろ夜勤仕事に行かなければ。今夜も寒いのかな。
| 2007年12月20日(木) | 弁慶のほろほろ漬け |
今年のベストは細野晴臣、ハリー細野&ザ・ワールド・シャイネスの『FLYING SAUCER 1947』、だらうか。
いま見つけたけど、アマゾンのスタッフが選んだ2007年ベスト14枚■。これはこれですするね。年越しそばか!・・・そそるね。
年間ベストをお祝いするというのは、ゆく年くる年なのだ。
ぼくは『タルホロジー』は入れなきゃ、な。「雪ヶ谷日記」は、21世紀がゆく20世紀を歌った、あがた森魚に音楽の神様が歌わせた、そういう曲。
ぼくたちはいつも小さくなってゆくばかりなのだ。
5さいのときに迷子になって泣きながら遠くの遠くの歩道を。下校途中のセーラー服の女子中学生ふたりに「どうしたの?おうちはどこ?」ときかれたのが嬉しいとて、安堵となって、その気持ちでいっぱいになってわんわん声をはりあげて、うれしくてうれしくてわんわん声をはりあげているのに、どんどんそのおねえちゃんたちは困って途方に暮れてゆくばかりなのが、
(んげ。書いてて気づいた。)
おれのレンアイ深層心理に、彼女を困らせれば困らせるほど嬉しくなってしまっているテーゼというものがあるのだろうか!
彼女とのデートに限って国分寺や中野や西新宿や御茶ノ水の中古盤屋に行かなければならない衝動が発生して、しまう、という、のは!
5さいのときに迷子になって泣きながら遠くの遠くの歩道を。
ついさっきのことのようなのになー。弁慶のほろほろ漬けでごはんたべて、コーヒー、たばこ。
コーヒーったってメグミルクとネスレコーヒー■だし。ガソリン入れに行ったついでに50えんびきでのむドトールのコーヒーがいちばんうまいな。
「サーチライトは着物の井桁(いげた)のようだ」 雪ヶ谷日記 あがた森魚
| 2007年12月19日(水) | ピーター・バラカンの夢 |
午前6時には眠りに落ちていた。
早朝の救急車が走る音を聞いた、気がした。いつも騒音で悩まされる駐車場をはさんだ新築3階建て、おれはこの
夢をひとつだけ見た、というより、こんな夢でもがいたのははじめて。
ピーター・バラカンがネット上の手書きできる形態の掲示板に、
マイラ・メルフォードが最初に出したピアノ・トリオのタイトルとレーベル、録音日が一行目に、
二行目に三人の名前が書かれていて、いずれも筆記体で。
ドラムがNasheeet Waitsナシート・ウエイツ■とあり、
おれがその掲示板にNasheeetに下線をつけeが1個多いとペンで書き入れ、
パソコンの画面なのだけどなぜがそういうことができるのだった、夢の中では自然にそうしていた、夢からさめると不思議な掲示板ではある。
そのメルフォードの最初のピアノトリオをおれはたしかに入手して聴いていた。
(さすがバラカンさんはジャズもいいところを聴いている、それにしても、あの作品でナシートウエイツはすでにおれの耳に入っていたのかー。うかつだったなあ。おれ、こないだCD売ってしまったしな。)
と、思いながら、ナシートウエイツに注釈を書き入れるように英文で「彼は現代ジャズでこの10年で登場した重要なドラマー6人ジム・ブラック、ポール・ニルセン・ラブ、トーマス・ストローネン、マヌ・カチェ、本田珠也、フェレンク・ネメス、のひとりだ。」とバラカンさんに自分の存在を誇示するように書き入れた。ペンで。筆記体で。
そしたらすかさずI do think so,and you must listen...と2人のやたらと長い名前がバラカンさんから書き込まれた。
うお!うお?なんて名だ、チェックしなきゃ、わ、長くて読めねえ、どこのジャンルのドラマーだ?それにバラカンさんはネメスもストローネンも本田珠也もすでにチェックしているというのかー!とあわててもがいているうちに肩がいたくて目がさめた。
目がさめて、時計を見ると午後2時40分。2人のドラマー名はさっぱりおぼえていない。
パソコンを開けてメルフォードとウエイツのdiscographyをチェックしてみると、まったくそのような録音は存在しないようだった。
なんなんだ、おれの記憶。
それにメルフォードに対しては次第に抽象的で高度なピアノを弾くようになり混沌としたエネルギーを放つような不穏なピアニズムを喪失してきていたように感じていたのでここ数年ノーマークだったものである。
それにバラカンさんとはアンソニーコールマン来日時の楽屋でチラチラとお互いに視線を数度かわしていただけの経験しかない。
あ。ナシートウエイツってボヤン・ズルフィカルパシチの『トランスパシフィク』で叩いていたー!うおー、そうだったのかー!CD聴いてんのに気付かなかったー。
いま、外では救急車が走る音がしている。
| 2007年12月18日(火) | ほっぷすてっぷじゃんぷ ドルゥドロゥドロゥン ちっぷしろっぷほいーぷ ナリタイアタシ |
ほっぷすてっぷじゃんぷ
ドルゥドロゥドロゥン
ちっぷしろっぷほいーぷ
ナリタイアタシ
クールで強くてカッコいい イケてると言われていても
ほんとはそんなでもないし フツーに女の子だもん
プレッシャーなんかはねのけて すなおになりたいんだけどな
キャラじゃないとか言われたって あたしのこころアンロック
なりたいようになればいいじゃん しゅごキャラがついているよ
池上のデニーズの駐車場で19の長女と46のわたしはアイドルグループBuono!(ボーノ)が歌うアニメ『しゅごキャラ』のテーマソングをカーステ大音量でかけている。
ともにうっとりとした表情で聴き入っている。
| 2007年12月17日(月) | 『死人(しびと)』 JINYA DISC |
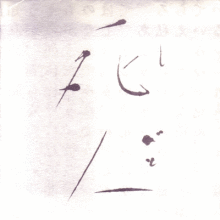
『死人(しびと)』 JINYA DISC
吉増剛造(朗読) 高柳昌行(ギター) 翠川敬基(チェロ)
死人(しびと)
古代天文台
オシリス石の神
吉増<石狩シーツ>剛造、詩の朗読。高柳<解体的交感>昌行、ギターとラジオ。翠川<緑色革命>敬基、チェロ。の、ライブ録音。
そんな録音があったのか。詩の朗読と即興演奏のコラボレーションといえば。きわめて60年代的な。先鋭化して70年代的な。おびただしい試みが行われたと思う。ぼくが通っている図書館にはブリジット・フォンテーヌの『ラジオのように』しかなくて、フランス発のアート・アンサンブル・オブ・シカゴの衝撃だけが21世紀に伝わる文化遺産になっているのだろうか?などと思い、そういうものかもしれないとも思い。
吉増剛造を知ったのは「石狩シーツ」1995という朗読CD(背景音がモンドで良い)で、その耳のショック、朗読の喚起力はおそらくこのジャンルにおける傑出したもの。異界からの声を現前させるこの作品に接して、現在最も注目される作家・古川日出男も朗読を行うようになったとも。
その吉増の先行した試みに高柳がいた、というのは、日本のジャズにおける高柳の重要度を認識する者にはいささか興味深い。この録音がなされた1984年、高柳はディレクションからアクション・ダイレクトへ移行中の時期だとされているが、そのメタ・インプロヴィゼーションという概念をおれはよくわからない。この録音を聴くに、速度とエネルギーの権化として屹立していた高柳ではなく、その速度とエネルギーのいわばボイラー室から噴出した蒸気によって排気口にくっついていた灰くずのような無機物が気まぐれな痙攣運動をするかのような映像がおれには感じられた。それがそうだというのなら、そうなのだろう。
おれがこの録音を偏愛するのは、高柳が直感的に正しくここで用いた短波ラジオの音のコラージュであり、電気ギターの電源音をじっと鳴らしている態度を挿入していることにある。すでに高柳は音響派も大友良英も折り込み済みだった、と、刺激的なことを書いてしまうのも可能ではある。そんなことは流行でしかない。おれはそのことよりも、2007年になってこの1984年の録音がCDとなってよみがえってきて、発掘された音源という意味ではなく、高柳昌行が現在生きて(蘇生の意ではない)奏でているというこのリアリティにある。音楽、や、演奏家、が、時空を越える、という新興宗教めいたことを記述してていいのか?・・・夜に、音楽は夜の音楽、コトバは夜のコトバ、と、つぶやく。
ラジオ短波が。犬の遠吠えが。そして田村夏樹の『コココケ』が耳に召喚される。
この『死人』とともに、わたしは『しばたやま』という吉増の朗読と渋谷毅(ピアノ)+川端民生(ベース)の録音を手に入れた。そこでの渋谷、川端も、特別な演奏だった。日本のジャズは欧米に比してどうのこうのと眠たいことを言ってはいけない。日本の文化土壌でかつて存在した試みや成果は、いまだ知られず、そして現在のわれわれを変容させ始めることが起こってくるようだ。
| 2007年12月16日(日) |
| 2007年12月14日(金) |
樹下龍児著『風雅の図像』ちくま学芸文庫。
| 2007年12月13日(木) | 年間ベストジャズトーキョー海外1枚 |
三鷹での仕事だったので小金井の江川亭で味付玉子ラーメンを食す。
味が変化したのか、おれの舌が変化したのか、このところ加速してすすむ老眼のせいで確信が持てない。
だが、耳のほうはいよいよ偏差値90台に突入してきた。いまなら日本ジャズ史上もっとも耳がよいとされたきた中山康樹に鼻差先行できるかもしれない。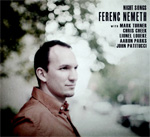
あとで見直しする。おやすみ。
Night Songs / Ferenc Nemeth (Dreamers Collective Records) 2007
1. War...
2. A Night
3. Intro To Vera
4. Vera
5. Intro To E.S.P.
6. E.S.P.
7. New Song
8. Ballad For The Stars
9. Theme To L.L.
10. L.L.
11. Raindance
12. Lullaby
Mark Turner sax, Chris Cheek sax, Aaron Parks p, Lionel Loueke g & vo, John Patitucci b, Ferenc Nemeth ds
マーク・ターナー、クリス・チーク、アーロン・パークス、リオーネル・ルエケ、ジョン・パティトゥッチ、フェレンク・ネメス。この6人が。
これをPMGの新作だと聴いてみそ?今年のベストに選んだ本作を、そう語り始めたい。メセニーが『The Way Up』2005を提示したあとに、つまりメセニーというジャズ、オーネット、ライヒ、ブラジル、ベイリー、カルテット、イマジナリーデイといったキーワードを横断して歩む獰猛な怪物の鼻差先行するサムシングを光らせている、ことを、やはりジャズに求めたかった。メセニーはジャズの彼方に進んだ表現に到達したから、とは、言い訳だっただろ?みんな。お導きは、ターナーとチークのダークなブレンドトーンで隠し名盤に相応しい『A Girl Named Joe』(Fresh Sound New Talent)1998、かもしれない。マーク・ターナーのサックスのトーン、そしてこねくりまわす抽象的な思考・語り口には、ジャズの未来が宿っていると思っている。ターナーが探っているジャズとポール・モチアンがトリオ(ロヴァーノ、フリゼール)やエレクトリック・ビバップ・バンド、トリオ2000で放っているジャズとは、おそらく現代ジャズのフロントを形成している。このフロント、と、メセニー、を、つなぐ感覚の領野、を、わたしはこの盤によって初めて想定できそうな気がしている・・・。なんだか書いてて、そら恐ろしいことをキーボードで打っているな、と、正直思う。なるほど、そうだったのか、と、おれはいま自分に教わっている。
この盤の1曲目を何度か聴いいるうちに、あれだけジャズとしてよくわからなかった『ユニバーサル・シンコペーション』
(途中)
今年は、フェレンク・ネメスというドラマーが登場した年だ。と、本稿のイントロにしようと思っていた。ので、そこからも書き出す。この10年のスパンで登場したジム・ブラック、ナシート・ウェイツ、ポール・ニルセン・ラブ、トーマス・ストローネン、マヌ・カチェ、本田珠也、いちお6人だな、おれがタイコ判をおすタイコは・・・(笑え!)。だいたい、あのデジョネットでさえ「おれの前にはエルヴィンもトニーもいたんだぜ、いまの若いひとは大変だよな」と語っていた(そもそもこの発言にはモチアンとの対抗意識はあると思うがサニー・マレイ、ミルフォードグレイヴス、ヨン・クリステンセンはやつの視野には入ってない、入っていなくてもちろん問題もない)が、ドラムンベースの登場、音響派的傾向、の、この10年にあって、ドラマーがシーンに登場することは容易ではない。またその才能を指摘するのも容易ではない。そのタイコ判つきタイコの中で、すでに音楽全体を構想(まさにメセニーのように!)できる才能を発揮しているという点ではネメスが一番手である。このCD1枚で、そこまで惚れ込む。
「パット・メセニー・グループの疾走感(ver.2.0)+コンポジションとインプロの相克という古くて現代的な課題の旅路を聴くこともできる。」・・・いかん、つい聴きながらつぶやいてしまった。
ギターのリオーネル・ルエケはアフリカ中西部出身で、ハービー・ハンコックが見出した逸材としてデビューしている(いま調べてわかった)。ルエケのギターの音、へんに外してしるようでそれでいて感覚的にはいい具合にどもっているような心地よさ。そしてまじに上手い。そんでやっぱり変態(YouTubeで観れるし)、音楽的に。
そしてピアノ、ベースは手堅く、必要十分に上手い。ときに必要以上に上手い。ピアノのアーロン・パークス23さいはカート・ローゼンウインクルと来日してたりするのか。パティトゥッチはあいかわらず上手いだけという経歴も本作での貢献は予想以上にプラスに働いている。
そして最後にリーダーのフェレンク・レメテ、ハンガリーのドラマー。ウエイン・ショーター作曲「E.S.P.」をのぞいてすべての曲を作曲・アレンジしている。・・・あ、ネメスはバークリーだけでなくボストンのニューイングランド音楽院も出ているのか。・・・そうか。ジョー・マネリ教授とも廊下ですれ違ったことくらいはあるな・・・。
おれはこのところ音楽について飽きっぽいところは猫以上で、3秒以上弛んだ音楽の流れには耐えられないでいる。この全編で70分あるCDは、聴きやすい疾走感を保ちつつ、弛んだところがない。音楽が瞬時の可変性を保ったまま、危うい緊張感のまま、5人の個々のミュージシャンのまさに図形的な配置の美しさの変化に耳は奪われるだけなのである。・・・いかん、何にでも書けるようなつまらないテキストになってきた。聴いてみたまえ。とにかくわたしはここでこの作品を掲げることで全世界のジャズジャーナリズムに宣戦布告をすることができる。稲岡さん、ありがとうございます。
よく読め。レーベル名は、Dreamers Collective Records、夢想家集団レコード、とでもいおうか。そのレーベルの作品番号1番が本作である。CDジャケの内側にあるメンバー写真には一緒に土星がプリントされてる。土星だぞ。
| 2007年12月12日(水) | 峰厚介ミーツ渋谷毅&林栄一『ランデヴー』 |
いつもおくればせなのはこのおれ。
豊島区中央図書館で峰厚介ミーツ渋谷毅&林栄一『ランデヴー』を聴き。■
このアマゾンのレビュー、最初の三ツ星はまるでおれが書き込んだような文体だが、たしかにわからぬわけではないその言い分、でもべつにプーさんに頼んだ録音じゃないし、
これを聴いておれは五つ星をまよわず付ける。
そうか、望月由美というひとの制作なのか。
今日更新されたJazzTokyo■では渋谷毅ソロ2作!なんてのがレヴューされている。
これも望月由美というひとの制作。ああ、これはすごい。
図書館で借りた分際で何を言うかと自分に言いたい。
しかし、おれの会社がまじに株式上場をする残業をさせないとて手取りが激減しているのだ。ほんにいい迷惑。
数日前に騒いだボーノが歌うアニメソングは19さいのアニメオタク長女が所有しているというので、新小岩駅前の中華屋でレバニラ定食をおごるかわりに貸してもらう契約がさっきメールで成立した。
渋谷毅のピアノソロ2種、これはもう聴く前にわかっている。
今年を代表するジャズディスクであることは間違いない。
んんん。
有馬記念が当たったら買う。
| 2007年12月11日(火) | hitomiの「体温」 |
天性の声を持つのにいまひとつhitomiは不遇から抜けていないままにまたぞろベスト盤で年末稼ぎに新小岩の路地に立つ娼婦のような風情ではないか。
「体温」■という1曲がことさらに輝く。それにしてもJポップの至宝ものの声だ。当時の彼女の瞳の表情の高み。
<2000年にシドニー五輪で金メダルを獲得した女子マラソンの高橋尚子が、練習中やレース前にテンションを上げる曲として「LOVE 2000」を紹介したことから、同曲が注目を集め再びチャートを上昇させた。>
とあるが、「LOVE 2000」の直前のシングルである「体温」にこそ、当時のQちゃんがこいで監督との文字どおりおれなんかがちゃかすことのできない崇高な想いを託したイメージとして聴いていたのではないか。直感的におれはそうだと思うよ。
もちろん「LOVE 2000」を聴いて走っもいたんだろけど。
そんなことより年間ベスト海外1枚+日本1枚は
フェレンク・レメテと死人(しびと)と確定させてはや4日、
しごとがつづいてアップできねえー
| 2007年12月10日(月) |
ニール・ヤングのCDをかけて早朝の国道を部屋に向かう。
ニール・ヤングのように生きたいと、音楽が思わせている。
| 2007年12月07日(金) | 『LIQUID BLUE / ケイ赤城トリオ』 ビデオアーツ(VACT-0001) |
(決定稿)
『LIQUID BLUE / ケイ赤城トリオ』 ビデオアーツ(VACT-0001) 2007.12.19発売
ケイ赤城(ピアノ)・杉本智和(ベース)・本田珠也(ドラム)
杉本智和(すぎもとともかず)、本田珠也(ほんだたまや)の名を刻みつけられる傑作ピアノトリオ盤が届いた。
この作品はトラックの後半に進むほどに演奏が高度に、ジャズの醍醐味に唸らされるように配置されている。1曲目は雰囲気ジャズ好きへの営業色濃厚、ピアノが奏でる祈りの感情はそのうちNHKあたりに起用されたいという祈りに聴こえ、2曲目から次第にジャズの核心に近づいてゆく。おそらく制作者にその意図はない。そのグラデュエーションは、杉本と本田のリズム隊に耳をすませれば明白で、聴き進めるつれて驚かされ、手に汗をにぎり、不意打ちをくらう。1曲目と相対するかの静けさではじまるラスト・トラックを聴くに、おれがおんななら惚れるぜこのタイコである。この二人の力量とこれからの可能性は相当高い。後半4曲の出来を展開させること、その先に21世紀のピアノトリオがある。
リーダーのケイ赤城は、マイルスデイビスバンドに在籍したという経歴も、なるほどと思わされるフェンダー・ローズのプレイ、が、聴きどころ、という前提は置いといて、これまでこのトリオを結成して7年、本作のコンポジションをマイルス作のトラック4(この演奏はECMファンには必聴)以外のすべてを手がけている。ケイ赤城は汎音楽的志向を強く感じさせるミュージシャンで、彼のコンポジションの展開の明確さは、杉本・本田という新しい世代の感覚、ある種の獰猛さ、を、活かすことに成功していると思う。強固に理に適ったピアノ・プレイもしくはコンポジションとのせめぎあい、ここを聴きたい。
空間プロデュースを手がけるTIME & STYLEが立ち上げるジャズレーベル<TIME & STYLE JAZZ>の記念すべき第一弾として発表された本作から、日本のジャズプロパーが果たせない新しさの萌芽を聴く。それは、杉本・本田という獰猛さのありように示唆されているのではないか。
| 2007年12月06日(木) | 沖縄の島とうがらし |
沖縄の島とうがらしを入手。
光が丘の大盛軒に持ち込んでギョーザのたれにくわえて食す。
ドンキで冷凍味の素ギョーザ118えん。
和歌山県産養殖ぶりの刺身580えん。
『LIQUID BLUE / ケイ赤城トリオ』 ビデオアーツ(VACT-0001) 2007.12.19発売
① SMILE IN THE RAIN 6:59
② LIQUID BLUE 6:41
③ RIPPLE EFFECT 6:46
④ BLUE IN GREEN 4:22
⑤ IF ANTS READ POETRY… 8:03
⑥ WINTER LIGHT 7:24
⑦ THE CHILDREN PLAY 5:57
⑧ ANOTHER WAY HOME 6:07
ケイ赤城(ピアノ)・杉本智和(ベース)・本田珠也(ドラム)
杉本智和(すぎもとともかず)、本田珠也(ほんだたまや)の名を刻みつけられる傑作ピアノトリオ盤が届いた。この作品はトラックの後半に進むほどに演奏が高度に、ジャズの醍醐味に唸らされるように配置されている。1曲目は雰囲気ジャズ好きへの営業色濃厚、ピアノが奏でる祈りの感情はそのうちNHKあたりに起用されたいという祈りに聴こえ、2曲目から次第にジャズの核心に近づいてゆく。そのグラデュエーションは、杉本と本田のリズム隊に耳をすませれば明白で、聴き進めるつれて驚かされ、手に汗をにぎり、不意打ちをくらう。この二人の力量とこれからの可能性は相当高いと思う。後半4曲の出来でCDを埋めれば、
リーダーのケイ赤城は、マイルスデイビスバンドに在籍したという経歴も、なるほどと思わされるフェンダー・ローズのプレイ、が、聴きどころ。
(書きかけ)
| 2007年12月05日(水) | 三澤寿喜「ヘンデル晩年の心意気〜音楽の母が挑んだオラトリオなど日本で研究・上演」 |
かみはひとをねこのせわをさすためちじょうにつかいあそばした
ヘンデルはなぜ音楽の母なのだオトコだのに
ある日、日本のヘンデル研究のパイオニアである渡部惠一郎先生のお宅でイタリア語のカンタータ「ルクレツィア」のレコードを聴き、衝撃を受けた。この作曲家の本領が最も発揮されたのは、声楽曲だと思い知った。
(三澤寿喜「ヘンデル晩年の心意気〜音楽の母が挑んだオラトリオなど日本で研究・上演」12月4日・日本経済新聞朝刊44面)
ヘンデル・フェスティバル・ジャパン ■
このおじさま、ひとりで好きなヘンデルの音楽祭をつくっているのにゆうき100ばい。
おれはコンポーザーズジャパンフェスティバルをそのうちおこなうのであるが、
おれがすきな曲聴きたい曲しか上演しないの。
いふくべあきらまつむらていぞうみよしあきら・・・
浦和第一女子高等学校音楽部の女声合唱のみなさんとは毎年なかよくしてしまうのである。毎年『詩篇頌詠(しへんしょうえい)』を聴けるのである。
100にんの女子高生。ふりそそぐひかりのおんがく。
こ、この世の天国ではないか。
| 2007年12月04日(火) | 藤枝守著『響きの考古学 音律の世界史からの冒険』平凡社ライブラリー |
今年の2月9日に増補決定版として
藤枝守著『響きの考古学 音律の世界史からの冒険』平凡社ライブラリーが刊行された。
この音楽ファンにとっての重要書籍を紹介せずに今年は終われない。
ハリー・パーチやルー・ハリソン(ジャレットが委嘱してピアノ協奏曲を作ったことでECMファンには有名)などの増補がなされている。
注のジェームス・テニー(1934〜2006)に
「パーチやヴァレーズ、ナンカロウとも交流があった」とあり、テニーの作品はハットロジーで何枚か聴いていただけだったので、聴きなおさなければ。
古代ギリシャから中国の音階やアラブ音楽まで俯瞰しながら現代までを扱ったもので、書物だから音が聴こえないにしても、イギリス・アイルランド地方に残るケルト人の純正三度が大陸に甘美な快楽をもたらして中世・ルネサンスの変化を起動させているとか、刺激的なことこの上ない。
微分音ジャズのジョー・マネリを契機に藤枝守さんの存在を岡島さんから教わったのですが、ジョー・マネリの愛好家が一向に増えていないぼくのまわりがさびしい。とってもさびしい。おやすみなさい。
| 2007年12月03日(月) | まんが『しゅごキャラ!』 |
わたくしが音楽サイトmusicircusの音楽守護神ガーディアンのキングスチェアをつとめるただまさのりさまだ。
まんが『しゅごキャラ!』■を夢中になって読んでしまった。
わー。
アニメ化された主題曲がばっちり!>■ ぜたいCDかう!・・・って!1っしゅうかんぐらい前にテレビでみてチェックしてた曲だったー!!!■
この圧倒的なパフォーマンス!みぎがわの赤チェックのこ!■嗣永桃子(つぐながももこ)★15歳/Berryz工房★高校1年生★生年月日:1992.3.6★血液型:O型
フツーにおやじだもん。
いた!きも!
長女が幼少の頃、おれが切り取ってファイルしてあったイワモトケンチの不条理12コママンガに相当な衝撃を受けていたとさっき話していて。
なんと、あのマンガはもう手に入らぬ状態ではないのか?
あのファイルは捨ててしまったのだろうか。記憶にない。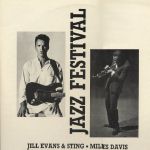
スティングとギルエヴァンスの共演海賊盤3LP。ユニオンの査定に出したら1100えん。やっぱ売らない。
| 2007年12月02日(日) | 銀杏BOYZ「光」 |
きよちゃんとひろったどんぐりをパソコンにひろげて、キースのブレーメンアンコール■でうっとりする休日の深夜。
笠懸にある岩宿遺跡の岩宿博物館に家族で出かける。
新田にある喜久屋食堂でラーメンと餃子ともつ煮。
イオン太田で原田知世『music&me』と銀杏BOYZ「光」(ジャケ写)を購入。
銀杏BOYZ「光」(12分超の力作)は、「きみのくびをしめる」という夢であれ幻想であれレトリックとして、そうとしか表現できないのか、それって甘くね?
月がかたむいたおわんのよう。
刀水橋のドトールでコーヒーをのんで、品川につくまで、ずっとおいかけてきた。
ラジオ深夜便でシャンソンを聴きながら品川から平和台へ。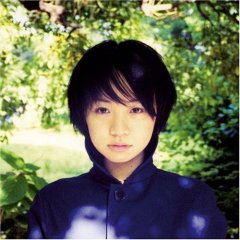
| 2007年12月01日(土) | 奈良の天河神社 |
12月に入り。
奈良の天河神社という音楽と芸術の神様がいるところへ導かれる。
■
養老天命反転地に行ったことを喜久屋食堂で子どもたちが話題に。
友だちに話すと、「どこそこ?」とかえされるという。
ここ読んで>■
荒川修作についての理解を深めること>子どもたちへ。
という、おれ。
ここ読んで>■
子どもたち。試験には出ないけど。
音楽やアートに接して、変容する自分というより、アートによって構築される身体、感覚、自我、としての自分に気づくということ。
子どもとの思い出とか恋人とかゼニへの執着とか言葉遣いとか、その音楽をこう感じるとかそう判断するとか、わりと固定的な価値体系で出来上がってしまっている自分、を、捨てられるかっていう気持ちもわからぬわけではないけれども、
アートが放つもの、が、おれという存在を再構築する、と同時に、おれはいわば消える。
そういったところから立ち上がってきたコトバ、が、傾聴に値するような気がすんだよね。