DiaryINDEX|past|will
| 2007年11月30日(金) | 商品名は「キュージョン」 |
キューピーとブラックジャック、顔の縫いあとがきちんとしてて髪型もかっこよくてキュート。
キューピーともぐろふくぞう(喪黒福造・笑うセールスマン)、かわいい指を前に出していまっす。
キューピーと妖怪人間ベロ、うぷぷ、髪は青いし、顔色わるいのにキューピーの顔だー。
ふたつのキャラがコラボったストラップ。その商品名は「キュージョン」■
つぶらやプロやら、たつのこプロやら、手塚治虫、ふじこふじお、エヴァンゲリオンやら・・・
これは商品としてかなり臨界を超えた天才性を感じるものだ。こ、ここまでやるう?
ここまで広範囲なプロダクション横断プロジェクトはこれまでなかったよね。
| 2007年11月29日(木) | ジョナサン・キャロルの『天使の牙から』 |
早朝に歌舞伎町の沖縄料理屋に行って、はじめてゴーヤ・チャンプルーをたべた。
ピリピリする辛くて透明な液体をかけて食べてたんだけど、20時間以上たっても、からだじゅうがピクピクよろこんでいて、指先までちからをこめたくなって、視神経がシャープに感じる。
ううう。またたべてえ。
夜は長女とごはんと買い出しと池上温泉。
「マスクしてるといい。あったかいし、おもいだしわらいしても、ばれなくていい」
と言って大井町の横断歩道で笑わせないでほしい。マスクにそんな利点をあげるひと、いねえよ。
5月に文庫になってたというジョナサン・キャロルの『天使の牙から』を買う。
いつも雑誌を買うおとうちゃんが文庫本買うのめずらしー、と、言っている。
ジョナサン・キャロルの世界に『死者の書』で出会ったのは、彼女が生まれた頃だったから、ちょっと不思議な感覚。
なんというか、枕の左側を見たらすやすや寝息をたてていた赤ん坊が、枕の右側に顔を向けたらいまの彼女になっていた、ようなイメージ。
ドライブしながら聴いたのはモンクのブリリアントコーナーズとケイ赤城トリオの新作プレヴュー盤。
ケイ赤城のほうはもう6回聴いている。
すごくよくて、理由はベースとタイコの起用にあったのが明白。
4日のプレス向けライブに都合をつけたい。
| 2007年11月28日(水) | フィルワックスマンとポールリットンのECMスティーブレイク制作デュオ作品『Some Other Time』 |
フィルワックスマンとポールリットンのECMスティーブレイク制作デュオ作品『Some Other Time』のジャケ。
完全即興というジャンルにライブエレクトロニクスを導入できるようになったのは、音色の微細な反応が技術的に高まったからであり、電気の音に対して好感するモードという追い風もあった。
だけど、感覚的には新しくない。むしろ古い。電気の音は、そっちの最先端モードからすると恥ずかしいくらいに時代遅れに聴こえる。
この作品で聴かれるのは、ワックスマンとリットンの欧州人としてのクラシックの素養という背景だ。思考法までが透けて見える思いがする。
それは彼らに刻印された同時代の詩情といったものであり、完全即興なるフィクショナルな身振りの裏側で、周到にある領域の表現は排除され、透徹した水準探査で編集された書物のようである。
ヴァイオリンは上手いし、パーカッションも完成されてるし、ああトラック14なんてドッキドキの短反応で構築された美しさ。
その破綻の無さは、息が詰まるくらいに見事なところがあり、そこがこの作品が傑作である理由だ。
ラストの「Some Other Season」はこの作品のすべてのトラックが途切れ途切れに反響してくるような奇妙な心地がした。
そいえばおれ。何かの間違いでチャイコフスキーとかシベリウスとか聴きに出かけたときに、「曲が始まる前にオーケストラが音合わせをして響かせたでしょ、あの時がいちばん今日のコンサートで良かったー」などと、素朴に思っていた時期もあります。
| 2007年11月27日(火) | ベートーヴェンの最後のピアノソナタや弦楽四重奏曲とは |
大江健三郎72さい。
いつぞやは朝日新聞のCMに出ててびっくりでしたが、
今日の読売朝刊19面。大江の新作についての記事で。
”芸術家的「晩年のスタイル」〜円熟ではなく破局の大転回”
大江氏は、トーマス・マンやジャン・ジュネなどの晩年の作品に言及したサイードの論考を読みつつ、ベートーヴェンの最後のピアノソナタや弦楽四重奏曲をくり返し聴いたという。
「これらの曲は円熟からはほど遠い、ヴェートーヴェン自身への裏切りのような大転回でもあります。一人の人間が統一できないバラバラなものが一挙に放り出された感じで。アドルノ(ドイツの哲学者)は、それを破局の情景であると言った。しかしサイードは、最も完成されて美しい、しかも新たな次元に至った作品でもあったと評価した。20世紀の音楽はシェーンベルグから武満徹まで、ベートーヴェンの晩年の破局から出発したのだ、と。僕はサイードの結論に賛成します」
記事の中、ベートーヴェンの表記が2つある・・・
なに、ベートーヴェンの最後のピアノソナタや弦楽四重奏曲とは、そういうものなのか。
聴きてー。
はずかしながら聴いたことないのであります。
| 2007年11月26日(月) | 21日に発売された三善晃の『レクイエム』 |
21日に発売された三善晃の『レクイエム』■。
こ、こんなすさまじいコトバによって構成されていたのだ。
おれ、初聴き当時、サウンドの音とイメージだけでこの作品を傑作だと判断していた部分が大きくて、
どんなコトバが合唱団によって空気をふるわせて(歌われて)いたのかは知ってたよ、
知って、たよ、
今回は、コトバの背景がみえてきて、いやおうなく、このコトバを発した場所に連れて行かれるようでもあり。
46さいになって、すこしは聴こえるようになったのだと思う。
感極まってライナーにある三善晃のテキスト(新稿)を写メールにしようとしたら音楽と感応したのか画像がこのように乱れた(こんな現象ははじめてだ)。
このライブ録音の現場にいたひとからの話では、観客席からはすさまじいオーケストラの音で合唱団の声がかき消されてしまって、必死の形相でくちを開いている合唱団が見えて、何が歌われているのかわからなかった様相であったとも。
いや、歌はデシベルでは聴こえていなくても、たしかにあったのだ。
コトバもデシベルでは聴こえていなくても、たしかにあったのだ。
そういう、状況も、また、すさまじく、正しかったのだと思う。
このCDの音源を手がかりにして(充実したライナーテキスト群)、
おれの場合、イラクの兵士が遠隔操作されたアメリカの兵器で瞬時に焼かれ死ぬ映像、を、見る、おれ、の現在、を、ジジェクをだしに?不自然に形状が揃ったサツマイモをスーパーで買っているおれ、の、現在、
何度か書いたようにおれにとっての三善晃は、あの生命体のような光のゆえんだ。オーケストラや合唱のスコアによって起動されている、はず、だ。スコアの中にひそんでいるはずだ。そこには指摘しうる分析しうる模倣しうる技法・技術があるはずで、ところが誰もその技法を継承していないのはなにゆえか。表現の必然という呪符で、なんぴとも持ち出せぬ、というのか。その謎、が、おれにとって三善晃を神格化させてもいる。いったいなんでこのような音楽の現象がホールの中に起こるのか。おれが音楽の神さまと奇を衒って言うのではない。あの生命体のように光る響きの正体。
参照点となるような手がかりはこの三善の意識のありかたではないだろうか。
三善は、歌詞は忘れてほしい、それが自らの力で、聴衆の中によみがえるために、と、願ったという。(『レクイエム』に対して)
| 2007年11月25日(日) |
愛の賛歌 越路吹雪 ■
Edith Piaf - Hymne à L'Amour ■
Jane Birkin & Serge Gainsbourg■ - Je T'aime... Moi Non Plus ■
トムとジェリー ■
と
ウルトラマン第一回
■
この映像の音楽体験が、最初の現代音楽体験となった世代がわたしなので。
| 2007年11月24日(土) | ジャレットへのインタビューがあるとするなら。 |
ジャレットへのインタビューがあるとするなら。
おれ、ジャレットに興味がなくなったなんてことないです。
見限れないの。永遠に見限らないと思うの。
硬派なジャズファンは「嫌いだから聴かない。あんな自己陶酔べとべとな表現をアートとは呼ばない。」て言い切るカッコよさがカッコわるいわ。
レイディアンスは特別に素晴らしく、カーネギーは経歴最下位の駄作、マイフーリッシュハートには倦怠感しか感じないわたしからキースへの4つのしつもん。
①ユニバーサルシンコペーションを聴いて(聴いてないはずない)、どう考えたか。
②ユニバーサルシンコペーションのガルバレクを聴いて、以前と異なった次元でのヨーロピアンカルテットを構想しなかったか。(April Fool記事でマイ・ソング再演カルテット再結成ニュースがあったけど、いやいやいや、冗談じゃなくていいって、現在の彼らならアリだって。すごいもんできるって)
③新しい世代のジャズメンの演奏を聴いたりしているのか。サックスを加えたポールモチアンとのカルテット、には、いまだ可能性があると思うけれども、どうしてリスクをとらないのか。
④スタンダーズに飽き飽きしている一部の長年のファンとしては、保護者同伴で自分のすがたを鏡に映して自分との会話に自閉し続ける現在のジャレットがほんとうに痛々しくさえ見えます。2000年以降、ジャズメディアでの饒舌とは反比例して。
・・・やっぱり4番目の質問はやめよう。というか質問になってないし。中傷だし。
上記3つのしつもんは、アリだと思います。
聴きたまえ!東京ラストソロでの「ブレーメン・アンコール」!!!■
ロックミュージシャンのようなウタゴコロと無謀ですらあるロマンチシズムを基盤にしていた音楽だろ?
こんなもん、ジャズじゃないだろ、ポールサイモンとかミスチルだろ。
フォークでありフリーターであり70ねんだいであり陳腐でさえあるだろ。
こういうキースの録音を復刻することも強く希望する。そう、二度と戻れないキース・ジャレットに、ぼくは出会いたい。
「Keith Jarrett - I Loves You Porgy」■
アルバムとはまた違った、撮影用モードでおそるおそるまとめているテイク。
あ、見つけた。「マイファニーヴァレンタイン」の映像。やはりな、このパートはこんなに気持ち込めた表情で鍵盤に指を置いていたのか。なんかキースじいちゃんの表情がいい。なんか許せる。いまでも表情を観客に向けてしわくちゃにするのね。笑えるけど、胸がきゅんとする。そうね。ありがとうキースって、まだ言わないね。■
やっぱり、今のキースは今のままでいいや。
| 2007年11月23日(金) | Jazz Magazine (仏)誌でECM特集だ! |

そもそもECMを通史的に重要作品を挙げるなどという、たいへんに意味のない、
この上なく魅惑的、蠱惑的、抑圧的な、
おそらく、世界的にもおれにしか許されていない所業を、大陸の西のはずれにある美辞麗句を国是とした没落した小国の編集子がなすなど、という、狼藉を、おれはゆるさん。で、そもそもこのラインナップ、「耳がない!」としか言いようがない。見てみ。>■
思ってもみたまえ、これらの作品をもってECMの至宝と思われるの、あれもないこれもないそれもないどれもない・・・
いや待てよ。
このようなかたちで誤った道を指し示すことが年長者の責務である、とも考え得るし、
自立した耳が、独力で登攀するように、という老婆心、
すべての道はローマに通じるわけだし、
・・・なるほど。
いや、さらに待てよ。
ここにアップされている作品群はジャレットのカーネギーホールを除いて、それなりに聴く価値のあるものばかりである。ただし、そのミュージシャンの代表作だと言えるかというと、はなはだ。
それより、ニューシリーズを除外しているのね。
冷静に考えると、いわゆるひとつの拡販記事にすぎないのだった。
| 2007年11月22日(木) | ヤマハはベーゼンドルファーを買収したらだめです |
(京という単位をはじめて新聞でみたです)
全世界のピアノ好きに衝撃!
「ヤマハのベーゼンドルファーの買収交渉大詰め」日経朝刊13面。
1828年設立、世界最古のピアノメーカー、ウイーンの至宝とも言われるベーゼンドルファー社は、ヤマハと地元ピアノメーカーの二社が有力候補となって買収交渉が進められており、近く一社に絞られる見通し。
それって、どうなの。
こないだはマンフレットアイヒャーが・・・この日に書いたな>■>おいおれ、いいこと書いてるし、こんなリンク先をはってるし、夢のようなレコードだ、まで言ってるし、すべて忘れてるし、だいじょうぶか、おれ。
ヤマハがベーゼンドルファーを買収するってことはだよ、
ヤマハ音楽教室が桐朋学園大学音楽学部を合併するとか、
ヤン坊マー坊天気予報のテーマをベゼンドルファーでポール・ブレイが弾くってことに等しい、
ように、ぼくは思う。
もっと言えば、
こうだくみがビリー・ホリディの版権を手に入れるとか、
えびちゃんは山瀬まみよりかわいいと主張するとか、
あさしおがあさしょうりゅうのおやかたをするとか、
とか、そんな不自然な、みのほどしらずな、決定的にしくじる感じがする。
してはいけないこと、では、ないのだろうか。
じつはほんとにまずいのではないかと思っていたりする。
きをとりなおして、マルチャンのカレーうどん3玉ぐいしてねます。
| 2007年11月21日(水) | ノイズ |

今ではノイズの名盤らしい、この日米の2枚組■。発売された頃、ジャズ喫茶いーぐるっ子だったぼくは後藤さん(後藤雅洋さん・店主・音楽評論家)によくCDを聴かせていただいていて、後藤さんはお客さんがいなくなったあと、この2枚組をあのJBLのスピーカーで大音量でかけたときいて驚いていた。日本のほうが断然にセンスがいいよね、と、さすがに後藤さん。あー、おれの感じ方ってあってるんだー、と、すごく勇気をもらった記憶があります。その後のおれは増長しすぎてますので来月から改めます。
と、そんなイントロをつけて、さっき見つけたノイズについてのちょっとすてきなCDのラインナップにうっとりしてしまうブログ、ここに置いときます。
■
メルツバウの新譜が毎日入荷していた音盤屋が群馬の伊勢崎にあったことを思い出します。
毎日メルツバウを聴いてコンプリートできたら・・・と、うっとりしていました。
ああ、今月もかねがないー。とか言いながら、おとといは日本の現代音楽のCDを2種入手。またCD売らないと群馬の子どもたちにごちできないぞ。品川の長女と池上温泉行けないぞ。がんばれ、おれ。
| 2007年11月20日(火) | 「俺たちの明日」エレファントカシマシ |
(画:ただこいいちろう)
王子の北とぴあ・さくらホールへは、赤羽をまわって行ったんだよね。
赤羽、っていうと、よー
エレファントカシマシの地元だ。
彼らがソニーから契約解除されてた時期、毎月彼らのギグに足を運んで応援していたおれだ。応援しすぎて赤羽の街を歩いたりしたものだ。
| 2007年11月19日(月) | Parish / Thomas Strønen (ECM1870) 2004 |
(どいつがストローネン?)
はじめて聴くミュージシャンの、最初の数音でその才能に圧倒されることほど、リスナーにとって幸福なことはない。
ボボ・ステンソンを保証人にしたサックスのカルテット、ECM登場作、どーせつまんないんだろ、という程度の認識で聴き始めた。
トラック1の最初の数音で、「わ・・・。このタイコのセンスは尋常なものではない。この作品は、このタイコがキーだ。」と、ドラマーがリーダーとなっていることを知らないで聴いているわたしでした。
かねがね、ジャズ界にはポール・モチアンの後継者が存在していない事実を痛感してきた。
このトーマス・ストローネンには、ジャズ界でモチアンの存在になれる目がある。
どうもストローネン本人は鳴り物をパカパカ叩いたり反応しながら演奏を左右してゆくことが好きそうな風情ではあるけれども、ブラシさばきの具合もよいし、やはり、タイコを叩いて演奏の時間を伸び縮みさせる能力(菊地雅章が使う表現でいうところの)、これがある才能をようやくジャズ界は得ようとしていると思う。
ストローネンはノルウェー出身で、ノルウェーのドラマーというとポール・ニルセン・ラブだけじゃないようだ。自分の国にヨン・クリステンセンみたいなドラマーがいることをいやおうなく意識して育たらざるを得なかった世代である彼らは、いい抑圧を受けて世界レベルの才能を培ったと思ってみたいぞ、わたしは。
ECMへの登場作品としては、即興あり、自作のコンポジションあり、演奏のバリエーションも提示してあり、ということで満点だと思う。13曲目「イン・モーション」を聴いていると、ジャレットのヨーロピアン・カルテットを揶揄しているのと同時に越えているものを感じる(そもそも越える意義もない時代がかったハードルに過ぎないが)。
ほんとに、ストローネンは音楽が視えている稀有なドラマーである。72年生まれ、35さい。いやー、できることなら、ノルウェーにとどまることなく、今からでもニューヨークへ出て数々の才能とセッションして、21世紀のジャズをおじさんに聴かせてほしい。
なお国内盤はノルウェーのジャズやロックに詳しい矢部瑞保さんが執筆しており、ECMの国内盤で彼女が書いているものは買いであります。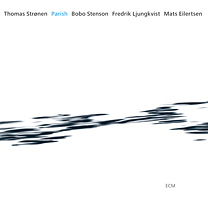
それにしてもセンスのないジャケ。このようなオールドスタイルを押し付けられて大切な自分の作品を出さざるをえないミュージシャンにおれは同情する。
| 2007年11月18日(日) | 藤井宏樹&松下耕指揮によるJOINT CONCERT「〜三善晃の作品をあつめて〜」 |
三日月の輪郭が、冷たくなった夜空にことさらくっきりと映る夜に、三善晃の作品で構成された合唱コンサートのことを記す。
藤井宏樹&松下耕指揮によるJOINT CONCERT「〜三善晃の作品をあつめて〜」■
この日記で、もっとこのコンサートをアピールすべきでした。しばらく言葉を失うくらいに感動して帰ってきました。
>Gaia Philharmonic Choirによる 混声合唱のための 『地球へのバラード』(詩・谷川俊太郎) 1983
>うたあい による 女声合唱とピアノのための 『三つの夜想』(詩・村松英子) 1985
>国立音楽大学女声合唱団ANGELICA による 女声合唱とピアノのための 『虹とリンゴ』(詩・宗 左近) 2004
>合唱団ゆうか による 合唱組曲『五つの童画』より(詩・高田敏子) 1968
>合同演奏で 女声合唱曲「麦藁帽子」(詩・立原道造) 1963
>合同演奏で 女声とピアノのための組曲『わらべうた』より 「あきかんうた」(詩・谷川俊太郎) 1963
>合同演奏で ― ピアノのための無窮連祷による ―「生きる」(詩・谷川俊太郎) 2000
>合同演奏で 「木とともに 人とともに」(詩・谷川俊太郎) 1999
コンサートの1曲目、『地球へのバラード』は、musicircus■に紹介した「赤毛のアン」と音楽の骨格を同じくする、宮崎駿アニメの無重力感覚を先取りしていたようなナンバー。
三善晃■・・・え!吹奏楽曲で「札幌オリンピック・ファンファーレ(1972)」なんてあるのか?これを聴かずしてミヨシストを名乗れぬではないか。だれかおいらに聴かせてくれ。・・・それはさておき。
どの合唱曲も、聴いてよかった。
4つの合唱団のクオリティの高さ。
くにたちおんだいの女子大生たちは桜花賞を思わせ、合唱団ゆうかは秋の天皇賞、うたあいは秋華賞、ガイアはマイルチャンピオンシップ。
やはり古馬たちの水準の高さは別格なものだ。そしてそれぞれに感触が微妙に異なるシルクの白い布のような美しさをたたえている。
そもそも4つの合唱団がこれだけの作品をくりひろげるなど、ありえない贅沢である。
80にんを超える合同合唱団による後半、「麦藁帽子」、このスケールで響きわたること、このホールの響きのよさ。息をのむ。
2004年に初演されたという『虹とリンゴ』(詩・宗 左近)。
宗左近(そうさこん■)の詩のすごさ、を、おれは今日まで知らなかった。
レクイエム、響紋を経て、なお。この作品の清浄・・・あえて、清浄。
合唱というのは合唱曲というジャンルではなく、同じときに響きあうことを共有する、人々が生きている時間のこと。
そんな、言葉にしてしまうと恥ずかしいものだけど。
三善晃の、合唱の歴史を変えた側面をもあぶり出し、現在のコンポジションにまで触れた選曲と構成にも、この公演の成功は支えられた。
プログラムは最近の2曲に至り、三善晃の全作品がひとつの交響曲になっているようにぼくには意識させられた。この明快な飛翔、それは速度。未来の子どもたちを導くような速度。
三善晃さん本人も会場に聴きに来ていて、ぼくは席ひとつ離れた後ろ。指揮者のおふたり、合唱団のみなさん、そして立ち上がってふるえながら手をあげる三善さん、会場の拍手、伝わる祈りと感謝の空間は光を放っていた。
| 2007年11月17日(土) | Mr.Children 19才の歌 この雨上がれ at 渋谷ラママ |
Mr.Children 19才の歌 この雨上がれ at 渋谷ラママ
■
11才の歌
Bianca Ryan from America's Got Talent
■
マット・マネリ 37才の演奏
Club d'Elf 8-17-2007 The Stone Church 4 of 4
■
いきものがかり 茜色の約束
■
Moondog Music これはムーンドック好きの集団なのかな
■
バルセロナ フレディマーキュリーの到達 しびれるう
Freddie Mercury Last Performance (Barcelona)
■
トーマス・スタンコ
■
Keith Jarrett - Umbria Jazz Festival at Perugia, Italy■
paul bley performance
■
| 2007年11月16日(金) |

高橋悠治 / ディスタント・ヴォイセス (Denon COCO-7977)
1.Distant Voices
2.Fliyng Off
3.Midsummer Blues
4.サマルカンド
5.タクラマカン
6.ロブ・ノール
Steve Lacy - soprano sax 1,2,3
高橋悠治 - piano ect
小杉武久 - electric-violin 1,2,3
佐藤允彦 - piano 4,5,6
1975年7月24日 1,2,3
1974年7月3〜5日 4,5,6