
|
 |
| 2003年02月21日(金) ■ |
 |
| ◆新国立劇場バレエ『ラ・バヤデール』 ザハロワ、ゼレンスキー、西川貴子、イリイン、他 |
 |
 ニキヤ: スヴェトラーナ・ザハロワ ニキヤ: スヴェトラーナ・ザハロワ
ソロル: イーゴリー・ゼレンスキー
ガムザッティ: 西川貴子
ハイ・ブラーミン(大僧正): ゲンナーディ・イリイン
新国立劇場バレエを見るのは、昨年の『こうもり』以来。その前は開場記念公演の『眠れる森の美女』ということになるので、考えてみるとあまり見に来ていないことになります。(他公演では来ていましたが、)
いずれもゲスト出演日ばかりなのでちょっと非国民ではありますが、既に沢山の固定のファンが付いているようでしたので、嬉しい気持ちになりました。
今回の全体の印象の良かった点は、やはりゲストが素晴らしかったということと、繊細な舞台美術の色彩が美しかった、会場が広くないので、音響に迫力があった等…。
だだ、スピーディーな展開と、演出上削除された部分を考えると、他の『バヤ』と比べて、薄味地味、物足りなさも感じてしまいます。(音楽もスピーディな展開になるように編集されてるとのこと)
全体に早めた分、最後の「寺院崩壊」場面を長めにやるのかと思ったら、結構一気にやってましたし…。
『ラ・バヤデール』は有名な作品ですが、これまで日本のバレエ団ではあまり無かったものです。そういった作品がこの国立のバレエ団にあるということは、意義深く嬉しく感じます。
さて、感想ですが、1幕1場、インドの寺院の場、寺院のセットは本物のような重厚な石造りの質感のあるもので、とても立派な印象。
苦行僧役男性ダンサーの迫力ある踊り、そして大僧正役のイリインは説得力ある演技で気に入りました。
そして、ニキヤのザハロワが登場すると暗い舞台にあの美しいシルエットくっきりと浮かび上がり、やっぱり美しいとしか言いようがありません。マグダヴェヤにソロルが待っていると告げられたときの輝いた表情、大僧正に対する拒否の表情、どれをとってもニキヤになっていました。
ゼレンスキーの舞台を見るのは久しぶりで、お変わりないかちょっと心配だったのですが(余計なことですが…)、いやぁー何か、若々しく、より引き締まった印象で、すっきりとしてとても美しかったです。相変わらずキレと迫力があり踊りが素晴らしい。
身長が高い2人が踊ると見入ってしまうほど綺麗。
宮殿セットは重苦しくなく、透かした細工が見事な造りでインドの夏の離宮という感じ。
1幕2場ではいよいよ三角関係のお相手、ガムザッティが登場します。
今回は新国のソリスト西川貴子さんがこの重要な役を務められていました。彼女のガムザッティは雰囲気が、金持ちの娘というよりは、どうしてもマダムに見えてしまい、演技もちょっと形式的に見えてしまいました。
踊りのテクニックは遜色ありませんが、ソロルと一緒にいるときの娘らしい恋心を表現してほしかったかな。(ジャンペの踊りを2人で見ているときとかも)
ソロルも何かシラッとしていたような感じがしますし…。
また、佐藤崇有貴さんがラジャー役というのが不思議です。あんなにお若いのにガムザッティの父親というのは、身長もすごく高い訳ではないし、キャラクター専門の熟練した人が努めた方がいいように思うのですが…。
第2幕、婚約式の場は豪華な色合いというより、アジアンな雰囲気の若竹色・濃い桃色を基調としたさわやかで落着いたセンスの良い美術・衣装でした。
どの版でも、ここで色々なディベルティスマンを見せてくれます。壷の踊り、黄金の神像はありましたが、鸚鵡の侍女たちとか、太鼓のインディアンダンスが無いのが残念。個人的に好きなので…。
本編にあまり関係なくても華やかにする要素なので見たかった。
ソロル・ガムザッティのパ・ド・ドゥは2人で踊るときは、合わそうとしてチョット一生懸命っぽく見えましたが、ソロは2人とも立派で迫力ありました。
そしてニキヤ登場。ソロル・ガムザッティは仲良く一緒に座って手など絡めあっていましたが、ソロルは動揺の様子。
ザハロワ(ニキヤ)の悲嘆にくれながら踊る柔らかな長い肢体を見ると、もう日本人では正直、かなわないなと思ってしまう。それほど美しい肩甲骨から滑らかに動く腕、真直ぐで長い足の見事さ。しかも非常に丁寧に踊るのですもの。
花篭を受け取ったときは一変して全身で喜びに満ち軽やかに踊ってました。
最後、蛇に噛まれニキヤが死んでしまったときのソロルの演出は、ニキヤを心配するわけでもなく、一直線に走ってその場を立ち去るというものでした。これってどうなの?
私は違和感を持ちますが、牧氏は現代風の味付けを各場面でしているということですから、無責任ソロルもその一部なのでしょう。
第3幕「影の王国」はコール・ドのダンサーの最大の見せ場です。暗く急な狭い坂をアラベスクを繰り返し、下りてくる様子は圧巻ですね。衣装は基本の白地にしっかりとした模様が入っている凝ったもの。私はもっとシンプルな方が好みですが…。
過酷で集中力を要するこの場面をしっかり踊っていたコール・ドの皆様に拍手です。
暗い背景にザワロワが白いチュチュ姿で登場すると、月光を浴びた水晶のように硬質の輝きを見せます。ゼレンスキーとのゆっくりしたアダージョはポーズからポーズへの移行が滑らかで、派手な動きをする訳ではないですが、見ているものに感動をあたえ、“美しい形”に魅せられてしまいます。もっと見たい! ソロルは本当にニキヤを愛していたというのが伝わる踊りでした。
3幕4場の寺院崩壊は、本当にドサッと建物が崩れるので危険すら感じる演出でした。驚いたー!!
最後はニキヤに導かれながらも力尽きるというものでした。
|
| 2003年02月16日(日) ■ |
 |
| ◆『バレエの美神』(最終日) 出演者:プリセツカヤ、ジュド、ハート、ルジマートフ、他…レニングラード国立バレエ |
 |
雨の日曜日。開演は午後3:30からでした。
【第1部】
◆ 『眠りの森の美女』ローズアダージョ (E・エフセーエワ、& シヴァコフ、モロゾフ、クリギン、リャブコフ&レニングラード国立バレエ)美術、背景
エフセーエワのオーロラ姫は、あまり初日見た印象とあまり変わりません。相変わらず表情豊か。本当にまだ大人になりきっていない、両親に可愛がられてすくすく育った娘という印象です。元気良く踊ってますが、スポーティーではなく甘―い感じ。
◆ 『パ・ド・カトル』 (シェスタコワ、ペレン、ハビブリナ、クチュルク)
初日よりも面白く感じました。シェスタコワは細く長い腕の動きが繊細で美しい。
ペレンは、前から思っていましたが、表情が硬くつまらなそうに見えてしまうところが苦手でした。今回は堂々としていて貫禄もあり、動きは良いと思ったけれど、もっと笑顔が自然に出来るようになればいいのですが...。
ハビブリナは4人の中で一番体格よく、こういった作品では前世代のバレリーナ風に見えて私は好ましいと思いました。
クチュルクはしっとりした雰囲気の踊りを見せてくれました。容貌も美人さん。
◆ 『眠れる森の美女』グラン・パ・ド・ドゥ (ヴィシニョーワ・コルプ)
最終日だけ追加上演してくれた演目。特別だったのか、今まで断っていたのか、光藍社のHPではプロに含まれてる時期が会ったと思いますが…。
レニングラードバレエの『海賊』出る出ない問題を見てしまっただけに、気難しいのかなどと思っちゃいましたよ。
まぁ 踊ってくれたんで、嬉しかったけど…。
ヴィシニョーワの踊りは、やっぱりいつも間違いなく良いんですが、最高な状態の時は、よりもっと良かった気がします。
『チャイコ・パ・ド・ドゥ』のときは、伸びやかで彼女の強い個性に合っていると思われるのですけど、オーロラは抑制している部分も含め、作りこみすぎている印象もあり…。
でも輝いていてオーラは凄いです。今後は演技や、繊細な部分も見てみたいな。素晴らしい逸材だけに…。
コルプの成長ぶりも確認できました。前回キーロフ来日公演の時の軟弱っぽい王子から頼れる王子に変身してしていて…。(コルプの顔って何かボリショイ系に見えるんですけど…)
◆ 『ロメオとジュリエット』バルコニーの場 (ザハロワ、ファジェーエフ)階段のセット、(ラブロフスキー版)
初日は正直言って、ザハロワの高評価の噂ばかり耳にして、でも実際見てみるとサラッとして何か観客に伝わりきれていないような印象でした。
でもこの日は作品のもつ、繊細さ、強さ、美しさが前面に出ていて心のもやもやが取れました。本当に良かった。
なぜかウラノワの『ロメ・ジュリ』映像を急に思い出して切ない気持ちになったり、とにかく美しい。
腕、足のフォルムのよさ、ポエジー溢れていて短い時間でしたがのめり込んで見てました。ファジェーエフも情熱的で良かった。
◆ 『ドン・キ・ホーテ』グラン・パ・ド・ドゥ (フィリピエワ・マトヴィエンコ、レニングラード国立バレエ)
相変わらず達者な2人。前回同様やっぱり大盛り上がりでした。安心、安心。
【第2部】
◆『ラ・シルフィード』グラン・パ・ド・ドゥ (レドフスカヤ・クズネツォフ、レニングラード国立バレエ)背景
レドフスカヤはやっぱり好き。本当に軽やかで清潔で柔らかで。嫌な癖が全く無く、優しい雰囲気をかもし出します。
クズネツォフ君は人柄が滲み出るような、好青年ジェームズでした。今回のほうがより良くなった気がします。
◆『シンデレラ』グラン・パ・ド・ドゥ (シェフェール・ローラント)
2度目に見た印象は。いやぁーローラント君の追いかけぶりが、エッチっぽい(あの目線)。かなりしつこい男&まんざらでもない女。なんて見方をしてしまいました。(笑)
◆『牧神の午後』 (プリセツカヤ・ジュドー、レニングラード国立バレエ)背景
ジュドは相変わらず表現力のあるダンサーだと実感。いつまでも見ていたかったなぁ。上品&セクシー牧神でした。
プリセツカヤは初日より大げさ演技は抑えられてました。
もう“ザ・存在感”な人。
でもこの方のエンディング登場芸は長く見ていたいです。はい。
ニンフ達は幾分初日よりあわてて無いですが、まだまだ…。
◆『ライモンダ』グラン・パ・ド・ドゥ (マハリナ・マトヴィエンコ)
マハリナは相変わらず豪華。特にこの日は音楽のテンポも緩急つけられて、キメる所、たーぷり魅せるところ、特にソロは酔わせていただきました。
エキゾティックな演目(音楽)にピッタリとハマるお人だわ。
逆にオーロラ役とか、今は想像出来ないけれど。(見た事あるが…)
マトヴィエンコ君は元気いっぱい頑張ってました。
でもお相手は、頑丈な“男”って感じの人で見てみたかったな。
◆『チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ』 (ヴィシニョーワ・コルプ)
見た事無い人は、是非見てほしい。もう職人芸。最高です。ヴィシニョーワの『チャイ・パド』を見ずしてヴィシを語るなかれ。(笑)
あのスムースさと粘っこさ、余裕ある表情。全てが絡み合い、誰も真似し得ない究極のパ・ド・ドゥに…。やっぱり一番彼女の個性に合っていると思います。
おまけのように書きますが、コルプも素晴らしかった。昔よりホント、力強いし柔軟。
【第3部】
◆ 『ジゼル』第2幕 (ハート・ルジマートフ、)レニングラード国立バレエ)美術、背景アリ
やっぱりメロウな独自の陶酔世界でした。ルジマートフ以外にこのような雰囲気のお方はいらっしゃいませんね。この先どのような芸に到達するか見守っていきたいと思ってますが…。
さて、今回は暖かく見守る母と、生きる術を知らなくて泣きじゃくっているような(イメージ)息子のような印象。ルジは最後の方ではいわゆる自立している大人、あるいは男っぽさはまるで無く、ただただ別れるのが受け入れられなくて駄々っ子のように悲しんでた子供のような印象。(母性本能くすぐられる人多いのでは、)
逆にハートは、ウィリーに狙われたアルブレヒトを、絶対に守るんだと、毅然とした強さをみせ、母が息子に見せるような、自愛に満ちた優しさを彼に対し垣間見せていました。 とこんな風に感じましたが…。
◆【カーテンコール】 (全員)
前回と同じ、女王プリセツカヤを讃える演出。 この日はジュドも牧神のふん装のまま登場していました。
そして最終日ということで華やかに舞台天井からキラキラテープとキラキラ紙ふぶきの演出。この瞬間のなんて綺麗なこと! ダンサーの表情も輝きます。
3部構成なので長かったけれど、素晴らしい数々の作品とスターたちを堪能できました。よかったー
|
| 2003年02月14日(金) ■ |
 |
| ◆『バレエの美神』(初日) 出演者:プリセツカヤ、ジュド、ハート、ルジマートフ、他…レニングラード国立バレエ |
 |
仕事を早々と切り上げ、急ぎオーチャードホールヘ。この公演は、出演者がケガや、所属バレエ団の都合など、たびたび変更がなされましたが、観客が満足するような沢山のスターが集結し素晴らしいパフォーマンスを見(魅)せて下さいました。
【第1部】
◆『眠りの森の美女』ローズアダージョ (E・エフセーエワ、& シヴァコフ、モロゾフ、クリギン、リャブコフ&レニングラード国立バレエ)美術、背景アリ
幕が開いたら、ガラ公演だというのに、美しい宮殿の庭に貴族たち、そして音楽と共に四人の王子や女官達などたくさんのコール・ドが現われ、オーロラ姫役のエフセーエワが登場しました。天性のものと言ってよいほど、非常に表情豊かで初々しく無邪気感じのオーロラという印象を最初に持ちました。
バランスも安定していましたし、アチチュードの高さもかなり高い位置でキープされていました。レニングラード国立バレエ団の期待の若手、エフセーエワは2001年のワガノワバレエ学校の日本公演でも主役を踊り注目を集めました。
今も変わらず愛らしい雰囲気。
まだ若いですが、観客に表現をうったえる力も備わっていると感じました。
そして、このチャイコフスキーの『眠り』ローズアダージョですが、こんなに幸福感を感じられる音楽を私は他に知りません。開幕から美しい場面にウットリしました。
◆ 『パ・ド・カトル』 (シェスタコワ、ペレン、ハビブリナ、クチュルク)
薄いピンクの柔らかい布地のロマンティックチュチュ姿の4名のソリスト。音楽といい振り付けといい大変クラシカルな作品ですね。
個性をそれぞれ出すのは限られていますので、なんとも言いにくいのですが、あの優雅で柔らかい腕の動きはワガノワメソッドの真骨頂でしょうか。
◆ 『ロメオとジュリエット』バルコニーの場 (ザハロワ、ファジェーエフ)階段のセット、(ラブロフスキー版)
キーロフの若手による美しいドラマティックな場面の再現ですが、終始繊細なジュリエットと若さ溢れるロメオという感じでした。
どちらかというとマクラミン版の激しく情熱的なバルコニーシーンを見慣れてましたので、とりわけ今回は上品な印象。抑え切れないほどの気持ちの爆発というよりも、純な心をもつ若い2人美しい逢瀬という印象が強いです。
しかし、演奏に関しては、音に厚みがなく、切れ切れな感じがして残念に思いました。本当はもっと盛り上がるはずですよ。
◆ 『ドン・キ・ホーテ』グラン・パ・ド・ドゥ (フィリピエワ・マトヴィエンコ、レニングラード国立バレエ)
ガラ公演には付き物の、この『ドンキ』ですが、今回は、レニングラード国立バレエのソロ部分&コール・ドも入り(しかも金色の衣装)より華やかに1部を締めくくりました。
さて、フィリピエワ、マトヴィエンコのカップルですが、もうこの演目お手の物とばかり、難しいテクニックを完璧にこなし、凄い拍手を受けていました。お互いに慣れて信頼している相手ですので、余裕もあり魅せてくれます。
フィリピエワのフェッテは片手を腰位置にキープしたままの難しいポーズでダブルも入れて回りきっていましたし、バランスを長く取ったりと観客の目線を釘付けにしました。マトヴィエンコはピルエットにしろジャンプ系のテクも際立つ巧さで、しかも爆発力があるので見ていて気持ちよかったです。
【第2部】
◆ラ・シルフィード』グラン・パ・ド・ドゥ (レドフスカヤ・クズネツォフ、レニングラード国立バレエ)背景アリ
美しい森の背景とシルフィード達。
絵のような場面の中にレドフスカヤ。シルフィードはガラ公演では、ジェームズ役の男性より目立たない気がしますが、しかしレドフスカヤが踊ると何ともたおやかで優しい雰囲気の舞台になるような印象をいつも持ってます。
ジゼル、ジュリエット、キトリ何を踊っても素晴らしいですし、余分な力が入らない自然な感じが好きです。今回は拝見できて良かった思うと同時に、演目的にもったいなかったかなとも感じてしまいます。クズネツォフもいい人そうなイメージでカッチリ踊ってましたが、私にはセルゲイ・フィーリンの素晴らしいジェームズが頭に残っていて…。
◆『シンデレラ』グラン・パ・ド・ドゥ (シェフェール・ローラント)
モダンな作品もガラの中に挿入してくれて、公演全体としてのいい清涼剤となり、私的には嬉しかったです。観客にも喜ばれてましたし…。
ああ、でも、取りやめになった、マイヨー振り付けの新作『LA BELLE』が気になるー。
パンフによると《水を湛えた川を思わせる背景の中、長い長いキスを交わしながら抱擁するふたり。
究極の愛のパ・ド・ドゥが期待出来そうだ》とあります。見ときたかったなぁ。
(2004年7月モンテカルロバレエ来日公演でLA BELLEは上演予定とのこと)
◆『牧神の午後』 (プリセツカヤ・ジュドー、レニングラード国立バレエ)背景アリ
この作品、色彩感がある音楽も好きですし、何よりもジュドの牧神を生で見られるチャンスだと思い楽しみにしていました。(ビデオ版好きだったので)
ジュド、良かったです。
今まで他の人が演じたのを見ると、何か、ぼやけた印象を持ってしまい、私の中でジュドの牧神がどうしても基本になってしまっていたので…。
役を選び、まだ暫らく踊り続けて戴きたいと願っています。
プリセツカヤのオーラはさすがと思いますが、恐怖を感じた演技が、ちょっとオーバーに感じました。
でも考えぬいた演技というのは伝わりましたし、何より舞台に立ってくれたことに意義があるのですよね。
あと、コール・ドのニンフが最悪。なれていないのか、それぞれのグループがバラバラでしたし、合わなくて、手を引っ張って退散とか、何か慌てていた感じがしました。ギリシャの壷の連続模様からヒントに作られた作品ですので、独自のフォーム、スタイルを守って演じてほしかったです。
◆『ライモンダ』グラン・パ・ド・ドゥ (マハリナ・マトヴィエンコ)
マハリナは大好きなバレリーナで、今まで色々見てきましたが、『ライモンダ』は初めてです。
マリインスキー劇場でグリゴローヴィチ版『ライモンダ』を初演する際、彼女がタイトルロール踊ったそうで、思い入れもあるのではないでしょうか。
衣装は、ボリショイと同じ様なデザインで、あそこよりもくすみの無い鮮やかな青でした。
踊りは、ロイヤル、パリオペラ座よりも間のアクセントをつけない、あまり硬くキッチリしすぎない印象。それにしても艶やかで迫力あり、彼女が登場するとくすんだ背景でも(今回かなり地味寂しいバック)、華やかな場面に見えてしまいます。
再び登場したマトヴィエンコは立派に努めていましたが、大きなマハリナと組むと身長と体格が合わない気がしました。
中世十字軍の騎士というよりチャーミングさが際立った印象ですが、踊り的には申し分なく、急遽変わった代役を見事に果たしていたと思います。
◆『チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ』 (ヴィシニョーワ・コルプ)
いやー見事の一言。ヴィシニョーワ凄いです。
この演目を踊るダンサーの中で彼女が一番上手なのではないでしょうか。
ゼレンスキーと組んだ時のほうがいい印象ですが、盛り上げまくりですね。
何というか、パとパのつながりがすごくスムーズで、スピードもあり、アクセントや安定感もあり、自信を持って踊っているのがビシビシ感じます。
コルプも素晴らしかったと思いますが、ヴィシニョーワの印象が何より強すぎて…。
◆『ジゼル』第2幕 (ハート・ルジマートフ、)レニングラード国立バレエ)美術、背景アリ
特別に演出された『ジゼル』のようで、ルジマートフの花を持って登場するシーンがかなり長く演じられ、既にどっぷりと役に入り込んでいるように感じられました。今回の衣装は中世風でベレー帽を被り、現代的とは全く逆のメランコリーな世界に観客を引き込んでいきます。実に静かな世界。
ハートはというと、何かその美しい世界が心地よく感じられ、どのような演技をするか観察するということが出来なくなり、ああだった、こうだったと思い出せない状況です。
次回は集中力を保っておかなくては。印象的なのは、ルジの演技で、最後夜明けと共にジゼルと別れなければならないシーン。
夢の中をボーと彷徨っているような演技から、ジゼルが消え、突如我に返り、未練と悔恨の気持ちがわいてきて、ジゼルの墓の前に倒れこみ、我を失うように激しく嗚咽が聞こえるんじゃないかと思われる程悲しむというもの。
とてもメロドラマでした。毎日きっと演技を変えると思いますので、この次見るときはどんな風になるでしょうか。楽しみです。
◆【カーテンコール】 (全員)
面白かった。『眠り』の最後のマズルカの音楽を使って組ごとに登場します。
マトビエンコはフィリピエワと出てから、一旦戻り、マハリナのエスコートをし、そのまま一緒にいました。
ジュドは普段着のカジュアルな黒上下に着替え済み。
アポテオーズの音楽に変わり、女王のようにプリセツカヤが登場。謁見するかのようにずらりと並んだダンサーに目線を送ると皆がハハァーという感じで順番にお辞儀をしてゆきます。
もう完璧、特別扱い。あの出方はチョット笑えました。毎度のことですが、すごい…。私的にはツボでした。(笑)
【おまけ】楽屋口にて、
通りかかった楽屋出口にちょうどジュドがいらっしゃってました。(着替えていたから早い?)
全員に言える事ですが、実際は顔も背丈も舞台で見るより小さいのですね。
丁寧に対応しており、優しい笑顔が印象的。続いて、モンテカルロの2人、特にかなり長い間ローラントさんはファンと話をしたり長い間対応していました。
マハリナは一通りサインに応じて、タクシーに乗った後も、ずっと後ろを振り返って手を振り続けていました。他、皆さん、結構ファンサービスしているのですね。
クズネツォフさん等自分のブロマイド?みたいなのを沢山配ってましたし。
何となく暫らく見てた私ですが、食事の予約していたので立ち去りました。
その日は遅くまで盛り上がりました。(終電間に合わなかったー)
|
| 2003年02月11日(火) ■ |
 |
| ◆『クラシックはいかが?』 東京フィル/西島千博&スターダンサーズバレエ/川久保賜紀/THE STRIPS他... |
 |
今にも雨が降り出しそうな空でしたが、楽しみにしていたコンサート『クラシックはいかが?』を鑑賞するためBunkamuraオーチャードホールに出かけました。
この企画は今年で7回目ということですが、去年のダンス音楽特集が大好評だったとのことで、今年も再びテーマ=“ダンス”で決まったみたいです。
前回も足を運び、フラメンコ、タップ、バレエ(草刈民代さんが『瀕死の白鳥』を踊った)等をフルオーケストラで味わいました。そのとき一緒に出かけた従妹がエラく喜んでおり、今年も誘って出かることにしました。
毎回、クラシック音楽に慣れ親しんでもらう事を目的にしている企画ですので、料金も驚くほど低料金。そういったことで、3Fの最後列まで満員Sold outだったそうです。
【第1部】司会:永井美奈子、 指揮:本名徹次
◆『4つのノルウェー舞曲1番』: グリーグ 「THE STRIPES(タップダンス)」
いきなり前触れも無くタップパフォーマンスが始まりました。このグループは、いわゆる、ブロードウェイタップではなく、黒人ストリート系のオリジナリティ溢れるリズムタップで、軽快で楽しい今まで私たちがイメージするタイプのものと全く違い、フリー感性で打ちつけたような強く細かいリズム、息を呑む程エネルギーに満ちていました。服装も渋谷で見かける若いお兄ちゃんという感じで、道端で見つけたら、怖くて避けてしまうかも…。(リーダーのHIDEBOHサンはFunk-Stepを考案したタップ界のカリスマだそうです)
音楽とのコラボは前から3列目だったので、タップの大きな音に消されて、オケが聞き取れませんでした。
◆『王のパヴァーヌ』: 作者不明ガリアルド、 『恋に落ちて』: ガストルディ
「コンコルダンツィア(ルネッサンス舞曲演奏・舞踊)」
激しいタップの後、タイムスリップしたように時代を遡り、400年前のイタリアルネッサンス舞曲の演奏、ダンスになりました。
正直言って、こういうゆったりとして切ない感じの音楽は、なんとも言えず好みです。特に1曲目の『王のパヴァーヌ』は、かつてその時代の吟遊詩人が小さな竪琴をもって歌い奏でるのを想像してしまいました。実際は色々な種類の古楽器アンサンブルでしたが、ついロマンティックな妄想の世界へと…
ダンサーはわざわざ復元した当時貴族のあいだで流行したスペイン風の豪華なドレスを着て、男女で踊っていらっしゃいました。
2曲目の『恋に落ちて』は軽快なステップで、歌(カウンターテナー)も入り明るい曲調です。コンサートを通して改めて古楽が好きになりました。
◆『アンネンポルカ』: J・シュトラウス 「大森智子(ソプラノ)」
ガラリとウィーンという雰囲気に変わり、有名なこのポルカは歌詞付ソプラノヴァージョンでの演奏でした。
◆『スラブ舞曲 第8番』: ドヴォルザーク
フルオーケストラの迫力ある演奏。この舞曲集は民族的“魂”感があり、10番諸々も好きです。
◆『眠れる森の美女』パノラマ: チャイコフスキー
バレエファンにお馴染みの曲。勝手に思考が反応して、王子とリラの精と共に森や湖をぬけて、オーロラ姫に会いに行ってしまいます。(再び妄想…)実に気持ちの良い曲。
◆『スペイン奇想曲』4楽章、5楽章: リムスキー・コルサコフ
「Las Chispas(フラメンコ)」
ここで今度はスペインの熱い世界へ。5人のフラメンコダンサーが登場し、衣装は裾が長く引きずる感じのものを着用してました。振り付けはステップに中でその裾を足で跳ね上げる動作を繰り返し、曲と共にだんだんと盛り上がっていきます。コルサコフの音楽も私は好きなんですよね。今回は好みの曲ばかり続きます。
【第2部】指揮:大友直人
◆『ファウスト』ワルツ: グノー 「谷桃子バレエ」
望月則彦氏、振り付けで8人の女性ダンサーが踊りました。クラシックチュチュで割とオーソドックスな印象。後で登場するスタダンのダンサーや他のパフォーマーと比べると、子供っぽい印象かな。
◆『ツィガイーヌ』: ラヴェル 「川久保賜紀(ヴァイオリン)」
彼女は去年モスクワで行われた、チャイコフスキーコンクールの部門最高位(1位なし)に輝いた人、ということで観客も期待を持って演奏を聴かれたと思います。
私は昨年コンクールの凱旋コンサート(チャイコのコンチェルト)を聴きに行きましたが、印象は変わらなかったです。というのは、音が低い。ヴィオラを聴いているみたい…。ピンと張った高音が聞こえてこない。
良いヴァイオリンを使っているのですから私が変なのかな?素人が言うのはおこがましいですが、今まで聴いた様々な演奏家達とかなり音の印象が違うもので…。
インタヴューを受けた時の彼女はとてもチャーミングで可愛らしかったです。
◆『ペレアスとメリザンド』シチリア舞曲:フォーレ
数々のシチリア舞曲の中で私が最も好きな曲。夢の中を彷徨っているような美しいメロディ。ただウットリ…
◆『死の舞踏』:サン=サーンス
《真夜中、墓場から蘇った骸骨が不気味に踊りだし、夜明けと共に墓に戻る》という設定の音楽らしいのですが、それってまさに『ジゼル』と変わりないじゃない!と美しい情景へと脳内変換しました。(笑)
◆『サムソンとデリラ』バッカナール: サン=サーンス 「西島千博・他(バレエ)」
スターダンサーズバレエ団所属の4人のダンサーで踊りました。西島さんは肌色の透けるフィットしたトップスに、ゆとりのある肌色の長いパンツ、他の3人の女性ダンサーは白いシンプルな膝丈ドレス。
饗宴を連想させる激しい曲にのって、西島さんと女性たちがかわるがわるチェンジしながら、曲の盛り上がりと共に激しさを増していきます。西島さんのきめポーズ時の顔を見ていたら、仮面○イダー系ヒーローを思い出しちゃいました。汗びっしょりの大熱演。
振付は、鈴木稔氏で、何でもこのコンサートの為に創作してギリギリ間に合ったそうです。
|
| 2003年02月02日(日) ■ |
 |
| ◆レニングラード国立バレエ『海賊』 シェスタコワ、/プハチョフ、/ルジマートフ」 |
 |
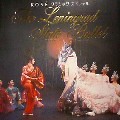 メドーラ: オクサーナ・シェスタコワ、 メドーラ: オクサーナ・シェスタコワ、
コンラッド: アルチョム・プハチョフ、
アリ: ファルフ・ルジマートフ、
ギュリナーラ: アンナ・フォーキナ、
アフメット(ランケデム): ダニール・サリンバエフ、
ビルバンド: アンドレイ・クリギン、
先週に引き続き、渋谷のBunkamuraオーチャードホールに向かいました。午後2時開演ですが、余裕が無くぎりぎりで到着。いわゆるクラシックバレエは久々になります。
この前の『竹取〜』は異質な作品でしたので…。
Bunkamura館内はとてもおしゃれな雰囲気で、いたる所に今度行われる企画公演 AMP『白鳥の湖』の美しい写真パネル展示がされていました。
館内に入ると 草刈民代さんが立っていらしたのが目に入りました。この日は観劇のようですが、別の日にこのバレエ団の『海賊』も踊る予定になっているようです。このところ毎回ゲスト参加していますね。
さて肝心の『海賊』ですが、会場は見るからにルジマートフ ファンだと思われる観客が多く見受けられ、熱気をすごく感じます。ただ、過去にガラでも頻繁に踊られる、ルジマートフ氏の当たり役 “アリ”は全幕とおして見ると、非常に出番が少なく、(特にこのグーセフ・ボヤルチコフ版はかなり少ない)ファンの方には気の毒に感じました。
まず、プロローグの遭難場面では嵐に遭う船に海賊たちが乗っていて、海に投げ出されたり、落ちそうになったりと、一連のスペクタクルな展開を大体は見せてくれるのですが、このバレエ団の版ではそれが無く、ミニチュアの船か揺れているだけ…。
ちょっとショボイと思ってしまいました。しかしダンサー達が踊りだしたら、そのフォームやかもし出す雰囲気の美しいこと! ワガノワメソッドは私の好み!
海賊コンラッド役の プハチョフは、背が高く体格も申し分がなくて、大変舞台栄えしていました。バレエ団期待の若手とのことで、今後さらに活躍されるでしょう。
ギリシャ娘、メドーラ役の シェスタコワは、ガラなどでよく拝見していましたが、親しみやすさが滲み出て、誰からも好感が持たれるタイプのダンサーだと思います。踊りもキレがあり、テクニックにしても全く危なげありません。この日はとても輝いていました。
奴隷商人アフメット役(通常、ランケデム)の サリンバエフはかなりのテクニシャンで、1幕の奴隷市場でのギュリナーラとのパドドゥでは拍手喝采を浴びていました。
ただ背があまり高くないのでロシアだと役が固定されてしまうかもと、変な心配をしてしまいます。活躍してほしいですね。
ギュリナーラ役は特に印象に残らず…。
セイード・パシャ役(A・マラーホフ)はこの版ではトルコ総督ということになっていて、他の版で多く見られるコミカルな役周りではなく威厳を保っていました。(男前に見えた!)
さてアリ役のルジマートフ ですが、1幕ではほとんど現われず、出てきたとしても脇に立っているだけ。終始、役柄の為、控えめにしていました。
そして2幕の有名な洞窟でのパ・ド・トロワ 。
ここでアメリカ系のバレエ団だったら、出番だ、目立っとけ、とばかりにテクニック見せ見せで頑張ってしまいがち(決めつけすぎ?でも否定ではないですよ。盛り上がるし…)ですが、ルジマートフの場合は終始、コンラッドの手下という立場をわきまえ、気張りすぎることも無く、抑制された役どころを体現していました。
ただ、昔に比べると、アクが無くなったというか、 悟りを啓いちゃった人というか、わさわさした演目の中で、別世界にいらっしゃっていたような…。見ていると何かちょっと痛い気持ちになるんですよね。痩せた身体にしろ、踊りにしろ…。 骨身削って舞台に出ているような気がして。
この版の『海賊』に話を戻しますと、ほぼ有名なキーロフバレエ版と大差はありません。
ただ3幕がちょっと違っていて、セイード・パシャの宮殿ではなく、パシャの大きな船の上で「生ける花園」の場面が行われます。
ボリショイやABTみたいに極彩色ではなく薄いピンクと薄い紫の柔らかな色彩でとてもきれいでした。
人数はあまり多くありませんでしたが…。
最後も海賊達の戦いの群舞があり、その船を奪い元気良く出航―で終わります。
ABTみたいに死者続出ではありません。(あれはやりすぎ!)よかったーと胸をなでおろしました。
最後に シェスタコワは本当に良かったです。どんどん良くなる感じ。
マールイ劇場バレエ団(レニングラード国立バレエ)の皆様、毎回長期のツアーを全国津々浦々までご苦労様です。
ルジマートフのファンの皆さんは、 最後のカーテンコールの彼のチャーミングな笑顔に救われますよね。
いい気分で劇場を後にされたと思います。
|
|