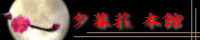年賀状に携帯の番号を書いてばらまいたせいか、
年賀状を何らかの理由で書かなかった人やら、その他、ご機嫌伺いやらで、
ここのところ、あたくしの携帯は、珍しい人からの電話がよくかかってくる。
今日は、いつもはメールとかで話している某嬢と、
養成所時代にとても仲良しだったジロウ(仮名)くんからかかってきて、
どちらもえらい長話をしてしまった。
養成所時代の友人で、唯一、密に連絡を取り合っているといえば、
この日記にも何度か登場しているユリ姐か、
まぁそれよりは頻度が少なくなるけれど、ちゃんと連絡をよこしてくれているのは、
やっぱりこの日記でも何度か登場したトキオくらいである。
ジロウ君とは、現役当時、それこそ一番長い時間を二人で過ごしてきたといっても
過言でないくらいの仲だったのに、
あたくしがあの事務所を去ってからというものの、彼の情報は
もっぱらトキオ経由で、ちゃんと本人と話すのは、実に3年ぶりくらいである。
元気そうだった。
彼は、あたくしより2つ年上だったので、もう三十路に突入しているのだけど、
声は前より若々しくなった気がする。
昔は、よく二人で「7割は沈黙を占めるような会話」をよくしたっけ。
喋らなくても、お互いの空気で、お互いのことがわかるという、
不思議な関係だったのだ。
交際は・・・・していなかった。
丁度この頃から、あたくしの体調がどんどん悪くなっていったのもあるけれど、
彼と一緒にいると、発作が起きるくらいに悪い状態の時も、
うつの時も、更にその症状がハイパーな状態になると本能的にわかってしまったので
付き合うまでには至らなかった。
つきあっているんじゃないか?と勘違いしている輩は、当時は沢山いたみたいだ。
そのくらい、あたくしたちは二人で一緒にいる時間が長かったし、
とりあえず、波長という波長がそっくりだったのだ。
一緒にいるんだから、勿論、彼のことは好きだったけれども、
恋とか愛とか、そういう括りではなかったみたい。
その証拠に、あたくしは自分より年上の彼をよく説教したし、
その説教の影響で更に沈み込もうとするジロウ君を引っ張りあげるのも、
あたくしの役割だった。
ジロウ君もあたくしのその価値観と同じようにあたくしを見ていた。
寡黙な彼だったが、レッスンの休み時間なんかにこっそりとあたくしの傍に寄ってきて、
「この中に、俺たちが付き合っているって勘違いしてるヤツ、
何人くらいいるんだろうね・・・・。」
なんていう冗談も言えるくらいではあった。
しかし基本的には寡黙で、
だけど、それは彼が意識的にコントロールしていることなんだということも
後々になって話してくれたけれども・・・・。
今、一緒にいるぷよ2は、彼に比べると喧しいほどよく喋る。
理詰めが得意なあたくしさえも疲れて、相槌のみになってしまうくらいに
よく喋る。
そんな生活が2年以上続いて、
あたくしはそれが当たり前のことのように思っていたのだけど、
実はそうではないというのに、今日のジロウ君の電話で気づかされた。
「ねぇねぇ、どうして黙っちゃうの??」
「・・・・・・・。」
「ねぇってば、聞いてる?? もしもし??」
「・・・・・・・。」
「もうっ!! お願いだから黙らないでよ。」
「・・・・うん。聞こえてるから大丈夫だよ。」
「黙らないでよね。電話でそれをやられると、
何考えてるかわかんないじゃない。」
「あぁ、そうだね。」
という、彼のやさしい一言を聴いて気がついた。
あたくしたちは元々、「7割以上を無言で過ごす会話」という方法で
コミュニケーションをとってきたことを、あたくしはこの2年ちょっとで
すっかり忘れてしまっていたのだ。
それを告げると、やっぱり彼もそれを忘れていたようで、可笑しそうに笑っていた。
「そうだったね。そういえば。
ダンスのレッスンとか終わった後とかも、
何でもないのにず〜っと2人で、黙って駅とかにいたなぁ。」
「うん。授業の後とか、一緒にご飯食べに行っても、黙ってることが多かったよね。
思い出した、思い出した(笑)」
「でも、俺だって誰に対してもそういうふうっていうわけじゃないんだよ。」
「わかってるよ、そんなの。あたしだってそうだもん。」
「あれが『俺たちのリズム』だったんだね。」
「そうか・・・・そうだったんだね。」
「トキオが言ってた。今の夕雅さんの彼氏と俺は正反対だって。」
「正反対・・・・かぁ。まぁ、向いてるベクトルは違うかもね、明らかに。」
「正反対ってどういう意味だろ。」
「わかった! 喋る量よ!!」
(2人で爆笑)
「今の彼は、よく喋るからね。
理詰めが得意なこのあたしを、喋り落とそうとするからね(笑)」
「へぇ〜。そんなに喋る人なんだ。」
「特別喋るってわけじゃないと思ってたけど、
ジロウ君と比べると、真逆よ。トキオの言うこともよくわかる。」
「なるほどねぇ。」
ジロウ君は、とにかく思ったことを口に出すというよりは、
じっくり考え込んでしまうタイプだった。
あたくしは、決してそんな彼を焦れて責めたりはしなくて、
当時はそれが当たり前だと思っていた。
彼も、あたくしが答えを我慢強く待っていることを知っていたので、
なるべく慎重に言葉を選んでいるようだった。
これが、つきあっている彼氏・彼女なんていう間柄だとすると
ちょっとややこしい顛末にも陥りがちだけど、『トモダチ』という便利な関係上、
あたくしも必要以上に彼に詰め寄ることもしないで済んだし、
彼も、あたくしに対して警戒心を強くすることなく過ごしてこられた。
ジロウ君はこの後、また沈黙に陥ったりしたけれど、
お互いにそれが『2人のリズム』だというのをもう思い出していたので、
あたくしも電話のこちら側で黙ったまま、彼が次に何を言い出すのかを楽しみに待っていた。
「あのね・・・・。
夕雅さんのことは特別なんだよ。
『好き』とかっていうのはまた別問題で・・・・なんていうのかな。
ミズエと夕雅さんは、すごく特別ですごく大切な人なんだ。今でも。」
「ミズエとはつきあってたんでしょ? トキオから聞いた。
連絡、とってる?」
「いや・・・・別れてから半年か1年くらいして、
1回だけ芝居のオファーの電話があったっきり、そのままで。
実家に電話すれば何とか消息もつかめるのかもしれないけど・・・・」
「君はかけないほうがいいと思うよ。」
「うん。だから、かけてない。」
それからジロウ君はまた黙ってしまった。
あたくしよりももっと重い病を背負い込んでいるミズエのことを
結局どうすることもできなくて、彼は彼女と離れてしまうことになってしまったのだけど、
きっとあたくしが彼とつきあっていても、同じような結果になっていたと思う。
ただ、ほんの少しだけ、東京に残留する時間が長くなっただろうという
展開だけは予測できるけれど、多分、一緒にいられた時間は、
明らかに短くなっていただろう。
彼は、ミズエのこともあたくしのことも同じように心配している。
1人の『トモダチ』として。
それがバカバカしい詭弁だという人がいれば、それはそれでいいと思う。
あたくしは、彼の呈する「愛の形」から身を守るために、逃げたのだから、
彼もミズエも責められた立場ではない。
彼は、その後に何か言おうとして、ぐっと言葉を呑み込んだ様子だったが
あたくしはその空気を見逃さなかった。
「・・・・わかったよ。
あたしがミズエの実家に電話してみる。
捕まるかどうかは確約できないよ。それでいい?」
「・・・・ありがとう。」
果たされるかどうかもわからない約束をして、あたくしたちは電話を切った。
彼と話をしていると、また芝居心が疼きだしてきて、
これ以上、話を続けていると、どうしようもなくなって
とるものもとりあえず、東京に舞い戻っていってしまいそうになってしまう。
実は、それはそれで良かろうとも思っていたのだ。
やりたいモチーフは沢山揃っているし、役者やスタッフを揃えるのも
東京の方がやりやすい。
舞台復帰への足がかりは、東京にいた方がうんと高いチャンスに恵まれる。
本は自分で書いて、後はジロウ君とトキオあたりを巻き込めば、
5ステくらいの企画くらいすぐにできるところにいるのだから、
1ヶ月、夜露をしのぐ場所さえあれば、何とでもなるとも思っていた。
ただ、先立つものがないだけで。・・・・嗚呼、金の力は恐ろしい。
疼く心。
そして、ジロウ君の言っていた『俺たちのリズム』・・・・。
あたくしがミズエの実家に電話するまで、
次に彼に電話をかけることもないだろうことも同時に悟ってしまった。
もっとも、彼はあたくしのことを「好きだ」と宣言したことはあり、
あたくしも、頷いてそれを受け止めたのだけど、
「無言の会話」で空気を悟る間柄というのは、それはそれで厄介なもので、
「一筋縄ではいかない」というのをここまで精密に表現しているあたくしたちの均衡は
けだし、素晴らしいとも言えるのだけど・・・・(苦笑)。