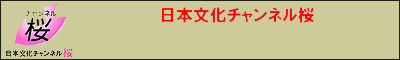目次|過去|未来
| 2002年09月12日(木) | たん譚観劇! |
長い間?前売り、売り切れで狂言を観劇することが出来ないでいた。ようやく切符が取れ、今日実に久しぶりに行くことが出来た。某大学の先生で茂山忠三郎の弟子?でもある、米国人の知人Jなどは、いつ行っても見に来ている。
別に、もぎりをして手伝っているわけでもないのに、いい席に座っている。かたやチケットも手に入らない日本人がいる。
本日の曲の一つは一休さんの話しでも有名なもので、主(あるじ)に、これから留守をするので、これの見張りをしておけ、大変な毒物(附子)で、空気感染さえもありうると脅かされたそれが、実は水飴で当時貴重品、しかし太郎冠者と次郎冠者はウソだと見抜き、さんざ賞味した後、主の軸、焼き物をこわし、責任をとって、それを食べて自害しようとしたと、主にいいわけする話。
狂言の題は「附子(ぶす)」という。附子はトリカブトの根を精製して作る毒物で、前説では、当時局部麻酔として使っており、顔などに塗ると、その部分がよじれて見にくい様相を呈するところから、現代の不美人を言うようになったといっていたが、樋口清之さんが書いているところによれば、その毒物を飲んで、あえぎ苦しむ顔の形相が真に醜い、そこからきているとも、読んだことがある。
古典とは同じものを繰り返し見ても飽きないものをいう、筋はすでにわかっている、みんな知っている、それをともに見て、また笑う。これが文化である。わずか二百年ちょっとしか歴史のないアメリカでも、映画ですでにそれがはじまっている。タイタニック他などはそれである。
話を狂言に戻す。
今回はっとしたことがあった。茂山千作の「鵜飼」という小舞が終わり、次の出し物「月見座頭(つきみざとう)」を見て感じたことである。この曲は、今は絶えた鷺流(さぎりゅう。他に和泉流・大蔵流がある)
で演じられていたようだ。題名からして今の人権派の人々から糾弾されそうな題名(なぜというに、めくらにも位があり、上から検校-けんぎょう-別当-べっとう-勾当-こうとう-座頭-ざとう-)である。琴の宮城検校、勝新演ずるところの座頭市の名にも見えるように。
今回これを見ていて、もし鷺流がこのような曲目ばかり演じていたとしたら、絶えてしまったのもしようがないかなと思ったのだった。決して専門家でもない淡譚の感ずるままのことだけれど、この曲には笑いがほとんどと言ってない。
話は、目あきが月や自然を吟じたり唄ったりする、座頭はそんなことはついに出来ない、せめて鴨川のほとりに出て、虫の音でも鑑賞しようと河原で聞き入る、そこに目あきが来て、目くらが風流をすると感じいって、最初は互いに句などを披露するも、当時著名な俳人(この狂言、月見座頭は江戸時代の後期の作と言われている)のまぜこぜだったりする、ここが唯一笑える場所だが、後は、その河原の席で酒を酌み交わし和やかに歓談の後別れるも、目あきが座頭に意地悪することを思いつく。わざとぶつかって難癖つける、ところが座頭はわざとだと言うことを「目あきが、めくらにぶつかろうことがあるわけない」と喝破する。
そしてかわらでくっさめを一度して、しずしずと帰っていく。
これは、目あきが、まったく相手にわからないという前提でする、悪魔のささやき的な行為だ。言い換えてみれば透明人間になって何でも出来るという事とおなじである。その時人はどういった行為にでるのか?そういう事を見ている側に突きつけてくる。が、しかしこれはもう狂言ではないと思うのだ。狂言では、人の刃傷沙汰はなく、人の死ぬ場面はない。皆無である。狂言は本来、弱い者が、強いものを笑うものである。
この曲に関して、多くの観客の拍手のとまどいがあったように思えた。例えば吉本新喜劇の中で、葬式の設定で悲しみのまま、終わってしまうような光景を思えばいいだろう。
見ている観客はとまどう、何か落ちはないのか?というわけである。それがくしゃみを一つしてめくらは目あきにしてやられて去っていくのである。
猿楽から能狂言が分かれ、洗練された笑いが狂言として残った。この曲はどちらかというと世阿弥を感じるのだ。能楽に見られる暗さ(悪いという意味ではなしに哲学的)を。
そう言う意味でこんな作風ばかりを鷺流が演じてきたとしたら、鷺流が絶えたのも無理がないと今回素人目に思ったのだった。