| 2008年03月11日(火) |
080311_ユリウス・カエサル著「ガリア戦記」を読む |
世の中には別に読まなくっても良い本が沢山あります。
いわゆる古典の中にも、読んでも特にもならない本があるものです。約2060年前に書かれたこの本もそういう部類かも知れません。
ユリウス・カエサル著「ガリア戦記」もそんな一冊。しかし、歴史上の英雄の姿を自らの手で描いたという点で無類の書物であり、かつ文筆家としての名を普及のものとしたこの本には、読んで特をしたとかどうとか言うことを超越したなにかがあります。
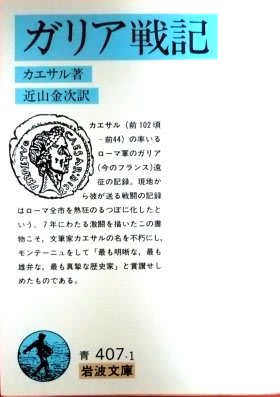
「ガリア戦記」のガリアとは今のフランスあたりのこと。そしてこの書物は西暦紀元前58年から紀元前51年にかけて行われたローマ軍のガリア遠征記です。
このころは今のライン川あたりを自然の境界としてそこまでの範囲でローマの覇権を及ぼしてそこに住む住民たちの安定を与えることがローマにとっての安定と繁栄に必要なことでした。そしてその安定を与えることが国家のリーダーに求められ、それを華麗に果たしたのがユリウス・カエサル(シーザー)でした。
書物は最前線の戦時報告書でもあり、それが本国のおくられたときにはローマ全市を熱狂のるつぼと化した、とまで言われます。それほどにカエサルはローマ帝国の英雄であったわけです。
物語の主語は「カエサルは…」で始まります。著者はカエサル自身でありながら「私は…」ではなく「カエサルは…」で始めることで、あくまでも客観的な戦時報告書であるということを強調したかったのでしょうか。
そして捕虜などから得た敵の様子を第三者的な目で描き、それにカエサルとその軍団がどのように対処したかを淡々と語ります。
時に判断を誤った部下の軍団を失ったり、奇襲をかけられて危機一髪に陥ることもしばしばです。しかしそのたびにカエサルは戦場を走り回り、手紙を送り、戦士たちを叱咤激励します。
「カエサルが見ているぞ」というだけで重傷を負った戦士たちが休息もそこそこにまた戦地に姿を現すというカリスマ性を余すところ無く描いています。
※ ※ ※ ※
敵の波状攻撃のために、次第に味方の中に不安が増し恐怖が具談を襲い始めたとき、カエサルは百夫長(百人の戦士のリーダー)、千夫長(千人のリーダー)たちを集めて演説を行います。
「…皆が何の目的でどこに連れて行かれるかを問題にするとは何事か…自分たちの恐怖を穀物の供給や道の狭さの性にするのは、指揮官の務めを見限って命令するようなもので、生意気な振る舞いだ!そんなことはカエサルの心配することだ!」
絶対的に指揮官に従え、そしてカエサルはこの軍団に特別な期待と信頼を寄せている、と語りかけます。
この言葉によって戦士たちの気持ちはそれまでと驚くほど変わって、「戦争の指揮は自分たちの判断ではなくて指揮官の判断に任さなければならない」と戦士たちが釈明をするほどになります。
カエサルの人身掌握術の極みです。
※ ※ ※ ※
また、敵が勝手に有利だと思いこんで戦いをしかけようとする様子をカエサルはこう言います。
「およそ人は自分ののぞみを勝手に信じてしまう」と。
戦いの中に身を置いた者が語れる深い生き様がここにはあります。
| 
