吉野家がいま、大変なことになっている。
ご存知のとおりその原因はBSE、いわゆる狂牛病だ。昨年末、米国産牛肉に初めてのBSE感染が認められ、日本は実質的な禁輸措置に踏み切った。このため、メイン商品「牛丼」の材料となる牛肉の大部分を米国産に頼る吉野家は、営業の見直しを迫られることになったのだ。
僕はこの問題に心を痛めている一人だ。なぜなら、僕と吉野家は「ただならぬ関係」なのである。
思えば大学一年生のとき。あれはアメフトの練習帰りであった。「生卵をかけて食うとうまいよ」。一緒に行った友人に、そう薦められた僕は、見よう見まねで卵を溶き、肉の上から回すようにして流し込んだ。その友人は、その後テレ朝に行った吉川君だ。92年の夏のことを、僕は今でもよく覚えている。
僕はゆっくりと箸を口へ運んだ。混ざりきらなかった卵の白身が糸を引くようについてくる。口に含む。噛む。
「むむむ!?」
衝撃が走った。甘い。そして濃い。タレに加え、溶き卵によって通常の状態よりもやや水気を多く含んだ牛肉は、ジューシーこの上なし。続く玉ねぎの歯ごたえ。まるで計算されたかのような煮込み具合だ。卵黄はそれらをやわらかくコートし、カスタードクリームのようなまろやかさと、独特の濃い味わいを加えている。
「むむむむむ」
お持ち帰りで食べたときのボソボソと味気ないという印象はその瞬間に消し去られた。それは鮮烈なデビューであった。
以来、僕は好んで吉野家の牛丼を食べ続けてきた。もちろん「松屋」も試したし、「なか卯」へも行った。でも「違う」んだよなあ。僕の味覚をつかさどる脳細胞には、あのとき吉野家の味が刻み込まれてしまったようだ。
「ただならぬ関係」はこれだけではない。
僕はかつて広告会社の営業マンをしていたのだが、実は新入社員のときに担当した最初のクライアントが、他でもない吉野家ディー・アンド・シーだったのだ。新人の僕は、連日吉野家の宣伝担当部署に通ったものだ。牛丼CMの撮影現場では、やっぱり牛丼が振る舞われたっけ。思えば、最初に僕を「ちゃん付け」で呼んでくれたお得意さんが吉野家さんだった。
その後、異動で担当クライアントが変更になっても、牛丼を食べる僕の食生活は変わらなかった。ひどいときは週に五回。ウシウシ・サカナ・ウシ・カレー・ウシウシのような状態であった。このままいくと角が生えてくるんじゃないかと、本気で心配したものだ。
店での滞留時間はいつも極めて短い。入店して食べて出るまで、約五分。毎日不思議と忙しい若手社員の生活のなかでは、実に「助かる」食事なのである。食べ終わった後、毎回確実に満足感が得られるという事実もまた、僕の足をして再びオレンジ色の看板に向かわしめたのであった。
吉野家といえば、「カスタマイズ注文」が必ず話題にのぼる。ツユダクは、「いろはのい」といっていいだろう。しかし僕にいわせれば、ツユダクはまだまだシロウト。それを聞くと「フフフ」などとほくそ笑んでしまう。誰しもそうして大人になっていくのだ。ネギダクと聞けば「おっ」ということになる。どれどれとばかりに、注文者の面構えをそれとなくチェックしてみたりする。ツユヌキやネギヌキクラスになると「むむー」と唸ってしまう。かなりハイレベルである。ただ、僕はそれらを経て再び「カスタマイズなし」の境地に辿り着いた。いわば悟りである。
こうなると吉野家に対して「身内意識」のようなものが生まれてくる。女子高生のグループや若いカップルが来店しているのを目にすれば客層の拡大に喜び、サッカー日本代表の小野伸二が年末に帰国したとき、まっさきに吉野家にいったと聞けば、「うんうん、そうだろう、そうだろう」と我がことのように目を細めてしまうのである。
その吉野家が、いま危機を迎えている。これはなんとも心配である。駅前の吉野家で今年の「うし初め」をしながら、この問題の一日も早い収束を願わずにはいられない丑(うし)年生まれの僕なのであった。
2004年01月08日(木)
| 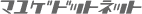 diary/column “mayuge の視点”
diary/column “mayuge の視点”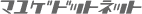 diary/column “mayuge の視点”
diary/column “mayuge の視点”