DiaryINDEX|past|will
| 2010年05月29日(土) | ラストのぐんまの山とともに泣く10ねんまえのきよちゃん、におどろくタガララジオ8 |
ラストのぐんまの山とともに泣く10ねんまえのきよちゃん、におどろく、この画像は現代アート最前線だろ、
22日のカフェズミで座間裕子さんとマイケル・ピサロを聴いた感想を書いたタガララジオ8です。>■
ここで書いたテキストを座間さんが英訳してくれました。おいらの文章は日本語ではのらりくらりしてるけど、英訳してみると音楽の本質に触れている、と、うれしいなー。韓国語や中国語に翻訳してくれるひとはいないかな。あれれ、サウンドのドラッグでしょ、は、そのまま英語でオッケーなの?ネイティヴチェックもするそうだから安心か。また、あの音楽は世界観の意識の美しさだ、と、文末に翻訳加筆しました。
‘July Mountain’ for field recording & percussion / Michael Pisaro, Greg Stuart (engraved glass p05) 2010
- Review by Masanori Tada
A limited release of 50 copies from a British contemporary classical music label. With a beautiful cover, I was told that this is a composition of percussion sounds and 20 field recordings, but the actual listening experience is something beyond the description.
I love to listen to the murmurs of the wind in the trees, the sound of rain, various sounds that occur when I ride a bicycle with my kids, while paying attentions to the perspective and the movement of each sound. This might be something similar to field recordings, but the difference between those sounds I hear and that music must lie in the composer's presence as an intermediary - who incorporates his clear aesthetics, thoughts and ideas into the materials of the recordings - prayerfully.
I saw Yuko Zama of the Erstwhile label again after ten years. When I heard her voice, I felt like I was time-tripped to ten years ago when I had a music talk with her for Out There magazine. I explained to her that my taste for music has changed after hearing Michel Doneda playing outdoor - towards the music that evokes in me environmental sounds like temple bells or the sounds of nature like murmurs of the wind in the trees - which are not really the sounds of nature but contain the similar feels and waves. I seldom listen to current improvised music these days. When I told her so, she said that a similar mindset is found in some of composer Michael Pisaro’s work. Then she played some music of Michael Pisaro at the Sound Cafe Dzumi in Kichijoji, so I had a chance to listen to his music for the first time.
This was like a sound drug - the customers who were there at the cafe including a young lady who loves noise music, a contemporary jazz fan, an artist, a recording engineer - all of them looked like they were straying away from their normal listening path to enter a new world. The cafe owner was so excited that he brought a LP of the Italian ambient music by Giancarlo Toniutti and said that he had a similar experience of discovering something completely new to him when he encountered this LP.
I cannot tell the exact differences of field recordings, noise music and ambient music in general, but I can tell that this "July Mountain" is definitely the most powerful music you can experience. You can read the more detailed story about Michael Pisaro in Yuko Zama's blog (http://d.hatena.ne.jp/yukoz/20100401/p1).
It just feels great to listen to this CD. With the music, I can also hear the sounds of Cessna planes flying over the panoramic view of this residential neighborhood in the suburbs of Tokyo, the chirps of birds, and even the sound of the sun. If Michael Pisaro ever has a chance to visit Kyoto, I can imagine that he would make fantastic recordings of everything there - from the calm chatter of the Kamo River while sitting on the embankment, the sounds of the temple bells, the sounds of Gozan-no-Okuribi, to the sounds of a small restaurant in Kyoto.
Listening to this music carefully with my headphones is also a great experience. Don't take this the wrong way, but it sounds really musical. The inserted piano sounds have even a little feeling of pop music. There are many works of ambient music in the world - that might be freer from the intermediary of musicians. But this incredible sense of exaltation in the music of ‘July Mountain’ - that is almost enchanting - must derive from the unmatched artistic creativity of the composer Michael Pisaro, who has a splendid awareness in seeing the beauty of the world.
- Review from Radio Tagara on Jazz Tokyo by Masanori Tada (born in 1961: music writer/co-organizer of Japanese music website "musicircus")
Japanese page: http://www.jazztokyo.com/column/tagara/tagara-08.html
| 2010年05月28日(金) | 小林よしのり『昭和天皇論』を読む |
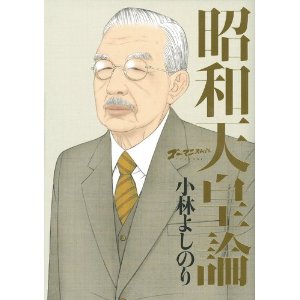
小林よしのり『昭和天皇論』を読む。
すごかったな昭和天皇。
学生時代に「天皇についてどう思う?」と問われて、
在るものは理由があって在るものだと思うし、
おれはあっていいと思う、としか答えられないでいた。
いまだにそれ以上のことはない。
身体が作動させる死へのプログラムという考え、と、昭和天皇のことを連想したことがありました。■
こう、日々、のろのろとごろごろとして休んでいますると、
老いのプログラムが作動しているのを感じるぜ。
スナガさん電話して
清水俊彦がSJで発表していた年間ベストをおしえてもらう。
1980年のベスト15のうち過半数の8枚がECM盤だった。
それの確認だったけれど、やはりECMよもやま話で盛り上がり。
そんなことをしている場合ではないのだが。
| 2010年05月27日(木) | 写真集『南無観 東大寺お水取りの光陰』(写真:今駒清則) |

アマゾンで購入ボタンを押してしまった。
奈良新聞社から07年に出版された写真集『南無観 東大寺お水取りの光陰』(写真:今駒清則)■、
サイトからスライドショーが見ることができる、が、見事な写真ベスト5は外してあるな!、それにA4サイズの大きさ、印刷の鮮やかさ。
アマゾン在庫1冊をゲットした。
3月にコンポストのレビューで即買いした越境ジャズ盤在庫1枚以来の快挙だ。快挙か?
ユリシーズ3号■、
おおお、福島恵一さんが巻頭「マイ・オピニオン」で「耳の枠はずし」について書かれている。
福島さんは、エアチェックやプログレ、フールズメイト、フリー/インプロヴ、ECMが共通語になっている世代の最強論者である。
来週6月6日にECMカフェ■なるバトルが予定されている。わたしの根拠の薄い妄想発言が福島さんを苦しめることだろう。ウルトラマン、ゾフィー対ゼットンをめざすぞ。
デイズ・ジャパン■の5月号・6月号、
世界中で開発による飢餓、戦争、子どもの死があることを伝えている写真月刊誌、
・・・音楽を聴く気が失せる。・・・寝る!
| 2010年05月24日(月) | 13ねんぶりの小沢健二のライブについてのブログ3つ |
13ねんぶりの小沢健二のライブについてのブログ
>山崎洋一郎さん■
>ロッキンオン編集部日記■
>セットリスト入り■
おれは単純に、チケットの抽選に当たらなかったので行けなかった。
友だちが「彼の歌詞を引用してうまいこと書く」のではなく、自分の言葉で書かないと意味がない、と、ライブの感想を書いていた。
ライブに行けたみなさんに感謝を。
手がかりから想像したり、信用したり、受信したり、察知したりする。
言葉のひとである小沢健二への信頼で、なんというのかな、こうやって、いろいろ考えて過ごしたり、本を読んでみたり。
| 2010年05月23日(日) | 札幌在住のかたはシニッカ・ランゲラン公演を見逃してはならない |
札幌在住のかたはこのコンサート必見ですよー!
シニッカ・ランゲラン札幌公演>■
シニッカ・ランゲラン、ECMの作品>■
ミュージサーカスの記事は以下。
ECM NEWS/ECM情報
July 23, 2007
シニッカ・ランゲランのアルバムへの示唆に富む批評 ■
ECMに新しい才能が登場していたのを見逃していた。ノルウェーのカンテレ奏者シニッカ・ランゲラン。カンテレという楽器はハープを横にしたような楽器で、弦をチューニングするレバーが付いている。フィンランドの民族楽器で、ランゲランはフィンランドに近いルーツがあるかもしれない。ノルウェーは地続きだし。
5月23日(日)、東京駅八重洲口徒歩3分の Salon'd TOSHIN という会場で、日本カンテレ友の会主催により、ランゲランのソロ・コンサートが開かれた。30名ほどの小さな会場で、親密な雰囲気の中、朗々とした北欧トラッドの歌声に圧倒され、カンテレのチューニングをずらすことで演出される微分音もしくはメセニーのピカソ・ギターを思わせるつまびきに瞠目させられた。伝統的なフォークの味わいに斬り込むカンテレの現代的表現。それでいて、その静かな音の織り成す必然性にはアヴァンギャルド感は皆無である。
も、もしかしたら、こういう浪曲ががなるような不協和音の自然な配置は、フォークの根源に触れているのか?カンテレとは、こげにエッジのある楽器なのか、と、おののいていたが、ECMコンプリートを備える月光茶房の原田正夫さんとECMミュージシャンに信望の厚いオフィス大沢さんからお話をうかがうに、カンテレという楽器は現代音楽やエレクトリックな表現の分野はそもそもあるのだそうだ。なるほど、すると、おそらく正統的な演奏法によるカンテレ演奏に親しんでおられる日本カンテレ友の会の皆さんは驚いてしまう演奏だったのかもしれない。
| 2010年05月22日(土) | 「虹色の戦争」 |
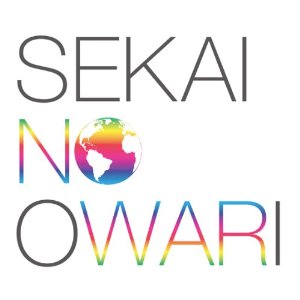
あおいろの空に神さまが来て願いをひとつ叶えるなら、ぼくらのいのちは消えてしまうのだろう。
世界の終わり(バンド名)の「虹色の戦争」が爆音でかかり続ける5月22日の真夜中に。座間裕子さんがカフェズミでかけて来場者みんなをとりこにした(耳の人生の軌跡を少しだけずらした、と言い換えてもいい)フィールドレコーディングを構成したりする現代音楽系の作曲家マイケル・ピサロにしても、福島恵一さんがブログで眼差すディストピア・アンビエントなる音のありようにしても、世界の終わりが歌う世界観にしても、ぼくの中ではひとつの地平に重なって見えている。前方120度で聴いていた耳が、360度全方位に、地平線の向こうまで耳の手が伸びて聴きはじめるような、もう昨日の耳には戻れない、でもそれを伝える言葉の手立てが見つからない、見つからなくていいのだ、そこにはひとはいないし、ひとはいらないところ音、誰が聴くために?、さあ、ぼくはきのうのぼくをおいてけぼりにしてゆこう。
| 2010年05月20日(木) | 日本共産党中野区議候補金子洋(かねこひろみ)に清き一票を |
あさ8時すぎに山手通りを目黒から北上していたら、日本共産党の街宣カーが走っていて、
おれの小学校時代の朋友・金子洋(かねこひろみ)■と同じ名前が中野区議候補でクレジットされていたのだ。
彼は学生時代に民青に入っていたから、ありえないことではない。
おれのくるまは5台くらい後ろを走っていたが、街宣カーが左折してゆくときに、候補者が振っている手だけが見えた。
函館市立港小学校の音楽クラブでおれが大太鼓で彼が小太鼓だった。あとはみんなかわいい女の子たちだった。シュトルム・ウント・ドランクな小学校時代だった。■
候補者の手の振りは、あの時の小太鼓の叩きと一致した。
おれの小学校時代は悪ガキで、ファンタやビールのビンを酒屋から盗んでは換金して仮面ライダーカードをコンプリートしたり、おれの好きな女の子と仲良くしている成績がよくてまじめな彼をいじめたり、彼の自宅にペンキやチョークを塗ったくったりした、らしい。彼はつねにまじめな対話で根気強く悪ガキのおれとつきあってくれて、親友になった。一緒にベートーベンの運命の第4楽章を口ずさみながら歩いた。
中学になると校則のウラをかいて一緒にゲタ履きで登校したのが痛快だった。彼はつねに学年トップの成績を維持した。おれは全科目で勝てなかった。彼は学年トップなのに、休み時間には落ちこぼれのクラスメイトたちに勉強を教えていた。ほんとに絵に描いたようにいいやつだった。トーマの心臓の優等生みたいであった。
おれは何かで彼に勝ちたくて、合唱コンクールの指揮者になって最優秀賞を獲ったところで、おれは転校してしまった。おれは片思いのますみちゃん超美人と離れるのが辛かったことしか憶えていないが、彼はおれに中学生なりの熱い別れの言葉をくれていたような気がする。ますみちゃんとおれは5年後に奇跡の両想いになるのだが。
早稲田に進学した彼と東京で再会する。ジョイ・ディヴィジョン、キャバレー・ヴォルテール、モノクローム・セット、ギャング・オブ・フォー、スージー・アンド・ザ・バンシーズ、プリテンダーズ、ローリング・ストーンズ、デヴィッド・ボウイ、一緒に聴いたなあ。山歩きにも3・4回行った。デモにも行った。金大中を救わないといけない時代だった。
おれは早くに結婚して子供ができて、すっかり付き合いの悪い大人になって、いろいろ踏み外しているうちに互いに消息不明になっていた。
彼の人物はこのおれが保証する。おれは練馬区なんで無理だが、中野区にお住まいのみなさん、彼に清き一票を。
でもなあ、おれと日本共産党の考えは基本的な状況認識は一致しているんだろうが、どこか違うところがあっての。
おれは消費税をまじにちゃんと上げて財政再建して、セーフティネット拡充して、子育てはワーキングプア階級でも可能にして、法人税下げて企業を凶暴化させて、才能の海外流出を防いで、沖縄の米軍基地は成田空港を使用したらいい、と、こう思っておるんじゃが。プチ右翼かなあ。サピオ読んでるし。マクドナルド不買だし。コーラ中毒になってるし。
| 2010年05月17日(月) | スイング・ジャーナル休刊のニュース |
うわさのスイング・ジャーナル休刊のニュース■。
金曜の夜勤に体格のいいガイキチを追い出すのに中途半端に抵抗するもので警官臨場までのあいだにみぎあしのスジをいためる。原因は運動不足なのだ。思った速度で身体を動かせていない。コーラをまた飲んでこれまた中毒に歯止めがかからず。
おまけに風邪もひいてついでにアレルギー性鼻炎で土曜日は終日臥せていた。
日曜日は6月6日(日)に予定している福島恵一さんの「ECMカフェ」の選曲をしてみたり。
井上頼豊の『チェロ・コンサート』、コニッツのヴィレッジヴァンガード、モチアントリオECM、クリススピードの最近のCD、
ブノワ・デルベックとアルヴェ・ヘンリクセンのCDなんてのもどきどきして聴いている。
駅前のライフにお水取りに行くBGMは「世界の終わり」。
タガララジオ7がアップされてます■
このジャケを並べる感覚がくせになるなあ。
メインステージのディスクレビューには復帰できそうにありません。
小沢健二がスチャダラパーの公演に特別出演している!とか、■
あー。おれ、小沢健二のチケット、すべてハズレてたんだよなー。行きたいが・・・。なむさん。
ミュージックマガジンが小沢健二の特集(本人への取材なし)していて、たしかに「信者」という言い方はそのとおりかもしれないんだが。
おい、こいぶー。
ラヴドライブの西澤さんが22日土曜日の午後7時からの松本人志の番組に出るそうだよ。ぜひ、観てくれってさ。
耳鼻科の待合室でよんでた高橋留美子の「らんま1/2」、つい全巻中古でそろえてしまう。
| 2010年05月12日(水) | こいぶー連絡 |
おい、こいぶー。さっき郵便局からCDRを送ったずら。
これでビートルズはコンプリートやろ。
「The Beatles」と書いてあるのは通称「ホワイトアルバム」という2枚組だ。
発表された順番で聴いたほうがいいと思うぞ。あとから耳の記憶を整理してもいいけどな。
ツェッペリンは2と4を送った。次に聖なる館とフィジカルグラフティを送る。
おまえこないだ菊地雅章のAAOBB(ALL NIGHT ALL RIGHT OFF WHITE BOOGIE BAND)に
激しく反応していたけど、ジャズ聴くか?
図書館にあるマイルス・デイヴィスをまずは全部聴いとけよ。
| 2010年05月11日(火) | 清水俊彦さんについて。ニセコロッシ観。 |
清水俊彦さんについて。ニセコロッシ観。
おれも清水俊彦のジャズライフ連載や福島恵一のジャズ批評連載を読んでなければジャズオルタナティブを聴いてなかったずら。
アウトゼア誌作成時に横浜ジャズプロムナードで藤井郷子さんや座間裕子さんと清水先生にお会いしたことあるだけなんだけど、
おれへのコメントは5秒であとはずっとかわいい座間さんばかり見つめていてこのえろじじいと激しく共感!した記憶しかない。
生前親しかったひとたちからの証言をきくと、なにやら更年期に発症したパーキンソン病の薬の副作用もあって、
幻覚、妄想、思考がまとまらない、幻想と現実が混濁する、という苦しみがあったことは容易に想像されると、
それはおれの知り合いの医者も言っていたけど、正常に戻るときがある病状時期はなかなか切ないものがあるらしい。
大友良英さんの文章■を読むと、
自分の作品だけ切り取って古本屋に処分していた可能性、その悲痛さを思う。
おれは情状酌量めいた事実の不明確なところを書いてしまっているのだろうか。おれは愛読者として失格だな。
福島さんのレクチャー、「触発する清水俊彦像を示唆してみせる」愛情のある素晴らしい営為に、つい余計なことを書いてしまった。
80年頃だっけな、スイングジャーナル誌で清水先生が年間ベストを書いていて、半分以上がECM作品なのに驚いたことがある。
先輩が「いや、あのベスト選は輸入盤が対象外だから、仕方なく国内盤になってるECMを結果並んだということだよ」と
助言してくれていたなあ。
ジャズオルタナティブが出版されたあとのジャズライフ誌連載分はまだ未発表のままな気がする。
群馬の倉庫にはその頃のジャズライフ誌がまだあったはずなので、発掘してまたそういうCDたちを聴いてみようかな。
| 2010年05月10日(月) | 福島恵一「耳の枠はずし」第4回 複数のことば① 清水俊彦を聴く |
福島恵一「耳の枠はずし」第4回 複数のことば① 清水俊彦を聴く。■
剽窃論文問題に触れ、福島さんは初版で読んだときに「清水さんらしからぬ、つまらないものだ」と思ったそうだ。清水さんにはリニアに歴史を書くことはむしろ執筆してこなかった特質があるし、またその書籍の執筆依頼を断れなかったであろう人脈的背景もうかがえるとの指摘。
清水俊彦で検索をかけると同名の小児科医と剽窃問題とキーワードが出てしまう現状。
福島さん自身、清水さんのテキストに触発されなければフリー・ジャズや即興を聴くことはなかったとも。
平岡正明との対比や、なぜ清水俊彦だけがポスト・フリーという切断面を記述することができたのか、詩人としての清水俊彦とその背景、高等遊民の系譜、などが論考された。
おれなぞは高等ユーミン???荒井由実?松任谷由実?着飾ったユーミンの想像をついしてしまい、ひとりでうつむいてしまったが。
久しぶりに聴いた音源には圧倒され、初めて聴いた音源には驚愕した。
ブラクストンの『フォーアルト』は血の噴き出すような攻撃的なソロだったと記憶していたのに、ずいぶん理詰めで、現代音楽の思考のように吹いてるように実感してしまった。
ブラクストン72年のシリーズFという録音は初めて聴いたけど、このサウンド、そのままECMサウンドじゃないですかっ!サーマンECMに近いものがあるではないですか。どうしてなんですか福島さん。
ジュゼツピ・ロ−ガンは学生時代にアナログ盤を買って「間違いなくもう聴かない!」とマージャン部屋の天井のかもいにジャケを陳列して数年し彼女と引越しをするときにほこりとヤニに汚れたためゴミで捨てられていた盤なのに、なにげに良かった。
いちばん驚愕したのはレイシーの『Lapis』だ。こんな演奏をしていたなんて知らなかった。
フィールドレコーディングも実験音楽も即興もプログレも音響もごった煮で入った先鋭盤ではないですか!これ、まじ欲しい。
| 2010年05月01日(土) | 学生時代に書いたという川島素晴さんの吹奏楽「ファンファーレ」にノックアウト |
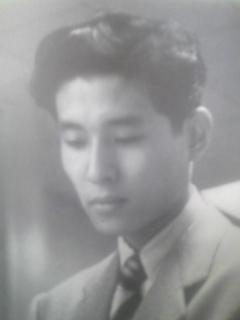
むかしおれの夢に出てきた黛敏郎はこの顔だった。
上野の奏楽堂へ吹奏楽を聴きに出かけた。■
「奏楽堂の響き3」
選曲は、「戦前・戦中世代のマーチ集」、「3人の会の音楽」、「新世代と新編曲」の3つのテーマで、貴重な発掘スコアもある。
学生時代に書いたという川島素晴さんの吹奏楽「ファンファーレ」にノックアウトされた!このひと天才だろ!
つうか、全国の吹奏楽プレイヤーのみんな、ここに21世紀の吹奏楽があるぜ!
スピード感があり、わかりやすく、スリリング、かつ、かっこいい。
委嘱初演の「吹奏楽のための協奏曲」は、作曲者が「相撲を観て手を握るかんじで聴いてください」などと言うが、
このきっぱりとコンポジションの突き抜けるかんじがいい。これも21世紀の吹奏楽のスタンダードになるべき悦びだ。
とにかく、おれはいま、それだけ言いたい。
それにしても、奏楽堂の椅子は硬いし、ただでさえ血圧の低いおれは、おしりのほっぺに血が通わなくなって、シビれるし、
さんざんなコンディションでいろいろ聴いてきたんだが、
吹奏楽はしょせん吹奏楽だろ!オーケストラの弦楽表現がないだろ!と思っていたが、
回転寿司はしょせん回転寿司だろ!に異議をとなえたい心境だ。なんだそれ。
会場で、なんと、明日行く京都のコンサート会場で売られる
「黛敏郎の世界」京都仏教音楽祭2010実行委員会編集というきわめて貴重な本を入手する。2500えん。
そこで、
黛が1959年に書いた「私のモダンジャズ論」におののく。
「実は、こうして抽象化され、形而上化された、一見まるでジャズではないと見做されそうな音楽にこそ、ジャズの未来を賭け得る新しい曙光が認められることを、私は固く信じて疑わない。」
と、結論付ける黛の視野は21世紀の現代ジャズすらも見通していたようだ。