DiaryINDEX|past|will
| 2007年09月30日(日) | 新宿ピットイン、ノルディック・ヒート2007 |
今日聴いたCD。
フェレンク・ネメス。聴くほどに、いい。これ聴いていると、『ユニバーサル・シンコペーション』や『ネイバフッド』の支持のされ方が腑に落ちるようになった。そのリズム、に。この盤のほうが根本的に演奏に生命力がある。格は下かもしれんけど、やはり。
オールド・アンド・ニュー・ドリームス。ECMが79年に問うてみたオーネットリスペクトバンドとも言うべき提出。砂上の楼閣に過ぎない、と、小野好恵は書いていた記憶がある。ひさしぶりに聴いたけど、なるほど、こげなオーネットの譜面化ともいうべき作業には、今となっては制作者アイヒャーの不遜な帝国意識が感じられる。しかし、彼らの演奏が語るドイツロマン主義化した望郷の演奏意識、は、オレなりには胸をうつ。終わった学園祭の風景にあって、キャンプファイヤーをたいてみているのだ。比較されるべきは、大友良英ONJQライブ、の、歴史的勝利だろう。
リュック・フェラーリ Luc Ferrari。プログレロックじゃね?と切り捨てようとするが、おれが見ているこの風景、光景を成り立たせている、大切なおれの記憶とか、情緒を持つ根拠、とか、日常の知覚を構造化する脳の機能を壊してしまうような恐怖を感じる。この山の緑も、排気ガスも、練馬区の地下のマグマも、そこを歩いている保育園児の記憶も、おれの赤い自転車の塗料も、粒子に過ぎない、と、言い募っている音楽。そんな音楽ってアリなのか?だから怖いんだよ。
ブーレーズ・プレイス・ヴァレーズ。
いやー、ファラーリのあとに聴くと安心するなー。早川SF文庫の、過去に書かれた未来についてのストーリーを読む、安堵感がある。あとに生まれた世代というのは、たとえばブーレーズやヴァレーズに対するわたし、は、すごく優越しているものなのかもしれない。それはどういうことかというと、おれの息子がミスチルをコンプリートで聴いた経験は、たとえば、彼はもうビートルズとかを聴かなくても困らないんだよね。ピカソやマイルスを知らなくても新しい世代が平気なのは、もうそれらは日常のどこかに潜んでしまって精神を刺激しているから、と、省略できるというか。
きのう長女とドライブして、ミスチルを何ヶ月ぶりかに聴いてみた。「あんまり憶えてないんだ」と、いろいろ人生を彩った記憶に感謝するというか、銭湯の待合室で首相が変わったとかミャンマーの軍事政権とか大相撲の優勝とか他愛のないことを話している時間のあたたかい輝きに、おれにとって音楽なんて囲碁将棋の趣味に興じるじいさんとそんなに変わんないんさね、コンビニにジュース買いに行こう。

いやー、これは、必見でしょう。
新宿ピットイン、ノルディック・ヒート2007。■
マッツ・グスタフソン、インゲブリクト・ホーケル・フラーテン、ポール・ニルセン・ラヴのセットが観たいぞ。
つい。おざけんを見てしまう。ほとんど歌う詩人。王子様後期の彼の高みは、振り返らない美しさを示していた。東大文学部卒。
■
■
| 2007年09月29日(土) | ルネッサンスの「ノーザン・ライツ」、イエスの「世紀の曲がり角」。 |
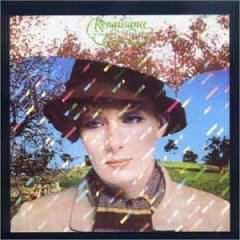
さっき、さ。
NHKの特集番組かなんかの予告、の、BGMに、ルネッサンス■の「ノーザン・ライツ」■
が、かかった。
アニー・ハズラム(女性ヴォーカルのなまえ)の声!、とブラウン管に向かって叫ぶ。なんでおれは憶えているんだ。
聴いたとたんに、おれの指さきや、薄くなった頂頭部や、股関節、ひじのくるぶし、くちびるや眼球、が、高校2年生に戻ってゆく感じを、鳥肌が立つように、ざわざわざわー、と、自動的に感じてしまってほんとうに驚いている。眼球が!、だぜよ。
ついさっき駅前を「今日は疲れた、しんどい」と歩いていたおっさんが、猛ダッシュで飛ぶような全力疾走(おれはこれでも陸上やっていたんだ)をできる身体に変化してしまったのだ。
そんで。
高校のときミーハープログレ好きだったわたしは今、
かれこれ30年近く耳にしていない曲なのに、まざまざと耳によみがえって脳内繰り返し再生をしはじめている、
イエスの「Turn Of The Century」(世紀の曲がり角)。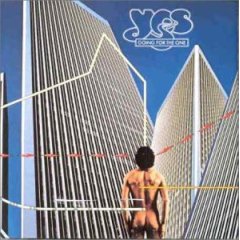
あ、あ、あ、あ、あ。
いっきに「千と千尋の神隠し」の終盤シーン、千尋がゼニーバのところへ行くのに水に覆われた駅に向かって歩く、あの場所、に、ぼくは居るではないか。
わたしにとっては、プログレとはファンタジーであり、イマジネーションであるのだ。イエスの「世紀の曲がり角」を聴きながら、高校2年生のわたしは白石区菊水元町の2階ベランダから石狩湾に向かって輝く夕焼け、壮大なパノラマとなった音をたてて動く雲、を、見ていた。プログレとは進歩ロックでも、技巧でも、サイケデリックでも、クラシックコンプレックスでも、コバイア語でも、南方プログレ左派でも、ディシプリンでもなく、ドラマチックでイマジネーティブな感動に過ぎないのだ。それが、ミーハープログレ好きであるゆえんだ。
このあたりは、ミーハーECM好きとしてスタートするのと同値なのだな。わかりやすすぎー。
そんなことは書いていると、ばかにされそうなので、ちょいと次に、いかに孤高のハードコア・ジャズ・リスナーとして、キャリアを積んでいったかについて、書いてみたい。
やっぱり、寝る。
| 2007年09月28日(金) | トロピカーナ果実酢(350ml、160円)。Otomo Yoshihide's New Jazz Quintet "ONJQ Live"(DIW)。 |
7月あたまにコンビニで飲んで、「うおお、これぞ求めていたドリンク!」と思っていた、トロピカーナ果実酢(350ml、160円)。■
すぐにどこのコンビニにも見当たらなくなってかなしい思いをしていたのですが、
2ヶ月ぶりに、港区港南のローソンで出会う。
ひさしぶりに品川の長女と買い出しとお食事と池上温泉デートをする。彼女はトロピカーナ果実酢は苦手だという。はやく寒い冬になって旬の生カキを食べたいー、と、のたまっておった。
品川区品川図書館。港区港南図書館。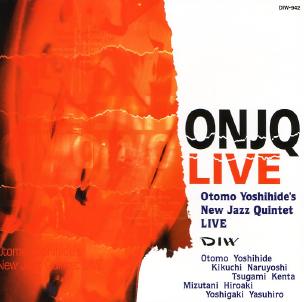
Otomo Yoshihide's New Jazz Quintet "ONJQ Live"(DIW)を聴く。
これはすごいライブ記録だ!あからさまにドルフィー、オーネットをアナグラムしたような、あまりにあまりな演奏なので、笑ってしまう1曲目も、見事な演奏が押し切ってしまって、「まいりましたー」とドキドキしてしまうのだ。
2曲目の「Flutter」を聴いて、彼らのファースト、2001年、Tzadikから出たばかりの『Flutter』を聴いて、「いやいやいや、これはサイン波+ジャズカルテットなんかじゃないですよ、この気持ちよさは単なる足し算じゃないですよ、何て言ったらいいんだ、これがジョン・ゾーンのレーベルで出ているところに日本のジャズ業界のダメさかげんですよ、これ、もう、傑作!」と饒舌になってジャズファンをやっていた6年前、を、思い出してしまった。あのあと、こんなライブが出ていたのか。つい聴きそびれていた。
彼らが推し進めている時間、意識の流れ、が、静寂を思わせるような、音楽のマジックが起こっていたことを過ぎ去ってからみんな知るの、という、得難いライブなのだ。(はい。これ、日本語になってませんね。いいんです。日記ですから。)
| 2007年09月27日(木) | 土星の環 W・G・ゼーバルト |
ロウストフトの南を三、四マイルにわたって、海岸線は長くゆるやかな弧を描く。草の生えた砂丘や低い崖の上方を通っている歩行者用の小径からは細(さざ)れ石の平浜が見下ろせるが、その浜に沿って、夜となく昼となく、一年中いつなんどきでも、棒と縄と帆布と防水布で思い思いに拵(こしら)えたテントのようなものがずらりと並んでいるのを、おりふし眼にすることがあった。それらは長い列を作って、ほぼ等間隔で海端に続いていた。あたかもどこかの流浪の民の最後の生き残りがここに、この地の果てにたどり着いて、これまでの窮乏も流浪もそのためにあったと思わせてくれるような、はるかな過去からの悲願であった奇蹟のおこるのを待ちわびているがごとき光景だった。・・・
| 2007年09月26日(水) | ステファン・ウインターは宣言している |
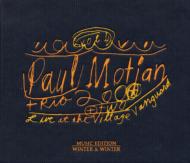
タイムリーを逸するのはわたしのトレードマークである。ヤコブ・ヤングのライブもメセニー=メルドーのライブも行けないのー。
モチアン・トリオ2000のヴィレッジヴァンガード・ライブを国内盤(ボンバ・レコード)で入手したのは7月20日■で、「おおお!」と思っていたんだけど、
せんたくせんざいの裏っかわに落っこちたまま行方不明になっていたというか、買ったことも忘れてて、さっき見つけてあわてて作文するのさ。
「ヴィレッジ・ヴァンガードでのポール・モチアンTrio2000+Twoによる忘れられない一週間のライブの模様を記録している。」
ステファン・ウインター自身のライナーだ。
「ウインター&ウインターはこの一週間にアルバム三枚分を録音した。」
「音楽はいつも生まれる時と場所に深く関わっている。17世紀のような非凡な時代とヴェネツィアのような特別な場所が独創的な芸術の生まれるきっかけとなる。アントニオ・ヴィヴァルディの活気溢れ、間違えようのないバロック音楽は、その時と場所の非凡な組み合わせなくして存在しなかっただろう。人種のるつぼニューヨークと20世紀とくればジャズ。そしてニューヨークの中心にあるヴィレッジ・ヴァンガードはこの音楽の最重要機関のひとつである。・・・」
この、プロデューサーとして自信溢れる記述に、ジャズファンも酔いしれようではありませんか。
(あれ、なんかへんな文体だし)
いやー、じつにいいライブだ。聴きながら、よだれが出まくってるし。至福である。
ただし。みんなに言っておきたいのは、『Paul Motian Trio 2000+One / On Broadway Vol. 4 or the paradox of continuity』Winter&Winter 2006■、これが、奇跡的、かつ、決定的に、音楽が生成する瞬間に満ちた録音であったこと、歴史的なものだとおれは捉える。おれの耳の感性を賭して言い切る。
こういうふうに手をぎゅっとにぎって確信が持てて、日記を書いているわたしは幸福である。
ECMレーベルをコンプリートするわたしは、次なる完全聴破ターゲットをハットハット(ハットロジー)にしてみたり、ウインター&ウインターにしてみたり、スクリューガン、サブローザ、英レオ、クリプトグラモフォン、サースティイヤー(ブルーシリーズ)、ブハーストにしてみたり、しているうちに、いわゆる日本銀行券という実質レコード交換券を十分に手に入れられないままに、むだに年をとってしまった。
そいえば、ツァディックも集めようと思ったこともあったのだ。
おれは幼稚園のときに牛乳のフタを集めた。
メーカー別、日付別に。
コンプリートに向かう使命感。
牛乳が発明された日からの完全コンプリートに向かう途方もない陶酔。
一枚一枚をいつくしむように眺めては指でなでて並べてみる。
年少のがきをつかまえて「おまえんちにある牛乳のふたを集めてぜんぶもってこい!」と5さいでおぼえた恐喝。
幼稚園中に有名になったコレクターまーくんは母親に叱られまくるが知るかそんなもん。
ある日、親切なおばさんが牛乳屋のゴミ箱から袋いっぱいの牛乳のフタをおれにくれた。べたついたへんなにおいがする牛乳のフタの塊り。
おれはなぜか、泣きたい気持ちになった。
あの、世界が腐って壊れてしまう感じ、を、おれは求めてCDを聴いているだけなのかもしれない。
何書いてんだか・・・。
| 2007年09月25日(火) | 90年代はザヴィヌル・シンジケートの活動が後世に残る |
ほう。
けいまくん、インスピレーションを得られたコンサートに行ってきたのか。
うらやましいのう。
ジョー・ザヴィヌルが亡くなったこと書いたっけ。
思えば、90年代はザヴィヌル・シンジケートの活動が後世に残る、いろいろな過去から未来からの文脈が交差する場所に鳴り続けた音楽を放ったのがザヴィヌルだった、ということかもしれません。
歴史というものは残酷かつ嘘つき。そして虚構な性質を帯びている。
過去と未来から中吊りにされて偶像化・歴史化することはよくある。
本人も意図できなかった聴取のスケールでもって測られてたりするんだな。
ぼくの高校の日本史のせんせは唯物的史観(だっけ・笑)の持ち主で、
歴史は英雄ではなく民衆が作ったのだと500回くらい演説した。
わたし、という民衆が、90年代ザヴィヌルを「これ、すごいだろ!」と
若いリスナーにすすめて、その意識がリレーされたとする。
音楽を聴こうではありませんか。
| 2007年09月19日(水) |
| 2007年09月18日(火) | 「脳は変奏する」 |
「脳は変奏する」
わたしが書いているたったひとつのことは、生きているわたしたちの脳は音楽を変奏するということなのだ。
さっき夜勤明けで熟睡した夢の中で、次々と閉まってゆく午前0時の国道沿いの食堂街をあえぎながら走って何か注文できないとメシにあたらない、ラーメンがあるぞ、でもとんこつだ、かつおのたたきの定食、うう、いまいち、はまちのさしみと餃子の定食、それいい、おばさん注文たのみます、厨房からオヤジが「おう、ラストオーダー」と怒鳴る、ありがたし、なんだオヤジ、小金井の酒屋のオヤジじゃねえか、と、カウンターに座ろうとするのに、おばさんぼくがすわろうとするカウンターにうな重おいたりインスタント焼きそばをお湯を入れて置いたりする。こまっているとケータイに着信があって、相手は誰だかわからないが、サイトのミュージサーカスはジョンケージだろう、というので、あ、これは吉田秀和だ、と、思い、わたしたちが言いたいたったひとつのことは脳は変奏するということなんですよ、ぼくが聴いたゲルギエフのストラヴィンスキー春の祭典はすでに変奏であるのと同時に、幼少期に円谷プロ怪奇大作戦ウルトラマンのBGMで現代音楽のエッセンスでディズニーのサントラ作用で聴いてできたぼくの耳が聴く変奏、今日の記憶明日の記憶と経年で予期せぬ様態を見せる変奏、とかですね、と、漠然と説明をしなければならないはめになっている、おなかがすいているのに、でも、ケータイに演説しながら、ああそうなんだ、と、ひとりごちながら目がさめた。
ぼくの赤血球も音楽を聴いて音楽を変奏しているのだ。と、起き上がりながら言い換えてみて、その表現はちょっとガキっぽいかなと思う。
今朝は、パスコの十勝バタースティック2本と牛乳だけで、吉田秀和全集3「二十世紀の音楽」(白水社)の「サイバネティックとチャンスオペレーション」「二十世紀音楽研究所にふれながら」を読みながら床についたのだった。そしたら、そんな夢をみた。吉田秀和も同じ夢を見ていたと思う。
| 2007年09月17日(月) |
干瓢。かんぴょう。間氷期。
長男が、いまって間氷期じゃね?、という。
おめー、だからおれは地球温暖化を推進してできるだけくるまで移動する、アイドリングだいすき、よそのクーラーはこっそり下げる(おれ自身はクーラーだいきらいだ)、会社のポットはこっそり再沸騰、地下鉄のエレベーターは待ってひとりで乗る、ひまな午前はじゃんじゃん駐車場に水まき、バンクフェス以降のミスチルだいきらい、と、一貫しているだろ。気付くの遅い!
そんなんだからざーどだのたけうちまりあだのに泣けるのだ。
おれが、生死をかけた親友のお見舞いに、サニー・マレイ、アルバート・アイラー、ドン・チェリー、ヘンリー・グライムスらの、血の噴き出すような生命力そのものを音にしたような、1965年の録音、日本の誇る音楽の英雄杉山和紀が復刻、の、1曲、と、そして、小沢健二、ソロ、第一作シングル、葉の伸びる生命力そのものを歌にしたような、「天気読み」、を、持参した、2007年に歌詞を味わう「天気読み」、100年を越える音楽、は、やはり、このようなものだ。
おっといけねえ、竹内まりあ「ふたりはステディ」とZARD「揺れる想い」をくちづさんでしまったい。
いい歌なんだから、しょうがないだろ。
| 2007年09月16日(日) |
わが師匠が、大腸ガンの開腹手術をした。おなかに生々しくタテに入った深い切り傷、というか、これ以上深い切り傷はないわけだけど。
その腹部を縦走している切れた血の色をした肌の断層、縫った跡をみせてもらった。
おれが親なら、「な、なんでこんな腹切られるような心配かけんだよ!」と、あたまのひとつでもはたきたいかもしれない。
ガンの転移について担当医から説明があるという午後5時まで、音楽のはなしはほとんどしなかった。
ペットサウンズとポールモチアンの音楽については出てきたっけ。
転移していた、というメールがきた。
| 2007年09月15日(土) | 2まい40曲で200えん |
100えんショップのジャズのCD。けっこう聴いたことない曲ばっかり。2まい40曲で200えん。
「That’s Jazz volume one」
01. A Morning Date / Louis Armstrong & Earl Hines
02. In The Jazz Band Ball / Mugsey Spanier
03. Indiana / Red Nichols
04. The Minor Drag / Fats Waller
05. I Found A New Baby / Sidney Bechet
06. Way Down Younder In New Orleans / Jimmie Noone
07. Tea For Two / Louis Armstrong
08. Believe It Beloved / Bill Coleman
09. The Entertainer / Scott Joplin
10. Love Is Just Around The Corner / Pee Wee Russel
11. London Café Blues / Lu Waters
12. Shanghai Shuffle / Buster Bailey
13. Vibe Boogie / Lionel Hampton
14. It Don’t Mean A Thing / Duke Ellington
15. Malibu / Benny Carter
16. End Of The World / Stan Kenton
17. Heigh Ho ( Dwarves Marching Song ) / Bunny Berigan / Gail Reese
18. High Society / Louis Armstrong
19. Stampede / Fletcher Henderson
20. At Sundown / Mugsey Spanier
「That’s Jazz volume two」
01. I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate / Mugsey Spanier
02. Sweet Georgia Brown / Red Nichols
03. Sweet Lorraine / Jimmie Noone
04. Stars Fell On Alabama / Louis Armstrong
05. I’m In The Mood For Love / Bill Coleman
06. The Kissing Bug / Duke Ellington
07. Walking The Dog / Bunny Berigan
08. Gatemouth / Kid Ory
09. Elite Sinopations / Scott Joplin
10. Who’s Sorry Now / Benny Carter
11. I Wish I Were Twins / Fats Waller
12. All Gods Chillun Got Rhythm / Fletcher Henderson, Jerry Blaki
13. Embracable You / Pee Wee Russel
14. Sceamn Boogie / Lionel Hampton
15. On The Sunny Side Of The Street / Louis Armstrong
16. When The Sun Set Down South / Sidney Bechet
17. Figety Feet / Lu Waters
18. Intermission Riff / Stan Kenton
19. Rhythm, Rhythm / Buster Bailey
20. Black Bottom / Benny Carter
| 2007年09月14日(金) | 緊急アピール「小泉文夫記念資料室(東京芸術大学)の資料散逸危機?」 |
小泉文夫の資料の分散と助手の常駐の廃止に反対。小泉文夫の資料の一括管理と助手の常駐に賛成。
さきほどわたしはメール送信しましたが。
こちらのサイト■もご参照ください。
この週末のメール送信(署名活動)が重要のようです。
有志が月々200円ずつ出し合ってなんとかする、とか、大金持ちのパトロンさんになんとかしてもらう、とか、も、ないのかな。
| 2007年09月13日(木) |
岡村靖幸の「真夜中のサイクリング」>■
「ただいとしい」>■
Pat Metheny Group - Are you going with me?>■
Silence - Jan Garbarek,Egberto Gismonti,Charlie Haden>■
Ellery Eskelin w/ Andrea Parkins & Jim Black>■
Gilfema - Tin Min フェレンク・ネメス、リオ−ネル・ルエケ、のトリオだー>■
ぼくらが旅に出る理由ライブ>■
Flipper's Guitar テレビ出演 1991.07.08 WOO music satellites>■
Kenji Ozawa – Lovely>■
ドンキーコング2>■
東芝CM>■
| 2007年09月12日(水) | 「アタック№1」と「夜明けのスキャット」 |
メンデルスゾーン
詩篇114 「イスラエルの民はエジプトを出で」 作品51
賛歌 「おお主よ、救いを見出させたまえ」 作品96
詩篇98 「主にむかって新しい歌を歌え」 作品91
カンタータ 「ラウダ・シオン」 作品73
ミシェル・コルボ指揮 リスボン・グルベンキアン合唱団および管弦楽団
なんで、この盤に癒されているかというと、合唱+オーケストラ、じゃないけどー、の、響き。
おれは名古屋で聴いた三善晃を想ってこれを聴いてるんだい。
けっこう古そうな録音だけど、録音データが出てないエラート盤で。通じてるんだよ、おれん中では。
こないだ仕事中に。
アタック№1のイラストが吊り下がっている場所で、有線では由紀さおりの「夜明けのスキャット」が流れてたんだな。
20代の部下に「いやー、この歌、やっぱり名作だわ、この曲、知ってる?」と、たずねたら、
「あー、これはアタック№1ですよねー」と即答されたのです。
「お、おえー?こ、これがアタック№1に聴こえんのかあ?・・・聴こえるわけねえべや、って、・・・聴こえんじゃん!」
「くるしくったってー」「あーいしあーう」
「かなしくたってー」「そおのーときーに」
「コートのなかでは」「とーけーいいわー」
「へいき、なの」「とまるー、の」
やっぱおれのみみってへんだー
| 2007年09月11日(火) | 杉山和紀さんをさがせ(4) |
ニフティ会議室「倶楽部ECM」で、わたしは「ちるちるみすちる」というハンドルで、悪態の限りを尽くしていた時代があったのですが。
大阪のECM者の方から情報提供をいただきました。
「ほんの少しですが杉山さんについての紹介、顔写真、インタビューが記載されています。」とのこと。
常盤 武彦著『ジャズでめぐるニューヨーク―充実のミュージシャン&クラブ・ガイド』(角川oneテーマ21) (新書)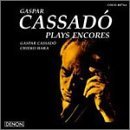
『カサド・アンコール・アルバム』
翌年、原智恵子(ピアノ)と結婚するガスパール・カサド(チェロ)、1962年のクリスマス・イブに麻布の飛行館スタジオ(現・サウンドシティ)で二人で録音したもの。
昭和37年。
むかし子供のころに見たカーテンの柄やクッションの布地の肌触り、石炭ストーブのあたたかさ、そして、空気のにおい。どうして、そんなものをわたしはこの音楽、この演奏に感じてしまっておどろいている。
だいたいサンサーンスの白鳥とかフォーレのエレジーとかリムスキーコルサコフの熊蜂の飛行だなんて、このおれが、聴くと思うか?あほらし、おとといきやがれ、じかんのむだ、と、言うくらいのラインナップ。
つよく、つよく、音楽に抱きしめられているんだ。このうっとうしい雨も、あたたかくやわらかくすら感じる。
| 2007年09月10日(月) | ロヴァ耳ECMもの通信 vol.325 2007/09/10 カロリン・カールソン |
全国のジョン・サーマン漂泊の独り旅旋律愛好家のみなさん、こんにちは。人生に失敗してますか?してますね。奥さんとうまくいってませんか?いってませんね。ついひとりで70年代ガルバレクのレコードを聴いてませんか?ゆうべも聴いてましたね。
ジョン・サーマンが疾風怒濤のザ・トリオを経て、多重録音ソロの道を歩みだしたのは、欧州の舞踏家カロリン・カールソンの伴奏をやった影響から生まれた『アポン・リフレクション』■からです。これはたしかCDにも書いてあります。
そのカロリン・カールソンが、“大野一雄フェスティバル2007”にて10月5日、来日公演を行います。■
あと。
13日・14日には、吉増剛造( ポエトリー)+土取利行( 音楽)というドリームマッチも設定されているという・・・、これは聴きたい。
| 2007年09月09日(日) | 縄文以前のインプロ時代 |
南の島に住むガールフレンドから、土取さんのHPにのってるよ、と。
ほんとだ。>■
土取さんにとってインプロは通過して久しい。
でも、そんなの関係ねえ。
そだねー、縄文以前のインプロ時代の土取さんを聴いてみたいよね。
高木元輝とやってる!んご、んぐ、80年にビリー・バング盤で、ウイリアム・パーカー■とやってる!
一昨年、土取さんと坂本龍一のデュオ盤『ディスアポイントメント・ハテルマ』■が復刻されましたが、そ、そ!ここでのjazzamurai氏のレビューが、この作品をきちんと位置づけているように思います。いやはや、あこがれるようないいレビューですね。
うおおお。なんかジャズ萌え。ウィット・ディッキーのCD、ジャケこれ>■、かけて。これ。■
タイコのウィット・ディッキーが自覚的に叩きのギアチェンジを自在にあやつっている。ロブ・ブラウンのピュアなアルト、健在すぎ、だし。ジョー・モリス(本職はギターなんだぞ)のベースはウイリアム・パーカーばりの重たさを放ちながら黒光りして硬いんだ。
ゆうべは昔作った編集CDRをかけて、126キロのドライブをした。
音楽は、配置されプログラムされたときに、互いに干渉し、支え合い、べつものにさえ聴こえたりする。その宇宙的なありように、即身成仏の意味するところを感得した気持ちになったり。
編集CDR 『 heaven 』 2005.10
1. birdsong / Stefano Bollani, Paul Motian from 『Tati / Enrico Rava』(ECM1921) 2005
2. Since I Left You / The Avalanches 2001
3. Dark Awing / Tomasz Stanko, Tomasz Szukalski, Edward Vesala, Peter Warren 1974
4. Cafe de 鬼(顔と科学) / 電気GROOVE
5. HEAVEN / 浜崎あゆみ 2005
6. EXIT TV drama ver. / EXILE 2005
7. You Know My Name (Look Up The Number) / The Beatles 1970
8. Son Of Sam / Elliot Smith 2000
9. Honeycom.ware / 100s(中村一義) 2004
10. Notes from heaven / William Parker and Ad Peijnenburg (19:56) from 『BROOKLYN CALLING』 2004
11. マレイ・ペライア/バッハ・イギリス組曲1番より“アルマンド”
12. しずかな いけ A Quiet Pond / 高橋悠治 絵本『けろけろこころ』福音館書店 2004
| 2007年09月08日(土) | 杉山和紀さんをさがせ(3) |
さらなる情報提供が。杉山和紀さんに関して、
「土取利行さんの『ブレス』はお聴きになってませんか?」
だけのメール。んご、んぐ、(Cサザエさん)…、そこに杉山さんがいるのか!
ううむ。わたしには、ECMつながりというか、札幌、群馬、所沢、恵比寿、京都、大阪、小金井、国分寺、港区、文京区、フィンランド、などにお住まいの耳トランスな同年輩以上の方々が、数年に一度の割合でこそっと耳打ちするような情報をいただくことがあるのですが、それは、わたしにとっては何らかの、弘法大師でもミューズの神でもカムイコタンでもいいとは思うのですが、存在からのお導きだと収めるならわしに。
がー、聴いたことねー!
土取利行は『サヌカイト』を20代のころに聴いて、息を詰まらせていた記憶しか、いま、ないのー。
お、G-Modern誌の19号に土取利行インタビューというのがあるらしい。ウェブで復刻させてくださいー。
それにしても、杉山和紀さんが出がけた音楽のラインナップ、すごすぎないか?
| 2007年09月07日(金) | 杉山和紀さんをさがせ(2) |
(1)は、この日の日記、ね。>■
情報提供をいただきました。
杉山和紀さんについて。『STEREO SOUND #158 2006年』に興味深い記事がありました、連載記事の『嶋護の一枚 the BEST Sounding CD』(P538)。
Kazunori Sugiyama=録音ミキサー
ブラック・セイント・レーベルの優秀録音盤(空間の存在感や演奏家の気配の描き方も、ソリッドなだけでなく独特のしなやかさがある)の録音ミキサーのクレジットを見るとKazunori Sugiyama とある。
主な作品『ライヴ・アット・ブルックリン・アカデミー・オブ・ミュージック / ワールド・サキソフォン・カルテット』『ヴァイオリン・ソロN.Y.C 1980 / 小杉武久』
1990年頃録音ミキサーを止め、プロデュースに専念するようになった。
そだ。そいえば、フリクションがツァディックTzadik(ジョン・ゾーンのレーベル)で1999年に新作を出したことがあったよ!■
いや。ジョン・ゾーンは杉山さんの協力を得てツァディックを得たのだ。■
それよりもなによりも。わたしが知っている限りでも数人のリスナーの人生を変えてしまった、あの、『ストリング・カルテット』。ここで、出会うか。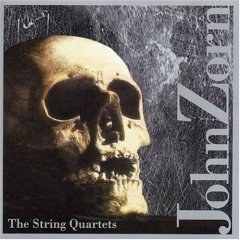
John Zorn : String Quartets (Tzadik)1999
| 2007年09月06日(木) | Music Today 21 「ジャン=クロード・リセ」<室内楽>〜全曲日本初演 |
今日の音楽 Music Today が今でもやっている、くらいの認識しかなかったのですが。
ジョン・ケージが晩年に辿り着いたミュージサーカスというコンセプト、の、最終形というよりも、最新更新版、『ユーロペラ5』(1991)、日本初演があった。
ほぼ3日間、リンパが腫れて臥せていたもので、見ることができなかった。
本橋内科クリニックで抗生物質の投与を受けてようやく快復基調に。医学は偉大だ。
今週9月8日、土曜日のコンサート、は、
「電子音楽マニアなら、彼の名を聞けばチャウニングやマシューズと並ぶ初期のコンピュータ音楽の最重要人物とピンとくるのでは? そのリセがサントリーの現代音楽祭のテーマ作曲家として来日する。」と、紹介される作曲家、ジャン=クロード・リセ。
サントリーホール国際作曲委嘱シリーズNo.31
テーマ作曲家「ジャン=クロード・リセ」<室内楽>〜全曲日本初演
曲目 ジャン=クロード・リセ :「少年」のための音楽(1968)/ピエール・アレによる広島の惨劇についての劇より「ナカ」〜ソプラノと4楽器のための、「転落」〜2トラックテープのための
:ヴァリアント(1994)〜コンピュータ処理によるヴァイオリンのためのインタラクティブピース
:対話(1975)〜フルート、クラリネット、ピアノ、打楽器、指揮者のための
:Tri-IX(2002)〜ピアノのための
:1台のピアノのためのデュエット「3つのエチュード(エコー、ナルシス、メルキュール)」(1971)〜ヤマハ・ディスクラヴィア・ピアノのための
:蜃気楼III(1979)〜16楽器とテープのための
:共鳴する音空間(2002)〜8トラック・テープのための
:オスクラ(2005)〜ソプラノとコンピュータのための
フランスでは、1970年代に、トリスタン・ミュライユ、ジェラール・グリゼイ、ユーグ・デュフール、フィリップ・マヌリといった作曲家たちがコンピュータによる音響解析に基づいた新しい創作世界を探究し、それは、一般に「スペクトル音楽」または「スペクトル楽派」と呼称され、日本でも、1990年代に入ってからIRCAMで直接学んだ作曲家たちを通じて紹介され、非常に大きな影響力を放ってきています。
ところが、これまで、あまり紹介されてこなかったジャン=クロード・リセこそが、このスペクトル音楽に直接影響を与えた張本人であることが、3日に行われた講演で明解に説明されました。もちろん、今年のフェスティヴァルにリセを招聘した湯浅譲二氏は、まさしくその功績ゆえにこそ、リセの紹介を企画したわけです。
リセは、ヴァレーズの数少ない弟子のひとり、アンドレ・ジョリヴェ(音楽に呪術的、宇宙的、始原的世界を求めた作曲家)に師事しており、最晩年のヴァレーズに、音響解析の探究を奨励された筋金入りの作曲家です。
世界で初めて、音響を構成することで音楽を創造したのがヴァレーズ。
リセは、そこで、作曲のために使う素材自体をコンピュータによる音響解析によって作り出し、なおかつ、その素材をさらに独自の、時間と空間を折り畳むイメージに基づき、(そこには、聴覚という知覚を用いたエッシャーばりの錯覚の導入もあります)「作品」として組織していく、というプロセスを辿ります。
リセの音楽のキー概念は、
「音のなかで、時間を遊ばせること」
「響きのテクスチュアの固定化および流動化」
「特定の音の身振り(ゼスチュア)によって発展するプロセス」
「音響の内部のハーモニクスを取り出した個別のコントロール」
「架空の非物質的世界の響きを実際の器楽の響きと融合させる」
等々、となります。
いやはや、ヴァレーズの名前にがぜん聴きに行きたくなったリスナーも多いのでは。
ヴァレーズはチャーリー・パーカーのアイドルであり、フランク・ザッパの父であり、ジョン・ゾーンの神であるという、そういう作曲家の孫弟子は電子音楽の始祖のひとりである、わけです。3000えんで聴けるのか。行けるひとはいいなあ。
| 2007年09月01日(土) | 画像は、次男がかいたもの。はやくマンガで |
きょうわ、ちとたいへんな、心理的に、体力的に、だったので、だらだら、かきのこします。
画像は、次男がかいたもの。はやくマンガで億万長者になって、おれに経費でCD買い放題させるという、おまえのこのよの使命をはたせ。
びーず、だの、ざーど、だの、わんず、だの、ぴんず、だの、そうず、だの、センスのないへんな横文字のJポップが出てきた時期があったな。
おいどんは、どれも、ちいとも、よいと、おもわんがの。
有線で、竹内まりあの曲がかかって、どんどんどんどん、という、ポップな決め技を使って、その、どんどんどんどん、に、さむいものを感じる。
クレバと草野マサムネの曲がかかって、「あなたがクレバいいのに」、に、さむいものを感じる。あついのに。
ぼくのたいせつな師匠が入院して腹部切開をするときいて、その不安な心理がシンクロし続けて、なんか、つらい。
同調してしまって、いるのだろうか。なんにもしてあげられないのに。同調していることで、彼の不安を軽減させられていられたらいいのに。