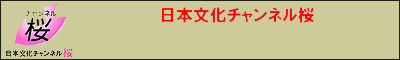目次|過去|未来
| 2002年08月23日(金) | 半空蝉(うつせみ) |
ここ何日か前から、涼しい日が続き、明け方など、寒さで目が覚めたことがあった。今朝も気持ちの良い目覚めで、花に水をやるため庭に出た。その時、庭の竹垣に立てかけてあったスコップの木の柄、上三分の一の所に、蝉の抜け殻が喰らいついているのが目に留まった。蝉の抜け殻は都会ならまだしも、この辺りでは珍しくもない。夏の季節の終わり頃、哲学の道を散歩すると、短い一生を終えた蝉や抜け殻など、道端にゴロゴロ落ちている、哲学の道大虐殺?の現場が見られる。
だけど、今回のスコップの木の柄に喰らいついている、空蝉(うつせみ)は様子が違った。近づいてよく観察すると、なんと殻から蝉が頭を出し、まさに脱皮しかかる状態で息絶えていたのだ。
七年に及んで地下生活をして、地中からようやっと這い出し、どこか小高い場所に這っていって、おもむろに殻を破りはい出ようとした時、明け方の急激な温度変化で、命運尽きたに違いなかった。しばらくじっと見ているうちに、志賀直哉の「城の崎(きのさき)にて」を思い起こしてしまった。
*******
・・・ ある朝のこと、自分は一疋の蜂が玄関の屋根で死んでいるのを見つけた。足を腹の下にぴったりとつけ、触角はだらしなく顔へたれ下がっていた。他の蜂は一向に冷淡だった。巣の出入りに忙しくその傍を這いまわるが全く拘泥する様子はなかった。忙しく立ち働いている蜂はいかにも生きている物という感じを与えた。その傍に一疋、朝も昼も夕も、見るたびに一つ所に全く動かずに俯向きに転がっているのを見ると、それがまたいかにも死んだものという感じを与えるのだ。それは三日ほどそのままになっていた。それは見ていて、いかにも静かな感じを与えた。淋しかった。
他の蜂が皆巣へ入ってしまった日暮れ、冷たい瓦の上に一つ残った死骸をみることは淋しかった。しかし、それはいかにも静かだった。夜の間にひどい雨が降った。朝は晴れ、木の葉も地面も屋根も綺麗に洗われていた。蜂の死骸はもうそこになかった。今の巣の蜂どもは元気に働いているが、死んだ蜂は雨樋を伝って地面へ流し出された事であろう。足は縮めたまま、触角は顔へこびりついたまま、たぶん泥にまみれてどこかで凝然としていることだろう。外界にそれを動かす次の変化が起るまでは死骸は凝然とそこにしているだろう。
それとも蟻に曳かれて行くか。それにしろ、それはいかにも静かであった。忙しく忙しく働いてばかりいた蜂が全く動くことがなくなったのだから静かである。自分はその静かさに親しみを感じた。
*******
志賀直哉の言いたいことはよく分かる、生の果ての死、動の終わりとしての静を蜂の死に重ね、そしてそれはもう、外的誘因がない限り、永遠に動かない。それを志賀はひたすら「静か(静謐)である、そして静(死)に親しみを感じる」と言っている。
ところが、今日庭で見た、半空蝉はその感慨にはたどり着かない。生の躍動最中(さなか)、それも、変身を遂げる直前で死んでしまったのだ。「ひたすら静か」とは到底感じられない。
ずっと見ていると、今にもぬれた羽をひろげ、少しの後、大空に飛び出していきそうな気配が残っている。ひたすら、「動」の気配が漂っているのだ。黒いキャビアほどの蝉の目が潤んでいるように見えた。
生から死へ天寿を全うした蜂と対照的に、生のただ中、十分力を蓄えて、変身を遂げようとするさなかの、不意の死。変な言い方かもしれないが、エネルギーがみなぎった死、のように思えた。