
|
 |
| 2005年07月14日(木) ■ |
 |
| 「食に知恵あり」 小泉武夫 |
 |
「食に知恵あり」日経ビジネス文庫 小泉武夫
「塩辛製造の原理は、原料の魚の内臓にある自己消化系の酵素、とりわけたんぱく質分解酵素の作用が主体となっている」うまみの主体になるアミノ酸がなぜ出来るのか、なぜこの料理はおいしいのか、例えばそういう科学的説明から、実際に食べたものしか分からないとんでもない『食通』の知識、二つが合体してこの人のエッセイには非常に説得力がある。
また、それぞれの食には古代からめんめんと続く歴史があるが、そのこの言及も多い。私の興味は大いに刺激された。
食の世界は奥が深い。私は塩の効果で、味付けだけでなく、薄い塩水に5〜10分つけて料理すると表面のたんぱく質が凝固してうまみが逃げないという調理法を初めて知った。
または『灰』の利用法。私はあく抜きぐらいしか知らなかった。しかし、胃腸や貧血の薬にもなるし、天然洗剤にもなる。保温性から調理にも使う。古代の人たちの生活も見える気がする。楽しい本である。
その他参考になったこと。
凍大根や丸ナスやかぼちゃなどを寒風にさらして干し野菜を作る。栄養成分も濃くなる上に、便秘や動脈硬化の防止、利尿効果もある。
米を煮て食べているため、硫化物の臭いが一部出ることがある。だから日本人は他民族が好まない納豆、味噌、タクアン漬けやにらなどの硫化物の臭いに嫌悪感が無い。
にんにく文化圏は中国や朝鮮半島、しかし日本は違う。おそらく質素な食事のため強烈な臭いは合わなかったのだろう。
ジンギスカンは旧満州の日本人の発明。モンゴル人は湯で煮た羊は食べるが、焼かない。また朝鮮料理のように調味料に直接つけない。
ツバメの巣とは本当に燕の巣である。マラッカ海峡に面したインドネシアやマレー半島などの断崖絶壁に住む海燕(アナツバメ)が小魚をついばんで巣に戻り、粘性の高い自分の唾液で固めたもの。
とろろやナメコ、じゅんさい、もずく。日本の『ぬらぬら』食はジャポニカ米だから。ぱさぱさではなく、粘質状なので、そこに副食がぬらぬら来ても何の違和感も無い。
豆腐の腐とは中国で『ぶよぶよしたもの』という意味。発明は8−9世紀。納豆は『寺の納所の豆』から来た日本生まれの食べ物。
奈良時代『延喜式』に「貝蛸鮨」がある。これはいいだこのなれ鮨。または蛸を石焼くして硬くなったものを削って食べるという方法もある。
煮汁を多くしたり、少なくして煮詰める料理が多い。
縄文時代には疏采の皮を塩付けにした簡単なものもすでにあった。『延喜式』には蕨、せり、アザミ、いたどり、フキなどを塩、味噌、しょうゆ、酒かすなどでつけている。
干物は日本が世界一。魚介類の水分を蒸発させると微生物の繁殖を抑えられる。
『播磨の国風土記』に「米飯にカビの生えたもの(よねのもやし)で酒を醸もさしむ」とある。もやしが種麹になっている。
(05.05.02記入)
|
| 2005年07月13日(水) ■ |
 |
| 総社西の弥生遺跡を探す |
 |
『総社西の弥生遺跡を探す』
県立吉備路郷土館発行の『吉備路風土記の丘ガイド』を頼りに、「立坂弥生墳丘墓」を探しに行った。倉敷から高梁川沿いに総社に行くと、やがて総社大橋にぶつかる。そこを西に曲がって橋をわたり、ずーとまっすぐ行くと、新本郵便局が右側、一里塚の名残のような大木が左側に見えてくる。そこを左に曲がるとやがて左側に協同組合ウイングバレイ(旧水島機械金属工業団地)が見えてくる。『ガイド』には無かったけど、その工業団地の入り口に遺跡公園があった。
その説明板を読んでみると、この工業団地には集落跡3ヶ所、古墳51基、製鉄遺跡5ヶ所あったらしい。古墳は横穴式。6C後半から100年くらいの間に作られたもの。3基からは鉄カスが出土。製鉄遺跡も同時期。60基の製鉄炉と16基の炭窯が確認されている。このひとつの村くらいの大きさの丘の上は古代一大製鉄工業団地だったみたいだ。時代は飛鳥時代。吉備の反乱が鎮圧されて大和政権に組み込まれた頃だろうか。
さてこの公園では沖田奥6号墳(7C前)が移築されており、高床式倉庫、炭窯、製鉄炉が復元されている。炭窯はなかなか精巧に作られている。空気穴と掻きだし穴が分けられており、この穴でまずは『白炭』を作るのである。そして製鉄炉で鉄鉱石をふいごで送風して溶かして作るのであるが、ほとんど「ちゃぶだい」位の大きさしかなかった。鉄カスがそばにあった。このとき初めて気がつく。そうかここが板井砂奥遺跡か。日本で最古級の製鉄遺跡である。千引きカナクロ遺跡はゴルフ場に、そしてここは工業団地として破壊されつくされているようだ。万が一残されていないか、工業団地を廻ってみたが、それらしきあとは全然無かった。おそろしい。古代の製鉄遺跡の重要性に気がつかなかったいうのか。歴史を動かしている要素のひとつの雄が経済だとしたら、まさにこの時代のその要、しかも現在分かっている最古級の資料だというのに。報告書だけが資料ではない。ここから見える景色、あるいは空気といったものは、壊してしまったあとではもう復元できない。鳥取や、島根で出来たこと、奈良では当然の如くして来たことがどうして岡山で出来ないのか。ああ!
気を取り直して立坂弥生墳丘墓を探しに行く。地図の上では公園から100Mと離れていない鉄加工工場のある辺りではある。工員に「弥生の墓の場所は知りませんか」と聞いてみる。全然知らない。よっぽど目立つものでない限り、たいていの住民は家の近くに遺跡が在ることを知らない。みんな古墳とは山のように大きいと思っている。しかしちょっとした盛り上がりがほとんどの古墳であるし、弥生の墓なんて盛り上がりさえないものが多い。わたしは地図で見当をつけて小山に登ってみる。墓になっている。いつの時代か知らないが巨大な仏塔もある。しかも、地蔵巡りの場所なのか十一番かそれ以降のお地蔵さんが2塔あった。ここが『聖なる場所』であることは明らかだ。ここに違いない。しかし、墳丘墓らしきものは見当たらなかった。調査は終えているはずなので、立て看ぐらい立ててくれれば良いものを。しかし、ぐるっと廻ってみて思いつく。この小山の中心を県道が通っている。この遺跡はもしかしたら道を作る時に発見されたものなのかもしない。そうだとするともう跡形も残ってはいない。しかし、ここが6Cの製鉄工場地帯だったとすると、それより300年も前に栄えていたこの場所というものはどういう意味があったのだろうか。この弥生遺跡はそれだけの謎をもって存在していたことになる。残念だ。
そのあと「ガイド」にある一倉遺跡、長砂2号墳も探してみたが、分からなかった。けれども新本川をはさんで弥生から奈良時代にかけて、ここがひとつの日本の先進地域だったという感触を持ちながら今日の『調査』は終えたのでした。
さて、製鉄遺跡年代を6C〜7Cと書いた。説明板にそう書いていたからだが、後日気になったので調べてみた。2003年11月28日発行の「たたら製鉄」(吉備人出版光永真一著)によると出土土器から7C〜8Cと書いていた。明らかにこちらが最新情報なので、こちらを信用したい。よって時代は奈良時代。吉備が大和政権に組込まれた後の操業開始だ。しかし規模は今の所吉備最大。重要性は変わらない。今、最古はやはり鬼の城麓の千引カナクロ谷遺跡(6C前半)らしい。
この本は製鉄遺跡の本としては分かりやすいが、私はあの復元遺跡をみてやっと古代の製鉄のイメージがつくれた。今日の一番上の写真にあるように製鉄炉とはこんなにも小さいのである。この下の写真は炭窯である。
|
| 2005年07月12日(火) ■ |
 |
| 見事な観光資源、高松北の遺跡を歩く |
 |
7月11日、初めてセミの声を聞いた気がしまいす。
映画ネタも尽きてきましたので、遺跡めぐりの話をちょびっとして、
読書ノートに移ります。
「見事な観光資源、高松北の遺跡を歩く」
4月10日、雨の予報を吹き飛ばす晴れ男が誰かいたのか、終始ぽかぽか天気の日曜日、「古代吉備を語る会」主催の「高松地区北部の遺跡群」の見学会に行きました。
数日前から咲き始めたさくらはすでに満開で、高松城址の桜は早々と桜吹雪を演出、野道にはタンポポ、踊子草、ホトケノザが黄色、紫、ピンクを演出し、参加者のある女性はせっせとつくしを採取し、ある女性は湿地で「イグサの原種」を摘んで小さな籠を手早く作っていました。気持ちのいい春の日、高松地区北部は賀陽(加夜)氏の本塁地の一部だったそうで、3C〜5Cの古代吉備の姿に想いを馳せた一日になりました。
最初に行ったのは生石(おいし)神社遺跡。足守と高松地区の境にある山の尾根の先にある。古代からこの場所が非常に重要な場所だったのだろう、弥生墳丘墓があったという。特殊壺の破片が採取されているが、何の型かは不明。おそらく弥生2C〜3Cの後期だろう、とのこと。10m規模の墳丘墓。はたして鉄器との関係は?この遺跡の下には足守川が流れている。
次に行ったのは、大崎廃寺跡。基壇の部分が小さな円墳のように盛り上がっています。ここからは飛鳥様式の瓦が出土したということで、飛鳥寺と同じ7Cの寺、つまり日本で最も早い時期の寺がここに存在したということになります。それだけでものすごいビッグ・ニュース。どうしてきちんと発掘しないのか不思議でならない。
その次は山道をより分け、大崎古墳群を見に行きました。古墳時代後期の横穴式石室がたくさん存在しているところです。きれいな石室がたくさんありました。大小あわせて43の古墳、全長25m以上の規模は9基、古墳時代全般にわたり、安定した地域集団(賀陽氏?)が存在していたという証拠でしょう。しかもそれがそのまま寺院造営にも繋がっていたとも想像できます。3C〜7Cにわたりこの地域では政権交代はなかったのかもしれません。
高松城址で昼食。花見今が盛りのこの時期、人出は多すぎず、少なすぎず、ここは案外いい花見スポットなのかもしれません。
次に行ったのは小盛山古墳。全長10m高さ14m3段墳丘の作り出しつき円墳。つまり「ホタテ貝型古墳」です。この大きさのホタテ貝型古墳は全国でも10本の指に数えることが出来るといいます。4C〜5Cの造営。丘陵を利用したのではなく、土を盛ったのだと見られています。作り出し部分がきれいに残っており、この方が前方後円墳に変わっていくのだなあ、と実感できました。未発掘。
次に行ったのは、小盛山から歩いて南に10分くらい行った所にある佐古田堂山古墳。全長150m高さ9mの中規模の前方後円墳です。登ってみると高松地区全域が見渡せてとても素晴らしい眺望です。日本第四位の造山古墳と同時期の築造と見られるだけに、この大きさは注目すべきだと思います。すわ、高松地区が造山古墳造営の主体かと、聞いてみたのですが、出宮さんはどうも違う見解を持っているみたいです。
そのあとは秀吉の高松城水攻め跡、蛙ゲ鼻築堤跡に行って解散。
この地区を歩いてみて思ったことは、もしこの重要な遺跡群をきちんと発掘し、学問的な重要性を全国に発信し、同時に遊歩道も作って観光資源として活かしたなら、弥生から古墳、飛鳥、戦国時代に至るまで遺跡群がひとつの地域にまとまり見事な「○○の里」的なものになるはずである。なぜ岡山県、岡山市はそういう発想がないのか。そういうことにお金を使わないのか。残念。
参加者のどなたかが言っていました。「県知事が悪いんじゃない。住民が悪いんじゃ。遺跡なにそれ?という意識なんじゃから。結局岡山県は豊か過ぎるんじゃ。観光で生きていかなくても、果物は豊富じゃし、災害はないし。」確かに岡山県では鳥取の妻木晩田遺跡のような遺跡保存運動は近年なかった。しかしそれは教育がそっちに向いていないからでしょう。鳥取の場合は片山知事の個人的なリーダーシップが強いという側面もあるでしょう。要はやはり、県の姿勢が文化面が豊かになるような方向に向くかどうかにあると思う。「吉備の地域は飛鳥地域に負けないわが国の曙の時期の最重要地域だった」そういうことを県民が知るというのは、観光云々はおいといて、お金ではとても買えないすばらしい財産になると私は思います。
(05.05.10記入)
|
| 2005年07月11日(月) ■ |
 |
| DVD「機関車先生」は65点 |
 |
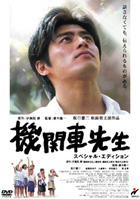 監督: 廣木隆一 監督: 廣木隆一
出演: 坂口憲二/倍賞美津子/
大塚寧々/伊武雅刀/
堺正章/佐藤匡美/
徳井優/笑福亭松之助/
千原靖史/森田直幸/
吉谷彩子
昭和三十年代、事故で声を失った先生が瀬戸内の島にやってきた。母親が昔ここにいたということもあり、島人は温かく迎える。
人物造形が一人ひとり丁寧で、特に子供がいい。しかし、肝心の機関車先生は話が出来ないとはいえ、あんなに。表情がなくていいんだろうかと心配してしまう。まあ、そういうところが島人の生活にぴったりあったのかもしれない。
淡々と出会いと別れがある。
瀬戸内のどこで撮影されたのだったけ。古い村の風景を眺める、それだけで心洗われる作品。言い換えれば、それだけの作品。
(05.07.09記入)
|
| 2005年07月10日(日) ■ |
 |
| 「ガラスのうさぎ」は80点 |
 |
 アニメ「ガラスのうさぎ」を倉敷芸文館に観にいく。 アニメ「ガラスのうさぎ」を倉敷芸文館に観にいく。
四分一節子監督、小出一巳・末永光代脚本、高木敏子原作、声は竹下景子、最上莉奈ほか。
意外にも表題の「ガラスのうさぎ」のエピソードは非常にあっさりしている。炎で溶けたうさぎは東京大空襲のことを幾らかは語ってはいるけど、そういう「象徴」では語りきれないことを、アニメの力を借りて誠実に語ろうとしたのがこの映画である。
予算と時間の関係なのだろう、描きこみはジブリアニメとは雲泥の差ではある。演出についても、少女が自殺を思いとどまったところ等、あまりにもあっさりしているように思えた。−−そうではあるのだが、私は正直ずいぶん惹きこまれた。ひとつは美術と脚本が非常に誠実だったこと。どちらも画面の隅々、台詞の一言一言に神経を配りまくり、当時を忠実に再現しようとしているのが良く分かった。ひとつはいままでの反戦アニメにあるように、終戦で終わりということにしていなかったこと。戦後の苦労もきちんと描いており、だからこそ「新しい憲法の話」の朗読が活きた。
悪い作品ではない。500人規模で人を呼んでも、充分満足させうるアニメである。
終わった後、会場すぐそばの倉敷美観地区をそぞろ歩いた。倉敷ガラス工芸、黒木三郎の寄せ木細工、備中和紙、ちっちゃなからくり玩具、等々店先の可愛い民芸品を眺めて歩き、雨にけぶる倉敷川を見ながら休んでいると、この倉敷の美しさを戦後最初に説いたのは皮肉にも外国人のバーナード・リーチだったなあ、と思い出した。偶然にも戦災を免れたため、この美しさが保たれたのだ。倉敷でこそ、九条は似つかわしい。倉敷九条の会を作ろうとしているらしいが、呼びかけ人はぜひ大原美術館の大原氏を、それが無理ならこの美観地区ゆかりの人を選ぶべきだと思う。
|
| 2005年07月09日(土) ■ |
 |
| 「リチャード・ニクソン暗殺を企てた男」は75点 |
 |
 監督 : ニルス・ミュラー 監督 : ニルス・ミュラー
出演 : ショーン・ペン
ナオミ・ワッツ
ドン・チードル
1973年、サム・ビックは、別居中の妻マリーと3人の子供を取り戻すため、事務器具の販売員として再就職する。しかし、不器用なサムは成績も伸びず、口先だけの営業を強いられることに不満を感じていた。ある日、裁判所からマリーとの婚姻解消通知が届く。新ビジネスのためのローンも却下され、追い詰められたサムは、ふとウォーターゲート疑惑の報道を耳にした。サムにとってニクソン大統領は、正直者が成功するアメリカの夢を踏みにじった男の象徴だった…。
サム・ビックと私は紙一重、ではない。妻に離婚を迫られ、人付き合いが下手で、思い込みが激しく、変な正義観を持ち、上司からはねちねちといじめられ、構造的な貧乏は容赦なく彼に忍び寄る。そうだからといって、彼は妻の恋人も殺せないし、上司も殺せない。怒りの矛先はゆがんだ正義観からニクソンに向かい、結果的には無実の人を何人か殺す。犯行前に思い通りに殺せたのは唯一自分に慕ってくれていた飼い犬であったというのは皮肉である。
彼と私はいっしょではない。断じてないと自信を持って言える。ただ、彼がかわいそうだ。可哀そうだ。あわれだ。
ミュラー監督は新人監督らしい。非常に手馴れた演出。次回作が楽しみ。
(05.07.06記入)
|
| 2005年07月08日(金) ■ |
 |
| 「恋愛中毒」は70点 |
 |
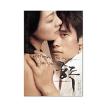 純愛中毒 (通常版) 純愛中毒 (通常版)
製作: 2002年 韓国
監督: パク・ヨンフン
出演: イ・ビョンホン/イ・ミヨン/
イ・オル/パク・ソニョン
同時刻の交通事故がきっかけで、イ・ミヨンの最愛の夫の魂は弟のイ・ビョンホンの身体に宿った?
構成は東野圭吾原作の「秘密」に似ている。(こっちのほうが複雑だか)イ・ミヨンが案外演技派である。注目。
ところでイ・ビョンホンがあと五年位しておば様から騒がれなくなったとき、転進の方向として、かっこいい悪役をするというのはどうだろうかなと思う。私はこの人の雰囲気に手塚治虫「バンパイヤ」で見事な転身を遂げたロックの雰囲気を感じ取る。ぺ・ヨンジュンが手塚作品の中ではケンイチ君だとしたら、ロックは洋行帰りで、かっこよく、なおかつ暗いイメージも併せ持っているという主人公を演じていたところなんかそっくり。
原作をうまく料理する韓国のことだから、いっそ「バンパイヤ」を韓国でやったらどうだろう。今ならCGで違和感なくトッペイを狼に出来るぞ。あの作品のロックが、ロックの転身第一作だったのだから、イ・ビョンホンにぴったりだと思うのだが。
(05.07.08記入)
|
| 2005年07月07日(木) ■ |
 |
| DVD「天国の本屋〜恋火」は50点 |
 |
 監督: 篠原哲雄 監督: 篠原哲雄
出演: 竹内結子/玉山鉄二/
香川京子/香川照之/
原田芳雄/香里奈
この監督の作品「深呼吸の必要」を見たときには、この人確信的に恋愛物語を避けたのだなと思ったのだが、この作品を見たあと、監督の作品グラフティを眺めて、(私の実際に見たのは「はつ恋」「死者の学園祭」のみだが)この監督恋物語苦手なんだなあと思った。
「一緒にこの花火を見ると恋人になれるという伝説」でもって宣伝していたこの作品であるが、内容は恋物語とは無縁。想いのすれ違い。という古典的テーマを天国まで話を持っていって、「花火」という映像的な力と、作曲されたピアノ曲という映画ならではの力で、ラストを飾るとどうなるかなあ、という監督の実験作品である。しかもラストのカットは「竹内結子」というのりにのった女優のアップで締めるという「決め」もやってみました、という作品。
ただし、監督の思いは上滑りしている。こういう想いをファンタジーで処理されてはかなわないと私などは思う。
(05.07.02記入)
|
| 2005年07月06日(水) ■ |
 |
| 「電車男」は70点 |
 |
 監督 : 村上正典 監督 : 村上正典
出演 : 山田孝之
中谷美紀
国仲涼子
瑛太
思ったよりよかった。
ただ話があまりにもとんとん拍子に行き過ぎる。もう少し波瀾万丈があったほうがよかったかも。
「乱暴されている娘を助けたあと恋が生まれる」という古典的題材をだれることなく見事に料理しているし、いくつか成る程という展開もある。(娘は単にサイトの助言に踊らされていたわけではないというエピソード、あるいは付箋紙のエピソード)
この監督の次回作が楽しみ。
(05.06.20記入)
(05.07.06一部つけたし)
|
| 2005年07月05日(火) ■ |
 |
| DVD「マッハ!!!!」は75点 |
 |
 マッハ!!!! マッハ!!!!
製作: 2003年 タイ
監督: プラッチャーヤ・ピンゲーオ
出演: トニー・ジャー/ペットターイ・ウォンカムラオ/
プマワーリー・ヨートガモン
テレビの宣伝では隠れて見えなかったが、本邦初ムエタイ映画である。主人公が耐えて、耐えて、やっと本領を発揮するところ、いかにも怪しげな悪役、次々と現れる相手、このあたりは亡きブルースリー映画の精神である。面白かった。サービス精神はジャッキー・チェーンを受けついている。そして、CGを使わない潔さ。(目が燃える所は唯一使っているように思えたが。)イヤー面白かった。
タイの風俗映画としてもよくできている。
(05.06.28記入)
|
|