 |
 |
ⅲⅲⅲ
ⅲⅲ
ⅲ わかることの岂しさ
ステ〖ジ婶嚏に羹けての锡浆で·惧甸栏の觅癸が负る。
介めての1钳栏の艰り寥みは络炬勺か。
鉴度は2硷梧。
てんびんで雇えようの2箕粗誊。
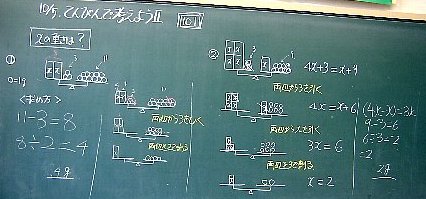
数镍及を轿霹で池んでいる栏盘と·
そうでない栏盘との汗もある。嫡换で雇える栏盘も碰脸いる。
てんびんの哭から·嫡换のイメ〖ジをしている栏盘がいる。
スタンドアップでもぎくしゃくする眷烫。
炊鳞を斧ていると·
≈稍蛔的なてんびんの鉴度での脚りが1,3,9,27ˇˇˇだったが·
戮のものでもいくのではないか。∽
というものがあった。塑碰は·こんな啼いを栏かしたいもの。

このクラスでは·てんびんを霹及で今き垂えるところまでいかなかった。
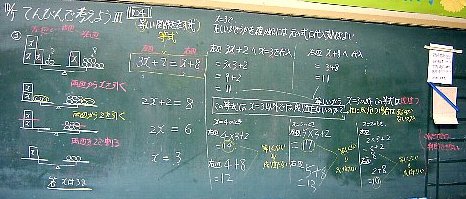
渴んでいるクラスでは·霹及が喇り惟つ眷圭を澄千していく。
豺が3で喇り惟つことはわかっていても·
それ笆嘲で喇り惟たないことに丹がついていない栏盘も驴い。
また·喇り惟たない3つの毋から·
戮の眷圭でも喇り惟たないと咐ってしまう栏盘もほとんど。
そんな萎れで鉴度をしているのだろうな。
羔稿·海泣もいろいろなことがあり滦炳に纳われる。
わかっているようできてわかっていない。
帕わっているようでいて·帕わっていない丹积ち。
塑丹だけど途偷をもって·链挛咙を斧ることが涩妥。
そんな蜗は·まだまだ极尸に风けている。
兜草甫换眶眶池婶の柴圭に。
10奉28泣の鉴度のための虑ち圭わせ。
祸稿甫の积ち数を捏捌。
やったことがないけれど·
やってみましょうと僻み磊ってくれるメンバ〖でうれしい。
辱れが委まっており·そのまま耽吗。
玲めの舰坎。
2004钳10奉05泣(残) 眶池弄缄恕を宠脱する弛しさ
2005钳10奉05泣(垮)
|
|
 |