 |
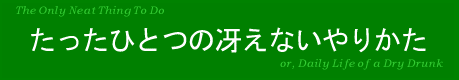 |
ホーム > 日々雑記 「たったひとつの冴えないやりかた」
たったひとつの冴えないやりかた
飲まないアルコール中毒者のドライドランクな日常
もくじ|過去へ|未来へ
2010年05月12日(水) 適者生存 いろいろな人種が混じって住んでいるアメリカでは、白人の多いミーティングもあれば、黒人の多いミーティングもあるのだそうです。町の中心部の黒人居住地帯では、当然黒人ばっかりのミーティングになり、郊外の住宅地のミーティングでは白人ばかりになります。例えば白人の人の、たまたま一番近い会場が黒人の多い会場だったりすると、そこをホームグループにはせずに、ちょっと離れていても白人の多い会場に行くようになるのだとか。
人種以外にも、職業とか、AAプログラムの解釈によって、相性の良い人たちが集まってグループを作っているのだそうで、これを「適者生存」と呼びます。
適者生存とは、進化論で「その環境に適した形態を持ったものが生き残り繁栄していく」という考え方です。
ちょっと僕の周りを見渡してみても、いろいろなAAグループがあります。
例えば僕の属しているグループは「AAとして最もオーソドックスなところを目指す」とか言っちゃってビッグブックしか使いませんし、「仲間」も大事ではあるんだけど、それより「原理」を重視し、ミーティングでも神とかハイヤーパワーという言葉が普通に出てくるし、スポンサーシップを持たないなんてあり得ねえ、という態度です。
けれど、仲間の交流こそAAの原理だと解釈しているグループだってあります(そういうグループのミーティングでは神という言葉は刺身のツマみたいなもんです)。あるいは、ステップ!ステップ!とうるさいことを言わず、ミーティングでもアルコールの話はほとんど出てこなくて、ともかく毎週のミーティングに来て酒をやめ続けることが大事なんだという気楽なグループもあります。
広く見渡せば、生活保護の人ばっかりの会場もあれば、サラリーマンばかりのところもあります。男ばっかりで汗くさい(比喩的な意味で)会場もあれば、ほとんど女性ばっかりというグループもあります。
いろんな雰囲気、いろんな特性を持った会場やグループがあり、その環境に適した人がその会場に残って、ますますその雰囲気を強めていくわけです。だから、ビギナーには「なるべくあっちこっちへ行って、自分にあったところを見つけるように」というアドバイスが必要です。
当然僕は「自分のグループのやり方が最も正しい」と思っているからこそ、そういうグループのメンバーをやっているわけですが、その一方で「AAグループのこのバリエーションがAAの魅力のひとつであり、多様性がAAの永続性を保証してくれる」とも思っているわけです。生物学をかじったことのある人ならば、均一性が脆弱性を、多様性がロバスト性を意味することを理解して頂けるでしょう。
話は変わって、僕は先日出張で韓国に初めて行ったのですが、その経験を持ってして「韓国のことがすべて分かった」つもりになったら「単なるバカ」と思われるだけでしょう。たった数日の滞在でその国の全体像を把握することはできないのですから。だから、外国の土産話を聞く人たちは、その内容が局所的なことにすぎず、その国全体の話とは限らないことを、きちんと分かっていて聞くわけです。
けれど、これがAAとなると不思議な現象が起こります。わずか一つか二つの会場に数回出席しただけの人が、AAのことをすべて理解したかのように「AAとはこうである」と説明し、聞く方もそれをAAに関する普遍的な真実であるかのように解釈します。AAについては様々な誤解が存在していますが、その多くはこうした「AA土産話」が広がった結果です。群盲象をなんとやら、というやつです。
AAメンバーの中にも、この多様性が強さであると理解しない人たちがいるのは残念なことです。
2010年05月11日(火) この半年 11月
ミーティング 8
病院メッセージ 1
委員会 2
イベント 2
ステップを渡す 1
12月
ミーティング 7
ステップを渡す 2
1月
ミーティング 7
委員会 1
ステップを渡す 4
2月
ミーティング 6
委員会 1
イベント 1
ステップを渡す 3
3月
ミーティング 7
病院メッセージ 2
イベント 1
ステップを渡す 2
その他 1
4月
ミーティング 9
委員会 1
2010年05月10日(月) 近況 用事があって断酒会におじゃましました。
火事で三人が亡くなった事件のことが話題になっていました。依存症で最近退院された人だったのですが、焼けた家の中でご本人が、それとお墓の近くで燃えた車の中からご両親が発見されました。死因はそれぞれ一酸化炭素中毒と焼死。新聞やテレビで事件のニュースが流されましたが、依存症のことについてはひと言も触れられていません。
今日は「どうしてこのような悲劇が起きたのか、それを知らせねばならんのだ」という話を新聞記者にしてきた、と会長さん。
ここの断酒会は野菜の産地にあり、行くたびに野菜をおみやげに頂いてきます。今回も「ブロッコリーいらねえか?」と聞かれました。僕はブロッコリーが大好きなので「ぜひ頂きます」と答えたのですが、ブロッコリーはブロッコリーでも、ブロッコリーの苗でした。それを十数本もらってしまったのです。
「30センチ間隔で植えればいい。肥料は野菜用の三要素のやつでな」
三要素って窒素、リン酸、カリウムだっけか。
借家の狭い庭はすでにイチゴやらハーブで埋まっているのですが、なんとか隙間を見つけて数本植え付けました。それでもまだ半分あります。実家の田植えに行くついでに持って行って、カーネーションと一緒に母に渡せばいいや、と思っていたのですが、持って行くのを忘れてしまいました。「お前のやることはいつもそうだ」とは母の言葉です。
さて、どうしたもんだ。
庭を持っているスポンシーに「ブロッコリーの苗いらない?」と電話したところ、近くまで来てくれるというので、近所で待ち合わせしました・・・が、そこへも苗を忘れていってしまい、結局我が家に来てお茶を飲みながら少し話をしました。
彼がAAに来たのは5年前ですが、当時は彼が今のように「スッキリとなる」とは想像もつきませんでした。最初は再飲酒もあったし、その後2年間は酒は止まっていたものの、処方薬の多用が続いていました。そのスッキリしない状態でもミーティングに通い続けたからこそ、その後の彼があったのでしょう。スッキリしだしたのは、薬の乱用をもとにソーバーをリセットして断薬し、ステップをもう一度1からやり直してからでした。おそらく断薬とステップの相乗効果だったのでしょう。
あのころ彼が患っていた「うつ」が、本当の?うつ病だったのか、それともアルコール性のうつ症状(や安定剤の相反作用)だったのか、両者の混合だったのか。それは今の僕には判断がつきません。ともかくアル中の「うつ」は治りうるものなのだ、というひとつの証拠を示してくれます。
ブロッコリーは順調にいけば2ヶ月ほどで収穫できるそうです。
2010年05月03日(月) 行ったり来たり AA日本ニューズレターは、AAのJSOが隔月で発行しているニューズレターです。一部70円なのですが、PDFでよければ AA JSO のサイトからダウンロードして読むことができます。
中身は「回復」よりも、AAを維持し動かしていくための話が多いので、AA外の人にはあまり興味を持たれる内容ではないと思います。が、その 最新号 に山梨の大河原先生が常任理事退任の挨拶文を寄せていらして、読んで感銘を受けました。それを引いてこの雑記を書くことにします。
スリップ(再飲酒)する人たちは、「またふつうに飲めるようになる」という妄想を捨てられずに酒に手を出していると説明されます。けれど何度か試してみれば、それができないことは体験的に学習できます。
ふつうに飲めないことを知っていながら再飲酒を繰り返す人たちは、何を考えているのか。それを説明してくれるのが大河原先生の文章です。それは「ここで飲んでしまっても、またやめればいい」「回復はいつでもできる」という考えです。飲酒と断酒の間を、何度でも自由に行ったり来たりできると信じているというわけです。
「今回の再飲酒は精神病院への入院とか大変なことになる前に酒が止まって良かった」などと(ちょっと嬉しそうに)言われると、こちらは<とほほ>な気分になります。
AAで何年も酒をやめているメンバーが、「もし次飲んでもまたAAに戻ってきて酒をやめます」と真顔で言ったりすることもあります。次回も戻ってこれると無邪気に信じているわけで、実際、戻ってこられる確率のほうが高いのかも知れませんが、戻って来られない確率も少なくありません。
(断酒の側に)戻ってくるつもりってことは、(飲酒の側に)また行くつもりということでもあります。「飲んでもまたやめればいい」というのは、飲んでしまった人に慰めを与え、再起を促す言葉であって、断酒している人が使えば、将来の再飲酒をあらかじめ言い訳しておくための言葉になってしまいます。
つまるところ、酒をやめるんだったら一生断酒するしかありません。けれど、ゼロか100のどちらかしかないアル中さんは、一生酒をやめるなんて無理だから飲み続けると言い出します。「一日断酒」という言葉は白と黒の間にグレーを作り出す装置なのでしょう。ではあるものの、次回のソブラエティではなく、今回のソブラエティを大事にするのが基本というわけです。
2010年04月29日(木) リハビリ 僕が子供のころ、実家でヤギを飼っていました。
雌ヤギは乳を搾り、雄ヤギは種ヤギとして種付け料が父の副収入になっていました。種付け料はヤギの血筋によって決まるらしく、良い血筋の雄ヤギを確保することが収入アップにつながるのでした。
ある時、峠の向こうに良い雄ヤギがいると聞いた父は、軽トラックに雌ヤギを積んで出かけました。そのヤギに種を付けてもらって雄ヤギを生ませる算段でした。しかしあろうことか、冬の凍結した峠道で車を正面衝突させてしまい、膝蓋骨(膝の皿)を折る大けがを負いました(ヤギは死んだそうです)。
退院してきた父は、天井から紐をつり下げ、米を入れた一升瓶を足にくくりつけてリハビリに努めました。それは相当痛かったようで、脂汗を流しながらリハビリに励む父の姿を今でも思い出すことができます。父が農業の力仕事ができるようになるまで回復するには、一年近くが必要でした。
話は変わって、アルコール関係で知り合ったある人のことです。
彼は過剰服薬(OD)をやって救急車で運ばれました。幸い一命は取り留めたものの、意識を失っている間に足が変な角度で曲がっていたため、血行が悪くなり、片足に機能障害が残りました。
その足はかなり痛み、無理に動かそうとするとさらに痛くなるのだそうで、理学療法士が勧めても「痛いから」という理由で彼はリハビリに熱心に取り組みませんでした。やがて足が徐々に回復し、痛みが取れる頃になってリハビリをやろうとすると、「動かさない状態で長く経過してしまったので、今さら機能回復は望めない」と突き放されてしまったのだそうです。
何にせよリハビリというのは痛かったり苦しかったりするものです。しかし、痛いから、苦しいからとリハビリを避けていては機能回復が望めなくなってしまいます。
うつ病においても、難しいのはリハビリなのだそうです。薬を飲むことは難しいことではありません。うつ病が社会に認知されるようになったおかげで、仕事を休むことの必要性も理解して貰えるようになりました。つまり、薬を飲むこと、休むことは比較的簡単なのですが、問題なのはリハビリです。
元々苦しいことを無理して続けてきたのでうつになった、と言えます。リハビリというのは、その環境に徐々に戻っていくことです。ところが、足の関節と同じように、社会的機能も使わなければ徐々に衰えていきます。健康な時には、膝を曲げることも歩くことも痛くなかったものが、怪我をした後はそれが脂汗が流れ落ちるほどの苦しみに転じてしまいます。けれどそれを経なければ機能回復がありません。つまり、リハビリというのは強いストレスなのです。
昨日まで休職して家にいた人が、いきなりフルタイムの仕事に復帰するのは無理な話です。それは動かない膝を無理に動かして農業をしろというのと同じです。結果としてうつがぶり返すことが多く、再び休職どころか退職ということになりかねません。やはりリハビリ期間は必要だし、しかもそこで焦って無理をしても、その期間はなかなか短くなってくれません。
逆にリハビリの辛さを回避する人たちは、「元々苦しいことを無理して続けたせいでうつになったのだから、こんな辛いことをしてはまたうつがぶり返す」と言います。そうやってリハビリを回避し続けた挙げ句、機能回復が難しくなっていきます。つまり「うつをこじらせてしまう」わけです。
満員電車に揺られて会社の近くの図書館に「出勤」し、そこで8時間過ごして帰ってくるとか。出社するだけで仕事をせずに会社に7時間いろとか。残業制限があって、仕事が終わらなくても帰らなくちゃいけないとか。そこに辛さや苦しさがあるのは当然で、それを飛び越していきなり日常生活には戻れないものなのです。その間にぶり返しがあっても、地道にリハビリを積むしかないのでしょう。
アルコール依存症もリハビリが難しい病気という点では同じだと思います。精神病院から退院していきなり仕事に復帰という例もありますが、皆がそううまくいくわけではなく、無理をすれば簡単にぶり返します。
そういう意味では、AAという自助グループはリハビリのためのグループと言えます。その人の社会的機能を回復させる役割があるわけです。やはり最初のうちはリハビリに時間を割いた方が良いし、そのほうが後々の人生を楽しめると思います。
unpaid work だって仕事なので、部屋を片づけることだってリハビリのひとつだし、それで疲れ果てるというのも僕も経験しています。大変だけどガンバってね、と応援するしかありません。もちろん、社会的機能は仕事ばかりではなく、様々なことがあります。見知らぬ人と話をすることだって、最初はなかなかできないものなのですから。
金銭や名声が幸せをもたらすとは限らないのですが、最低限の経済的安定や人間関係がなければ、幸せはとても難しくなります。同じように、幸せであるためには「何でもできる」必要はないのですが、ある程度のことはできなければ難しいと思うのです。
2010年04月21日(水) 刑法39条 刑法は犯罪に対する罪を決めていますが、同時に様々な理由で刑を減免しています。なかでも目立つのは責任能力がないものは罰しないという規定です。
一番分かりやすいのは14才未満の少年の罪を問わない刑法41条の規定。極端な例を挙げると、ロシアで両親が泥酔している間に3才の姉が新生児の弟を殺してしまう事件がありましたが、3才の少女の罪を問えないことは常識的に理解できます。
すでに削除された刑法40条は、いん唖者に対する減刑を定めていました。聾唖教育が未発達だった時代には、聴覚障害者は言語の獲得が難しく、そのため精神的に未発達な人が多かったのがこの条文の理由ですが、教育の発達した現代では聴覚障害者だからといって一律に減刑の対象にする必要がなくなったというわけです。
刑法39条は、心神喪失者は不処罰、心神耗弱者は減刑と定めています。最近は重大な事件が起こると、弁護側の主張の中に「心神喪失による無罪あるいは減刑」が含まれていることが珍しくなく、判決が責任能力の有無をどう判断するかが注目されます。それに関してよく聞く話が、精神障害者の犯罪のほとんどが不起訴になるという噂です。実際僕もその噂を信じていたのです。
うつ病の当事者として体験発表を依頼されたことがあり、その時に控え室で昼食を食べながら精神科医の先生の話をうかがいました(ようは雑談を脇から聞いていただけ)。話題は精神障害者の犯罪についてで、その9割が不起訴になる現状を嘆く話でした。もちろん、先生は9割が不処罰になることをけしからんと言っているわけではありませんでした。ほぼ自動的に不起訴になる仕組みでは、正式な裁判によって無罪(犯罪の事実がない)ことを証明する機会を奪ってしまう、障害者の裁判を受ける権利が侵害されていることを問題として取り上げていたのです。
実はこの9割という数字は、犯罪白書に心神喪失・心神耗弱と認定された者だけを母数にした数字として9割と掲載されたものでした。ところが、この9割という数字が精神障害者全体に拡大されて一人歩きしてしまったようで、僕も誤解していました。
精神障害者「不起訴9割」は誤解
http://homepage2.nifty.com/whitehole/db/4book/020703yomi.html
全体の起訴率が58%に対し、精神障害者の起訴率は46%。
殺人と殺人未遂に限ってみても、全体が58%、精神障害者は50%。
確かに一般に比べれば起訴率は低くなっていますが、極端な差があるわけではありません。
ひょっとするとあの時の先生の話も、精神障害者全体ではなく、心神喪失・心神耗弱という認定を受けた人だけに絞った話だったのかもしれません。(だとすれば僕がバイアスのかかった聴き方をしていたわけです)。確かに単純に不処罰とするのではなく、犯罪の事実があったのかどうか裁判で事実認定をしたあと、有罪であった場合のみ減刑する仕組みが本来であろうと思います。
実は以前AA関係の知り合いが泥酔して暴行事件を起こし、依存症での入院履歴もあったおかげで不起訴になったことがありました(依存症以外の病気はなかったはず)。その後彼は規定によって強制入院となり(医療観察法の施行前だったものの)数ヶ月で退院というわけにはいかず、久しぶりに顔をみた頃には拘禁症で見る影もない状態でした。結局外で暮らすことができずに病院に戻ってしまいました。もし彼が懲役に行っていたら結果は違ったかも知れないと思うのです。
というわけで、特に結論を導くでもなく終了。
2010年04月20日(火) 不全感の進行 12&12では、人間の欲望(本能)を、社会的共存・(物質的精神的)安全・性の三つに分けて、いずれも人間が生きて行くには欠かせないもの(神から与えられたもの)と規定しています。つまり欲望があるのは健康なことです。
しかし、人は時に長期的展望を欠いたり、視野が狭くなったりすることがあり、すると欲望を過剰に満たそうとします(あるいは必要なだけ満たすことを否定し過度に禁欲的になる)。例えば名声欲にとりつかれるのは社会的欲望の暴走で、部屋が片づかないのは物質的精神的安定を求めすぎた結果だと言えます。そして、どれかひとつの本能を優先するとき、他の本能が犠牲にされます。
自分の中でこの三つの欲望(本能)のバランスが崩れたり、他者の本能とのせめぎ合いが起こるとき、私たちはトラブルに巻き込まれます。けれど、それは何もアル中だけに限りません。世界中の人たちが同じように欲望のせめぎ合いの中で生きています。けれど、なぜAAの12ステップがこの仕組みを強調するのでしょうか。
以前に、「アル中は自分に都合の良いものを、自分に都合の良い方法で、手に入れようとする。だから彼らが最も聞きたくない言葉は No だ」という言葉を紹介しました。また、ビッグブックには「私たちアルコホーリクは、自己規制力をあまり持たない」とあります。
つまり、アル中というのは、自分の中の三つの本能のバランスを取ったり、自分と他者の欲望のバランスを調整する能力が低いわけです。自分の欲望を満たそうと他者を犠牲にする一方で、常に自分は状況の犠牲者だと感じてもいます。
欲望が満たされないとき、人は怒り(恨み)を感じます。欲望が満たされない予感があるとき、人は不安(恐れ)を感じ、それが怒りに転じます。欲望の調整能力を欠いたアル中は、不安に支配され、怒りを持ちやすい人間だと言えます(そして怒りはやがて鬱に転じます)。
ところで「幸せ」とは何でしょうか。分かりやすいのは、欲望が満たされること=幸せという考え方です。人に尊敬されること、親切な人たちに囲まれること、金銭の不自由なく、ものに恵まれること、性的にも満足して、健康で利発な可愛い子どもがいることなどなど。こうした欲望の充足が人生の目的なのでしょうか。もちろん、最低限の必要が満たされなければ、幸せはとても難しくなります。けれど、ひたすらそれでいいのか?
12&12にはこんな文章もあります。
「人生の主な目的は人間の基本的欲求の充足にあるという信念」
「この信念によって生きようとして一番失敗したのが、私たちアルコホーリクなのだ」
これは何を意味するのか。どんなに恵まれた人でも、満たされない欲望を抱えているものです。もし人生の目的や幸せが、欲望を満たすことだとするなら、この世の中には生きる目的を果たした人も、幸せな人もいないことになります。しかし、世の中には完全には満たされていないのに幸せな人たちがいるのです。
結局アル中は、満たされないことへの不満や不安が人一倍強いのではないか。しかもその欲望は長期的展望や、他者との関係の視点を欠いた近視眼的なものではないか。そうした絶え間のない苦痛にさらされているからこそ、アルコールの陶酔がもたらす一時的な万能感(完璧な充足感)を「幸せ」だと勘違いして深くハマったのではないか。
だからこそ、肉体的な渇望(飲酒欲求と呼ばれるもの)が去った後でも、調整に失敗した欲望のもたらす不全感が、アルコールが与えてくれる幼児的万能感(つまり再飲酒)へと引き戻そうとし続けているのではないか。
というのが僕のとらえ方なのです。なので僕の棚卸しは、欲望をどれだけ満たすのが適切かという観点に基づいています。
単に酒をやめただけでは、満たされない不満、不安、不全感は解消されないどころか、かえって悪化するでしょう。というのも、いままで一時的であれそれを解消してくれたアルコールを使えなくなってしまうからです。(その意味では酒を飲んだからこそ生き残って来れたとも言えます)。
やはり何かの手段で本能を調整し、欲望が適度に満たされれば幸せであると感じられるようにしていく必要があります。そしてその手段のひとつが12ステップです。もちろん、12ステップ以外にもその方法はあるでしょう。ただそれが、内省と自己鍛錬などと大げさなものでなくても、何らかの軌道修正を日々行うものであろうとは思うのですけど。
この不全感は放置しておくと拡大するもののようですが、それは「不満はたまるもの」と考えれば当然かもしれません。飲まないだけで何もしなければ、おそらくこの「恨みがましさ」は拡大していくのでしょう。そして、それは再飲酒の引き金にもなるし、飲んだ後のトラブルを拡大させる原因にもなります。
前に「飲まなくても病気は進行する」という話を書き、では病気のどの部分が進行するかについて掲示板にも少し書きました。けれど書き漏らしたことがあったので、あらためて書いた次第です。つまり、
「飲まなくても、不全感の部分は進行し、悪化していく」
(ことがある、くらいにしておくか)。
下りのエスカレーターを歩いて上っているたとえ話がありましたが、まさにあれです。
2010年04月16日(金) 断酒しても進行する? すべてのアル中さんが毎日飲んでいたわけでないにしても、たいていは毎日酒を飲んでいた時期があったと思います。
アルコール依存症は進行性の病気だと言います。進行性で最後には死に至るものの、断酒によってその進行を食い止めることができる・・・と説明されることが多いのではないでしょうか。
けれど、断酒を続ければ依存症という病気の進行は完全に食い止められるのでしょうか? どうもそうではなく、断酒を続けていても病気のある部分は年月とともに着実に進行していくように思えてなりません。AAの仲間と話していても、「飲まなくても進行する」と考えている人は確かにいます。JoeMの本にも同じことが書かれていて、アル中は世界中同じなのかと思いました。
例えば1年間毎日飲んでいれば1年(365日)ぶん病気が進行するとします。では1年のうち1ヶ月しか飲んでいなければ、同じ1年でも30日ぶんしか進行しないのか? どうもそうならないようで、確かに毎日飲むのに比べれば進行は緩やかなものの、やはり病気は酷くなっているようです。それどころか、完全な断酒を1年続けても、やっぱり病気はいくぶん進行しているように思えます。
頭ではこんな風に考えます。10年毎日飲んでいたのなら、365×10=3650日ぶん進行したはずだ。断酒を決意し、完全な断酒は無理だったものの、その後の1年で1ヶ月しか飲んでいないのなら、(前の10年間に比べれば)ほんのわずかしか進行していないはずだと。
ところが、再飲酒を始めてから、飲酒が酷くなる(例えば連続飲酒とか)になるまでの期間や、再飲酒の間隔は、次第に短くなっているように見えます。3650日ぶんの進行と、30日分の進行が、ほぼイコールにしか思えない場合があるわけです。
つまり、
断酒していても依存症は進行する。
と考えた方が自然です。
しかしこれには異論が出ています。それは「毎日飲んでいた頃は、たいしたトラブルも起きなかった。なのに酒をやめようと四苦八苦するようになると、酒量も増え、トラブルも増えた」というもので、つまり「酒をやめる努力をすると、依存症の進行が加速する」という説です。(これには、なまじ酒をやめる努力なんかしない方が良い、というニュアンスが含まれるのかもしれません)。
どっちの説にしても、「再飲酒すれば元の飲んだくれに戻る、どころかもっと酷くなっている」と考えていることは一致しているわけですが。
2010年04月14日(水) 準備ができるまで 僕は20代を東京の調布で過ごしました。大学を中退しフリーランスのプログラマーをやっている間に何度か引っ越しましたが、住み慣れた調布を離れませんでした。やがて自殺未遂をきっかけに長野の実家に戻ることになります。AAにつながるのはその4年後、今回のソブラエティはそのさらに1年後からです。
JSOで全国のミーティング会場の一覧表を作っています。ある時それをめくっていると、過去に住んでいた調布にもAAグループがあり、カトリック教会でミーティングをやっていることが分かりました。
いったい何度その教会の前を通り過ぎたことでしょう。何も知らずに、酔っぱらったままで。もしあの頃に自分がアル中だとわかっていて、その会場を訪れていたら、自分にはまったく違った人生があったのではないか。長野に戻る必要もなく、仕事を続けることもできたのではないか。あの当時持っていた夢を諦める必要はなかったのではないか?(まあその夢は今となってはかなりどーでもいい夢ですけど)。
自殺未遂で運ばれた救急病院の医師に、精神科を紹介してくれと頼んだのですが、そのとき示されたリストから、AAがメッセージに入っていた病院を選んでいたら、やっぱり違う人生になっていたかもしれません。そう考えると、人の人生は、小さな選択で大きく変わりうるものです。
飲まなくなった後も、「どうせ酒はやめるにせよ、違う人生もあり得たのでは」という後悔に結構つきまとわれました。財産や社会的地位をあまり失っていない人を見るたびに、羨望が自分の過去の選択、過去の無知に対する後悔をかき立てました。
けれど今では分かっています。自分がアル中だと知り、AAの存在を知っていたとしても、当時の僕が教会のドアを開けることはなかったでしょう。AAの病院メッセージに触れたとしても、「くだらねぇ」のひと言で済ませていたでしょう。あのころの僕は、
まだ準備ができていなかった。
それ以上でも、それ以下でもありません。物事には正しいタイミングがあり、そのタイミングを自分の都合に合わることはできません。
謙虚さというのは、強いられて選ぶだけでなく、自ら進んで選び取ることもできるものだそうです。それは自分の人生も同じでしょう。僕は自分の人生の有り様を、仕方なく受け入れることもできるし、喜んで受け入れることもできます。もう「別の人生だってあったはず」と考えてほぞを噛むこともありません。
ちなみに、調布の会場は現在は別の場所に移っているようです。
2010年04月13日(火) 自立しない中年男たち たまちゃんのブログ に 朝日新聞の切り抜きを載せたエントリ があります。
話は「親の婚活」なので、この雑記の守備範囲とは無縁ですが、そこに信田先生の話が載っています。携帯で読んでらっしゃる方のために、該当部分を丸ごと引いておきます。
−−−−
母子関係などに詳しいカウンセラーの信田さよ子さんは「『子どもが自立しない』という、シニア世代の母親からの相談は少なくない。でも、そういう自分自身が子どもを縛り付けていることに、気づいていない人が多い」と話す。
経済的には自立できるのに、社会人になっても同居させ、食事から洗濯までしてあげているのは、母親自身という指摘だ。「就職したら自活させる。収入が少なくて一人暮らしができないなら、家事を分担させるなど、親も子も、ある種の境界を設けるべきです」
−−−−
なんでこの部分に目が止まったかというと、AAやその周辺を見渡してみて、やっぱり「中年男が親と同居しているパターンは難しい」と感じるからです。
高齢者の家を訪ねることの多い介護職員の話も載っています。中高年・独身・無職で、老齢の母親と同居、生活費は亡くなった父親の遺族年金。これで母親が亡くなったらどうやって暮らしていくのか・・・。
僕は実家で飲んでいた頃に母親から「夫婦だったら別れられるけど、親子の縁は切れないからねぇ」と嘆かれたことがあります。作った子供にPL法は適用されないはずなんですが、かように母親というのは製造者責任を(取りたがる|取らされる)ものなのです。
「ぬるま湯につかる」という言葉があります。「気も意欲も持たず、現在の境遇に甘んじてぬくぬくとくらす」という意味です(広辞苑)。男子にとって実家はまさにぬるま湯そのものです。風呂が熱すぎても冷たすぎても、入った人はすぐに飛び出します。ほどよく熱ければ身体が温まって出て行きます。しかし、ぬるま湯というのは熱くも冷たくもないのでいつまでも入っていられます。かといってホカホカに暖まらないので、出ればカゼを引きそうな気がして出られず。おまけにぬるま湯は、徐々に冷えていくのです。
実家は快適かというと決してそんなことはないものです。家族の胃袋を握っている主婦(この場合は母親)というのは「権力者」です。機嫌を損ねて飯や風呂や洗濯の世話をしてもらえなくなったら大変なので(ぬるま湯が冷水に一変するので)なかなか逆らえないわけだ。え? それは普通の夫婦関係でも変わらない? そうかもね。
お母さんとしては「息子に一人暮らしをさせて、飲んだくれて世間様にご迷惑をおかけしては申し訳ない」という気持ちなので、そこは夫婦関係と違うんですけど。
実家から出れば必ず良い方に向かうか、と言えばそうとも限らないのが難しいところですが。
実はアクティブなスポンシーの一人がこんな状況で、とりあえず彼が精神的・経済的に自立するまでお母さん元気でいてくださいと、こちらも祈るような気持ちでいるのです。
もくじ|過去へ|未来へ
