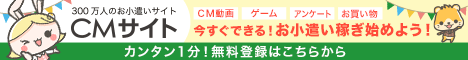どんなことばで
「おーわかった。んじゃまた連絡するわ」
別段とりとめもない話をした後、電話を切ると、部屋の中に静かな空間が帰って来た。
フリップを閉じた携帯をベッドの上に軽く放り投げ、手持ち無沙汰になる。
荷物の整理でもするか。と、櫻井はベッドに胡坐をかくように座りなおし、持ってきたバッグを引き寄せた。
と。隣のベッドに寝転び、読んでいた雑誌から目を離さないままの松本が、なんとなしに口を開いた。
「翔くんてさぁ」
返事もしないし顔も向けないが、聞いてますよ。というオーラだけは出しておく。
「まだ裕貴くんと続いてんだ?」
瞬間、櫻井の動きが止まった。
何を言い出すのか。というか、会話を聞いて勝手に相手を予想するな。というか、その質問にどう返せと。
言葉を失う櫻井。
ゆっくり首だけを、わけのわからない質問を投げかけた松本に向けた。
「あ、ごめん言い方おかしかった」
櫻井の視線に気づき、松本も雑誌から目を離すと、顔だけを向かい合わせる。
その表情は、自分の発言の妙に今気づきました。というものでは決してなくて。
絡み合った視線の先にある黒い瞳の重みに耐え切れず、櫻井は思わず目を逸らした。
「おかしすぎだろ」
荷物の整理を始めたはずなのに、出したものをまた戻すだけの作業になっている。
その動きを見て、松本の目もまた雑誌に戻るが、果たして内容は頭に入っているかと言えばそれは皆無。
「嫉妬してるんじゃないから安心して」
少しわざとらしいフォロー。声も無駄に笑わせているのはわかるが、表情は確認できない。
それがリアルで嫌なんだよ。
櫻井の眉間に皺がよる。舌打ちしそうになったが、こらえた。
「って、お前はオレのなんなんだよ」
つられたようにわざとらしく笑いながらも、話し相手に顔は向けない。向けられない櫻井。
松本からも、答える気配は感じられない。
バッグの中は、整理したはずなのに開ける前よりも乱れてしまったが、もう一度出すのも白々しい。
結局そのままにしてジッパーを閉じると、その音が妙に大きく響いた気がした。
隣の人間は、雑誌を読んでいるはずなのに、ページをめくる音すらしない。
訪れる静寂。
「なんなの?」
壊したのは、松本だった。
声の主に顔を向けると、いつの間にか松本もまた櫻井を見ていた。
視線がかち合うと、開いているだけだった雑誌を閉じ、立てていた腕を顎の下で組んで、うつ伏せになる。
が、櫻井から見える左目だけは、こちらに向けたまま。
「オレが聞いてんだよ」
「オレもわかんないもん」
うって変わって、すぐさま答えが返ってくる状況。
反則だろ。
問いに対する問いは、松本の十八番だろうけれども。わかっていてやってるのだろうけれども。
それがまた、櫻井に苛立ちを募らせる。
自分の問いに自分で答える義務などない筈なのに、そうはいかない雰囲気にさせられているのは何故か。
まっすぐ自分を見つめる瞳。少しだけ、視線を横にずらして言う。
「バカ、メンバーだろ」
やっとの思いで出た言葉は、当たり前すぎて、逆に、棒読みのようになってしまった気がする。
「知ってる」
予想してましたと言わんばかりの抑揚のない声で答えた松本は、瞼を閉じ、顔を枕と腕の中に沈めた。
表情が見えなくなって、なぜか櫻井はほっとする。
じゃあ聞くなよと言いたくなるのを抑えて、無意味に頭を掻いた。そういうことじゃないのはわかってて言った。
ここで自分がそう持っていっても、相手が同じ方向に取り合ってくれるはずはなくて。
だからといって、そこに松本が求めているのだろううまい表現を、さらりと当てはめられる自信もない。
大体にして、今更そんな質問をしてくる松本の方がどうかしている。
なんなんだ。
ため息をひとつ、松本に気づかれないくらい小さく吐く。
空白の時間に耐え切れなくなった櫻井は、もう一度バッグを開けると、ポータブルCDプレイヤーを出した。
適当なCDをセットし、イヤホンを当てようとした時。
「裕貴くんは、なんなわけ?」
タイミングを計ったように、新たな問いかけ。顔は、埋めたまま。
先ほどから引っ張り出された名前は、櫻井にとって、松本を含む嵐のメンバーとは別に大切な友人のもので。
昔は仕事仲間として。今はプライベートでの付き合いがある。
勿論松本も知っている。
なぜ今更、それを引き合いに出してくるのか。本当にどうかしている。更に募る苛立ち。
付き合いきれねぇよ。
問われても、櫻井の顔は、もう相手には向かなかった。松本の表情は、読まない。答える必要は、ない。
「おまえ、うざい」
反応が返ってくる前に、櫻井は乱暴にイヤホンを耳にあて、音量最大で演奏開始ボタンを押した。
櫻井がその忘れ物に気づいたのは、ホテルを出て大分経ってからだった。
マネージャーに聞いてみたが、ホテル側からも、それらしきものは見つからなかったと返ってきたらしい。
直感。松本が持ってる。
結局ふたりはあの後一言も会話を交わさず別れ、それから、会っていない。
互いのスケジュールの所為もあるが、電話もメールもせずに数日経っているというのは、かなり稀有だろう。
今日は週のど真ん中、水曜。あと3日もすれば、生番組でどうせ会う。
連絡せずとも持ってきてくれるのが人ってもんだろうと、櫻井は勝手に自分を納得させていた。
だが、渡される時のことを考えると、また一悶着あるかもわからない。
「…めんどくせぇ」
いつもはある筈の指輪の位置…右手の人差し指を、無意識に親指でいじりながら、櫻井は小さく独り言ちた。
「翔くん、寝てんの?」
ひとり車の中でまどろんでいたところに急に声をかけられ、櫻井は今に引き戻された。
「おはよ、さとっさん」
乗り込んできたのは、大野。今日はふたりで雑誌の取材。マネージャーの運転する車で、撮影場所に向かう。
おはようと小さく返しながら、大野は相変わらずのぼやけた瞳で思い出したように言った。
「松潤から伝言。どーすんの、アレ。って」
「アレ?」
思わぬ人物から思わぬ話題を振られ、櫻井は一瞬面食らったが、すぐに全てが読み取れた。
少し考え込んでいると、伝言の付け足し。
「言えばわかるから。って言われたけど」
大野に、詮索してくる様子はなかった。興味がないのか、聞いてはいけないと思っているのか。
どちらにせよ、当事者としては助かる伝言役だった。
それにしても、わざわざこんな伝言役をよこすとは、一体何の意図があってのことなのか。
何も言わず土曜に持ってくれば良いだけの話だろう。もしくはメールで一言よこすなり。
櫻井の中で、苛立ちというよりは気に食わないという気持ちがふつふつと湧き上がってきた。
受けて立とうじゃないの。
「じゃさ、悪いんだけど俺のも伝言してくんね?愛してるから捨てないでー。って」
体はシートに寄りかけたまま、捨てないでの部分だけ少しオーバーに手を伸ばして言う。
「はぁ?」
「言えばわかるから」
怪訝な顔の大野が面白くて、櫻井はわざと大野に顔を近づけ、松本の口ぶりを真似てみせた。
それが気に食わなかったのか、眉間に更なる皺を寄せ、大野は口をふくらませる。
「つーか自分で言えっ!」
「あははは!」
土曜まであと3日。伝言係が訳もわからず働いてくれるならば、それより前に何か松本からアクションがあるかもしれない。
笑いながらも、右手の人差し指の風通りの良さは、櫻井の心に反比例していた。
それはやはり金曜の夜に起こった。
櫻井が単独での雑誌の取材を終えた直後、タイミングを計ったようにかかってきた電話。
液晶に表示された名前は、勿論、松本潤。
スタジオの廊下を歩きながら、櫻井は適当な声でその電話に応えた。
電話の相手は、予想通り、名も名乗らず、挨拶もなし。不機嫌そのものの第一声はこうだった。
「なんなの、あの伝言」
いつになく低いトーン。感情は、読めない。
「伝わった?愛」
肩と首で携帯を挟み、櫻井は、誰が見てるわけでもないのに両手でハートマークを作って答えた。
が、電話の先からは当然、冷たい声。
「ふざけんな」
可愛らしい答えを期待していたわけでは決してないが、こうもあっさりあしらわれるとは。
自分のキャラ作りも相当虚しくなってくる。
「何、その態度。言ってほしかったんじゃないの?潤ちゃんてば」
わざとふざけた声にしてみせた。
少し強気に出れるのは、顔を、あの無駄にプレッシャーをかける瞳を見ずに話せるからだろうか。
「むかつく。捨てちゃおっかな、忘れ物」
当の松本は、むかついてるとは思えないほどの抑揚のない声で、すぱっと衝撃的なことを言ってみせた。
捨てられる筈はないとわかっていても、少し接し方を改めなければいけないらしい。
櫻井も、無駄な労力を消費しないように、本題に会話を促すことにした。
「はいはい。で、今どこにいんの?」
こうなったら一刻も早く忘れ物を取り返し、この刺々しい空気を、とまらない苛立ちを、和らげたい。
外にいるなら、帰りにでもマネージャーの車で寄ってもらえば、すぐだ。
面倒な事になる前に帰る口実もできる。
が、櫻井はその目論見を、瞬時にして消さざるを得なかった。
「…の公園」
「は?」
前半が聞き取れなかったのは、電波の調子でなく、わざと松本が声を濁して言ったからだとわかった。
聞き返すと、今度はその信じられない答えをはっきりと聞く事ができてしまったから。
「今翔くんがいるスタジオのすぐ近くの公園だよ」
「はぁ?!何やってんのお前!」
思わず声をあげると、コンクリート打ちっぱなしの廊下に反響し、櫻井は慌てて辺りを見回した。
誰もいないのを確認すると、すぐに思考に神経を戻す。
が、たった2,3秒前の、少し自棄的な声の松本の言葉が、櫻井には理解できなかった。
というよりは、理解したくなかったのか。
だが、混乱する櫻井をうっちゃって、松本は勝手に独りで話を進めてしまう。
「2分で来ないと、マジで捨てちゃうから」
勢い的に言い捨てられ、通話が切れた電子音が聞こえた。
「ちょっ…待てお前こら!」
一方的に切られた電話を強く握り締めて、聞こえるはずのない相手を必死で制止する。
無情にもその願いに応えるのは無機質な電子音だけなのはわかっていても、そうするしかなかった。
いつの間にか足は止まっていたらしい。先程から変わらぬ廊下の景色。
公園までは、どう頑張っても5分はかかる距離だ。
「っざけやがって…」
今や光を全く放たない携帯の液晶をきつく睨みつけ、乱暴にフリップを閉じると、櫻井は走り出した。
途中、マネージャーとすれ違うと、振り返りざまに送りはいらないとだけ伝え、スピードをあげる。
息が切れる。頭に血が上る。鼓動が、脈拍が、速くなっていくのがわかる。
そうさせてるのは、この走りなのか、それとも、気持ちなのか。
これだけ走って、辿り着いて、そこで、自分は松本に何を言うのだろう。何が言えるのだろう。
あの問いへの答えは、まだ出ていないのに。
いや、出ているのかもしれない。ただそれを、言葉にしたくないだけで。
賽は投げられた。一方的に。
ここから先のお話は、2パターンに分かれております。お好きな方を選んでどうぞ。
○ちょいと破滅的なSJがお好きな方はあっち
○仲良しラブラブなSJがお好きな方はこっち
 ○ハジメマシテ
○オエビ
○ノベル
○ダイアリー
○ハジメマシテ
○オエビ
○ノベル
○ダイアリー ○ハジメマシテ
○オエビ
○ノベル
○ダイアリー
○ハジメマシテ
○オエビ
○ノベル
○ダイアリー