
|
 |
| 2004年02月28日(土) ■ |
 |
| ◆『アナニアシヴィリの白鳥の湖』 アナニアシヴィリ、ウヴァーロフ、フィーリン、クレフツォフ、ペトローワ、パーリシナ他 (04/03/08up) |
 |

東京文化会館 14:00〜
芸術監督:アレクセイ・ファジェーチェフ
指揮&ヴァイオリン:セルゲイ・スタドレル
(演奏:東京ニューシティ管弦楽団)
お久しぶりのニーナ・アナニアシヴィリのグループ公演。以前はパ・ド・ドゥ部分が多い、お祭りガラのような公演でしたが、今回は作品そのものを見てもらうという趣旨に、移行してきたような気がします。
3つの作品それぞれ雰囲気が違い、なかなか楽しいひとときでした。
でも最後まで観て、やっぱりニーナはクラシカルな作品で、より輝くような印象は変りませんでしたが...。
今回は、当初予定されていた、マリインスキー・バレエのイルマ・ニオラーゼの代わりに、彼女と同じ故郷グルジアのダンサー、ラリ・カンデラキを起用。(ニーナは、ニオラーゼといい、カンデラキといい、同郷で頑張っているダンサーを大切に思っているんですね)
指揮者も、体調不良の為、来日出来なくなってしまったソトニコフさんの代わりに、セルゲイ・スタドレフさんが務められました。
この方はヴァイオリン・ソロも同時に演奏され、彼のおかげでかなり個性にとんだバレエ公演になりましたね。
スタドレルさんは、ヴァイオリニストとして、驚くほど数々の賞を獲得されている実力者のようで、例を挙げるとプラハ国際、ロン=ティボー、チャイコフスキー・コンクールなどで優勝&金メダル、その後ペテルブルグやモスクワでオペラやバレエの音楽監督や指揮者を務めていらっしゃるそうです。
検索してみたら、過去にモスクワ放送響でファドセーエフ指揮のもと、チャイコのコンチェルト演奏の為に来日していたり、ソリストとして活躍なさっていたようですね。
ニーナの公演では指揮をしながら、ソロ・ヴァイオリンが入る箇所で、いきなり客席の方を向き演奏開始。ソロが終わるとまたオケの方に向きなおす、という特殊なやり方をされていました。
私は正面の席ではなかったですが、舞台に近かったので、彼の派手に動く演奏姿が目に入り、神経がそちらに行ってしまうこともしばしば...。
指揮者近くの観客は、あの大きなお姿と激しい動き、それに迫力ある演奏で、一時はバレエより彼が気になったのではないかしら。
日頃のバレエ公演で聴くような、踊りの伴奏演奏というより、音量的にもフレーズひとつ取っても大変個性的で、私は面白かったのですが、観客は意見の分かれるところかもしれません。
◆『グリーン』
音楽:ヴィヴァルディ (オケ演奏 30分)
振付:スタントン・ウェルチ
ニーナ・アナニアシヴィリ
セルゲイ・フィーリン
ドミトリー・ベロゴロフツェフ
コール・ド・バレエ
この作品はヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲に触発された、現在ヒューストンバレエに芸術監督で振付家のウェルチが、ニーナ、フィーリン、ベロゴロフツェフ&モスクワ・ダンス・シアターの為に創作した作品との事です。
事前にチラシ等のイメージでは、緑のロマンティック・チュチュ型の衣装を着た群舞が幻想的に写っており、ゆったりとした柔らかな印象の作品かなと思っておりましたが、実際には、快活でテクニカルな男性群舞や、早めのバロック音楽にのった鮮やかなステップ部分も多いものでした。
きちんと覚えてはいませんが、男女各8人の群舞が登場する場面は明るめの曲調。ニーナとベロゴロフツェフ、またはニーナとフィーリンによるパ・ド・ドゥ場面はしっとりとした雰囲気で、たっぷり魅せてくれます。
素敵だったのは、何といってもフィーリン。 ステップの正確さ、全てにおいてフォームが美しくて崩れのない踊り。彼は、私の中では見るたび印象が良くなっていきます。
それに、どのようなスタイルの踊りでも、幅広く自分のモノにしする能力のある方ですね。
以前より髪が長くフワッとさせていて、いっそう麗しかったです。
ニーナはこのようなシンフォニック・バレエ作品では、悪くはないんだけれど、他を圧倒するすごさは、それほど感じられなかったかな。
それでも踊りの大きさは、彼女ならではですし、本人のもつパーソナリティーが舞台を彩っていました。
ベロゴロフツェフも良く踊っていますが、この作品ではフィーリンに比べるとインパクトは弱かったかかも。
衣装は全員タイトルどおりグリーンカラーです。ニーナは灰色がかったモスグリーンのロマンティック・チュチュ風で、女性群舞はもう少し明るい若草色。ベロゴロフツェフとフィーリンは下だけのタイツ姿で、男性群舞はユニタードでした。
◆『セコンド・ビフォー・ザ・グラウンド』
音楽:アフリカン・ミュージック (テープ演奏 30分)
振付:トレイ・マッキンタイアー
インナ・ペトローワ
エレーナ・パーリシナ
ラリ・カンデラキ
ドミトリー・ベロゴロフツェフ
セルゲイ・フィーリン
ユーリ・クレフツォフ
コール・ド・バレエ
アメリカの振付家マッキンタイアーが、ヒューストン・バレエの為に創作した作品。
解説によれば、アフリカ諸部族に伝わる、《死の1秒前に、人はそれまでの人生の幸福な時間と最も重要な瞬間のすべてを思い出す》という考え方にインスピレーションを受けて創られたとのことです。 日本的に言えば、死ぬその一瞬に「人生が走馬灯のように見える」とよく聞きますが、それに近い意味なのかもしれませんね。
で、このように書いてあると、何だか重たそうな印象を持ちそうですが、実際は気持ち良い、幸福感に満ちた作品でした。
出演者が皆、楽しそうに踊っていたのが印象的ですね。
使っている音楽はアフリカン・ミュージックだそうですが、思ったより洗練されていて、アメリカ南部風、田舎風?な心地の良い感じかな。
カンデラキ&ベロゴロフツェフ組、ペトローワ&フィーリン組、パーリシナ&クレフツォフ組の順番に登場し、場面が変ってもひたすら幸福な世界を見せてくれます。舞台背景の色調が3組それぞれ変化し、見ようによっては、朝昼夜の風景にも見えました。
そしてどのペアもとても楽しげなこと!
久しぶりに観たペトローワってビックリするほど表情豊かでまろやかな雰囲気、スタイルも昔のまま美しかった。前回(2001年)、2人とも公演に参加していたのに、なぜかフィーリンと組んで踊らず残念に思いましたが、今回はあの幸せそうなペトローワの表情見れただけで満足です。フィーリンはやっぱりいいですね。
パーリシナ&クレフツォフ組は以前『スパルタクス』でも見ましたが、パリーシナはあの時より更にベテランの熟成というか、カッコ良さを感じました。とても動きのキレが良くて、難しい踊りも安心して見ていられる。
そしてペアとしてとても合っていますね。威厳も感じられた。

◆『白鳥の湖』ハイライト
音楽:チャイコフスキー (オケ演奏 55分)
原振付:プティパ、 追加振付/演出:ファジェーチェフ
オデット/オディール: ニーナ・アナニアシヴィリ
ダンサー/ジークフリード王子: アンドレイ・ウヴァーロフ
芸術監督/悪魔: イラクリ・バフターゼ
王妃: ショレナ・ハインドラワ
コール・ド・バレエ
オーケストラの序曲が始まる。
幕が開くとそこはバーや鏡が据えられたバレエのリハーサル・スタジオ。
オーケストラの旋律は、そのままピアノに変る。
レッスン中ながら、芸術監督はプリンシパル(ウヴァーロフ)の出来に不満で緊張感のある空気があたりを包んでいます。
次第に他のダンサーはその場から去り、芸術監督も重い空気のまま去ってゆく。
疲れたプリンシパルは、バーの近くでうたた寝をする。
そしていきなり舞台は本来の『白鳥の湖』第2幕(or1幕2場)の場面に変ります。
ウヴァーロフはジークフリード王子になり、夜の湖を彷徨っている。(つまり眠っている間の夢のお話ということか)
あとは普通のダイジェスト版『白鳥の湖』でした。
ニーナの『白鳥の湖』を観たのは2度目。前回はABT日本公演の時です。
その時はどうしてもニーナの元気よさばかり気になって、柔らかく踊っていたけれど白鳥としてはそれほど印象深く感じませんでした。(少々雑だったかも...)
で、今回ですが、円熟と言ったらまだまだお若く見えるので失礼かと思いますが、とっても大きな踊りで美しかったです。
儚いとか、助けてあげたいとかそういうのではなく、悲劇に対しても受け止める強さや、大きな優しさを感じました。
柔らかくしなう肢体が見事。グラン・アダージョの滑らかさは秀逸ですね。
ウヴァーロフ王子もとても美しいし...。
でも、ヴァイオリン・ソロのスタドレルさん、やたら目立っていたなぁ。何度か指揮者の方を見てしまいました。
黒鳥の方はニーナの真骨頂といった感じでとても華やか。誰もが自然に目を奪われてしまいますね。
フェッテは以前みたいに物凄いスピードで回るというより、ちゃんと丁寧に踊っていました。
黒鳥のヴァリは、ボリショイと同じ妖しげな音楽の方。(ABTでもニーナはこちらのヴァリでした)
王子のヴァリもボリショイと同じ、チャイコフスキー・パ・ド・ドゥの曲を使用。
舞踏会の場面では花嫁候補の踊りもしっかりありました。
悪魔ロットバルト役は、あの(折り合いの悪かった)芸術監督という演出です。
王妃役は、若いダンサーが演じていましたが、無表情で無味乾燥。
舞踏会の場面で王子が悪魔に騙されて城は大混乱へ...と、ここで、元のリハーサル室の場面に戻ります。
プリンシパルはうたた寝から目を覚まし、夢の続きのように白鳥オデット現れ、そして消えてゆく...。
あらすじでは、夢から覚めたところで、「自分が恋人を裏切ったことを理解する」と書いてあるのですが、演出が説明不足で理解不能。あとから、「へぇ〜」でした。
ファジェーチェフのハイライト版は、工夫はされているようですが良くなったようにはあまり思えません。
でも、この短い時間に、見たい踊りは挿入されていたし、ニーナやウヴァーロフ、そしてコール・ド達の豪華な踊りが観られたので、満足です。
とにかく“ロシア・バレエ”を存分に楽しませていただきました。
*最後に一言、
こういった全幕でない公演にもかかわらず、(白鳥で)コール・ド・バレエを24人揃えたのには驚きました。(男性ダンサーもソリスト以外に8人連れてきたし...)
しっかりと作品を見せたいという意思を感じましたね。
しかし不満な点もあります。ニーナ達以外は、公演パンフレット等に、大事な役を踊ったダンサーでさえ、どこのバレエ団から参加したのか一言も書かれていないこと。結局どこのコール・ドだったのか...。
せっかく一生懸命に踊っているダンサーや、観に来ている観客に対しても不備だと思いますが。
【特別アンコール】
大きな喝采と共に幕が閉じると、芸術監督のファジェーチェフさんがマイクを持って登場。
姿を見たとたん、恒例の「おまけ」だなと察した私はとても嬉しい気分になりました。 ニーナをはじめとする出演者達の温かな気持ちと誠意を感じますね。
◆『スパルタクス』より《スパルタクスとフリギアのアダージョ》
音楽:チャイコフスキー、 振付:グリゴローヴィチ
(エレーナ・パーリシナ&ユーリ・クレフツォフ)
この作品&このパ・ド・ドゥはとても大好きで、観る度に新たな感動を覚えます。
音楽も踊りもとにかく美しくて、男性の力強さ、女性のたおやかさが存分に表されている作品だと思います。
パーリシナ&クレフツォフは数多く演じてきたとみえて、胸に迫るような深みのある踊りは本当に素晴らしかった。
この演目の主人公のようにお互いを思いやるカップルの、年を経て到達した熟練の世界に酔いしれました。
◆『ドン・キホーテ』より
音楽:ミンクス、 振付:プティパ
(ニーナ・アナニアシヴィリ&アンドレイ・ウヴァーロフ、全員)
ドン・キホーテの華やかな音楽が流れると、会場全体が喜びに包まれました。この音楽はニーナのテーマ曲という感じですね。
2人ともレッスン着姿でニーナは下が赤いチュチュ。普段よりも愛嬌やユーモアに富んだ楽しい踊りを披露してくれました。
例えば、ウヴァーロフが手を差し出して、ニーナがその手に掴もうとする。すると、ウヴァがサッと手を引っ込めて、悪戯っぽい笑顔を見せる。
次は逆で、手を出されてもニーナはお返しとばかり無視して、ニッコリ。
何だか微笑ましいやり取りで、会場から笑いが漏れます。
踊りの方は、長いバランスや、得意のフェッテを大いに見せつけ、最後のコーダでは全員が次々に登場し、素晴らしい妙技を見せてくれました。
コール・ド・バレエの皆さんも、カーテン・コールではお揃いのシャツを着て嬉しそうに登場。
和やかな雰囲気に包まれた良い公演でした。
|
| 2004年02月13日(金) ■ |
 |
| ◆東京バレエ団『中国の不思議な役人』(初演)、『春の祭典』、『ドン・ジョバンニ』大嶋正樹、首藤康之、吉岡美佳 (04/02/16) |
 |
ゆうぽうと簡易保険ホール、開演18:30〜、(音楽はテープ演奏)
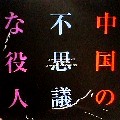
久しぶりに、五反田「ゆうぽうと」でバレエを観ました。
NBS主催の東京公演では、以前はよくコチラのホールを使っていましたが、「東京文化会館」ではない時には「文京シビックホール」にいつのまにか変り、また再びコチラ(ゆうぽうと)を使用する事になったみたいですね。 東バの『ベジャール・ガラ』や、今度来日する『モーリス・ベジャール・バレエ団』もココを使うようです。
「ゆうぽうと」は舞台との距離感がないですし、観やすいらしいのですが、どうもあまり個人的には好きではない。
街も建物の雰囲気も何となくねぇ〜、といいつつ、今年は何度も通う事になりそうです。
では、今回の公演について。
《ベジャール・フェスティバルⅠ》
【春の祭典】 (ストラヴィンスキー)
生贄: 首藤康之
二人のリーダー: 後藤晴雄、芝岡紀斗
二人の若い男: 中島周、古川和則
生贄: 吉岡美佳
四人の若い娘: 佐野志織、高村順子、門西雅美、小出領子
昨年観たシカゴ・フィルとの《奇跡の饗演》『春の祭典』と、この日のキャストは、奇しくも中島周さん以外は全く同じメンバーでした。
今回のは通常通りのテープ演奏による『ハルサイ』です。
見た印象ですが、《奇跡の饗演》のときの方が、良い意味での緊張感が客席まで伝わってきて、音楽を一音一音の身体で捉えて表現する力がすごかったような気がします。
あのピリピリとした集中力から比べると、強烈ではなかった...。
まぁ《奇跡の饗演》の時の印象がとても良かったということですね。
表現するのは難しいのですが、ゆったりとしたところ、激しくなるところ、動きの抑揚の幅が、ほんの少し音楽と共に流れてしまい、どんどん先へ進んでいってしまった印象。
全体的に「神秘的」というのが薄らいだ感もありますが、それは音楽(生演奏と録音の違い)の力なのでしょうか??
照明もこんなに強い色だったかな?(うーんハッキリ思い出せない)
でも観終わって満足感はあります。今回観た3作品の中では、回を重ねているせいか、一番しっくり馴染んで見えました。
特に何といっても首藤さんと吉岡さんが大変素晴らしく、それぞれの個性を充分に発揮されて、観客の皆さんも満足されたと思いますよ。
三つの作品の中で一番長い作品なのにアッという間に終わってしまった感じです。
首藤さん独自の、(内にこもったような?)個性は、他に代わりが見当たらない貴重なものだと感じますし、やはり見る度にどんどん引き込まれてしまいます。踊りも良かった。
吉岡さんは、東バ随一の表現力を持った方ですね。腕や表情についても細やかにしっとりとしていて、激しすぎない静かな情熱がとても素敵でした。
【ドン・ジョバンニ】 (ショパン「モーツァルトの主題による」)
ヴァリエーション 1: 高村順子 門西雅美 武田明子
ヴァリエーション 2: 小出領子
ヴァリエーション 3: 太田美和 井脇幸江
ヴァリエーション 4: 佐野志織
ヴァリエーション 5: 遠藤千春
ヴァリエーション 6: 吉岡美佳
シルフィード: 福井ゆい
軽いデザートのような楽しい作品でした。要約すると、レッスン着姿のバレリーナ達が一人の(姿の見えない架空の男性)ドン・ジョバンニに、妄想や夢、憧れを持ち、様々なかたちと個性でアピールする。最後はオチも付いています。
かなりクラシカルな振付で、他のベジャール作品のイメージとはちょっと違っていました。
まず冒頭に男性の声で、女性に対するドン・ジョバンニ?の心の声?のナレーションが流れるのがちょっとしつこく感じます。そこで使われる「ぞっこん」という、時代がかった言葉はちょっと笑えました。和訳が凄いだけか...。ユーモアのある導入部。
面白かったのは、太田さんと、井脇さんのコンビ。全く違う個性の彼女達の踊りや演技は印象に残りました。遠藤さんは華がありますね。その中でも特に良かったのは吉岡さん。踊りが美しい...。
シルフィードの存在は一人だけロマンティック・チュチュなので、とても目立ちましたが、最後までよく解らなかったです。
様々なキャラクターが生き生きと描かれていますが、作品としては、心に深く...というものではなくて、見たまま楽しめば良い作品なのでしょうね。
でも例えばスター達のガラ公演のとき、最後に全員で見せてくれたらかなりウケるんじゃないかと妄想しました。
【中国の不思議な役人】 (バルトーク)
無頼漢の首領: 後藤晴雄
第二の無頼漢―娘: 大嶋正樹
ジークフリート: 芝岡紀斗
若い男: 井脇幸江
中国の役人: 木村和夫
ベジャールに新作『今日の枕草子』から、氏の体調が芳しくないとのことで、急遽プログラムが『中国の不思議な役人』に変更になりました。チケットを切るとき、『今日の〜』が印刷されているものと、『中国の〜』が印刷されたチケットと2種類見かけたので、一瞬自分が間違えて見にきてしまったのかと焦りました。(笑)
本作品は、モーリス・ベジャール氏がフリッツ・ラング監督の『M』という映画作品と、作曲家バルトークからインスピレーションを受けたとのことですが、どちらも私にはあまり馴染みがなく、始まる前の休憩時に見た、パンフに載っている映画の写真や、過去のベジャールバレエ団での上演写真を見て、勝手に暗く妖しいデカダンスの世界を想像しながら開演を待ちました。
さて、この作品の出だしですが、パンフレットの解説に書かれているような怪しさが漂う暗黒街の雰囲気が、凝ったライティングやスモーク等で表されていて、かなりイケるんじゃないかと思ったのですが...。
大勢の無頼漢たちや、首領の後藤さんの様子も、裏社会の男に上手くハマっていて怖いくらい良い感じです。
ですが、この作品の大事な鍵を握る「娘」役の大嶋さんが、渾身の熱演にもかかわらず、妖しさとか背徳的な香り、相手が誘惑にのるような色気が私には感じられず、あまりにも現実的でガサツな「男」に見えてしまいました。別に“男”に見えても良いのかもしれませんが、退廃の空気というものがあまり感じられない...。
この作品について詳しい訳ではないので、単にパンフの写真で感じた私のイメージが、もっとディープで不安な世界を想像していただけかもしれませんが、“誘惑者”としての「娘」の雰囲気に最後まで違和感をもってしまいました。
でも、彼の“熱”と、最後には何とも言えない悲しさは伝ります。
それと、これは私の勝手な想像ですが、ベジャールは「娘」を男性に演じさせたときに、ヴィスコンティの映画『地獄に堕ちた勇者ども』のヘルムート・バーガーも、多少イメージを重ねているのではないかと...。
暗黒街=ナチの台頭する世界、「娘」=女装するヘルムート・バーガー(黒いスパンコールと羽の衣装の酷似)、共通性を感じさせる危うく狂気的、スリリングな雰囲気など...。
何となく世界観が似ているように感じます。
他の役、「ジークフリート」と「若い男」は割と軽めでユーモアを感じ、木村さんの「中国の役人」は、スッキリとして薄味ぎみでした。
...なぜか不思議とそんなに印象に残っていません。
今回の公演は正直、言い表わすことが難しいです。「中国〜」に関しては、準備期間が短かったこともありますので、更に深く追求していって欲しいと思いました。
勿論、観る側もよりいっそう、「作品」を感じていきたいとは思います。
|
| 2004年02月04日(水) ■ |
 |
| ◆ 『二月大歌舞伎』(夜の部)團十郎、仁左衛門、玉三郎、三津五郎、時蔵、左團次、他 (04/02/07up) |
 |
二月大歌舞伎「夜の部」を拝見しました。
今月の歌舞伎座は紅白の梅花で飾りつけられています。
夜の部は通常より開演が遅めで、終わったのは9時ちょっと前でした。全体に少し短めだったかな? その分、昼の部が長くなっているようです。
内容的にはどの演目も面白かったです!! ハッキリ申せば、お正月の公演より満足できました。
歌舞伎座に到着すると、まだ開場少し前。早めに来ているお客様が入口の脇あたりに並ばされていましたが、ずっと外で待つのはイヤでしたので、「一幕見席」用入口の奥(正面入口右側)にある、喫茶室「檜(ひのき)」で待ちました。
今まで知らなかったのですが、この喫茶室は開場時間になると、レジあたりに歌舞伎座係員が出てきて公演チケットを切り、そのまま館内に入場することが出来るんですね。
混雑を避け、スムースに入場することが出来て便利です。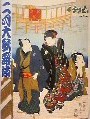
河竹黙阿弥 作
【三人吉三巴白浪】 (四幕八場)
(團十郎、仁左衛門、玉三郎、左團次、翫雀、七之助、吉弥)
今回は珍しく、両花道が用意されていました。(*上手と下手両方に花道あり)
いきなり始まったメイン演目の黙阿弥 作『三人吉三巴白浪』は因果や義理が絡んだお話で、一見ややこしく、無関係のような登場人物同士が、実はそれぞれに深く関わりがある。
話が進むにつれ、謎が解決していくようなプロットが組まれていて、全く飽きずに楽しめます。
あっちこっち2重3重のエピソードが重なり、それが上手く最後までハマっていて、少し都合が良すぎる感じもしますが、それはそれで面白かったですね。
立ち回りや動きも派手な演目で、初心者でも筋書きを見なくてもついていけると思います。
それに華のある役者さん(團十郎、仁左衛門、玉三郎)の揃い踏みで見られるというのは有り難いこと。
親分肌の「和尚吉三」を演じた團十郎さんは、演目のせいか、ここ最近の見た中では一番元気良く感じられ、何度も演じてきたという大きさと余裕が見てとれました。悪党でありながら義理人情の厚いという「和尚」を好演。この役は今回8度目だそうです。
何の因果か、「血の盃」で誓いを交わした“三人の吉三”の一人「お坊吉三」に、親を殺められ、可愛い妹は知らぬこととはいえ双子同士で契りを交わしてしまったので、業の為、殺さなければいけない...。
色々な事実が「和尚吉三」に突きつけられ、苦悩しながら覚悟を決めて行動するその姿はズッシリきましたが、悲しい場面でもテンポがある作品なので、重くなり過ぎず良かったと思います。
元は武家の出で悪党ではなかったが、不幸な事件をきっかけに悪の道に染まってしまった若造「お坊吉三」を仁左衛門さんが演じくれました。
最初に登場した姿も、黒の着流しで現れたときも、ゾクッとするほど色気があり、颯爽ともしていて、仁左衛門さん特有のこのカッコよさは毎回楽しみで見たくなってしまいます。
最後に雪の降る中、屋根の上で大立ち回りをするのですが、高い屋根から隣の屋根に飛び移ったり、かなり激しい動きをこなされていて、殺陣の刀捌きの美しさにも圧倒されます。
捕手役のトンボを切る若衆達もかなり頑張っていて、アクロバティツクな中にも様式の兼ね備えた美しさがあり、大変見応えがありました。
「お嬢吉三」は初役という事でビックリしたのですが、玉三郎さんの新たな一面を見ることが出来ました。
「お嬢」は姿かたちが大変艶やかですが、実は男という役柄。それに盗みを生業にしている一応悪役なので、ドスをきかしたしゃべりもあるし、立ち回りも沢山ある。でも見た目は美しい娘にしか見えないという何とも面白い役です。
今回、色恋沙汰は出てきません。ひたすら小気味良く啖呵を切るところや、気持ちの良い台詞回しも楽しめます。(「月も朧に白魚の〜」とお馴染みの名台詞も序幕に出てきます)それに娘の衣装も大変美しかったですね。
しかし、大詰『本郷火の見櫓の場』のようなあんなに立ち回りをしている玉三郎さんを見たのは初めてかも...。
このお話、大変洒落ていて、後半は「お七趣向」も楽しめます。「櫓のお七」話で有名な、吉祥院の欄間(らんま)に隠れるところや、雪風景の櫓セットが出てきたり、「お嬢」が「お七」風な衣装で現れたり、元は八百屋の娘というエピソードなど...。 場面をもじったような趣向が所々に出てきます。
両花道は大詰めに『火の見櫓の場』の時に使われました。
「お坊吉三」が従来の下手側花道、「お嬢吉三」は上手側花道から登場。
二人は追われる身なので、むしろで顔を隠してゆっくりした歩みで登場します。
行き着く先は木戸の閉ざされた雪の降る江戸本郷の町。二人はそれぞれが木戸に挟まれ自由に逃げる事が出来ません。
この後、追っ手である捕手達との激しい大立ち回りになります。(動きが激しかったせいか、捕手役の一人の鬘が取れてしまいました。そのまま演技を続けていたけど...)
一月に休演となった左團次さんも「和尚吉三」の父「土左衛門伝吉」役で元気に復活され、それはもう味のある良い演技をなさっていました。
前回見た時の舞踊演目は、あまり気合が感じられず元気がないと思ったのですが、きっと具合が悪い中演じていたのでしょう。今回は大変素晴らしかったと思います。
七之助さんも初々しい娘「おとせ」を大変好演なさってました。
七之助さんは前より背が高くなった気がします。実は(契ってしまったが)双子の兄という設定の「十三郎」役、翫雀さんと並んだら頭ひとつ大きかったです。
話し方、歩き方、仕草など、とても色っぽかったですね。
《舞踊二作品》
『三人吉三巴白浪』の他には二つの舞踊演目が用意されていました。
「傾城もの」と江戸風でいなせな「祭りもの」という全く違った二つの作品を、休憩を間に挟まず、そのまま続けて上演というのは初めて見ます。
美術や鳴り物も異なりますので、果たしてどうのようになるのか興味深く鑑賞。
【仮初の傾城】 長唄囃子連中
(中村時蔵)
幕が開くとそこは江戸吉原の華やかな世界。紅色の壁、奥には大きな金色の襖、左側には、傾城が着用する紫の打ち掛けが、美しく掛かっています。
鳴り物は上手脇に並び、三味線の他にも笛や小太鼓、小鼓など音色の方も華やか。
奥の襖が開くと、うたた寝をしている傾城(時蔵さん)が前に押し出されて登場。
黒子が差し金を使い、背後で蝶がひらひらと飛び交っています。のんびりした優雅な始まり方ですね。
衣装が大変豪華で、大きな孔雀が刺繍された華麗なものですが正直とても重そう。
鬘も顔の近くの髪は結い上げられていて、後ろの鬢は腰までの垂らし髪になっていす。
踊りの方はとてもしっとりしたもので、動きは激しくありませんが、恋人からの手紙を読みながら相手を思う女心が、振りや仕草でよく伝わります。
傾城(花魁)という身の上は、相手が通ってくれない限り自由にも逢えないですし、相手の心変わりを心配する、女の心模様を艶やかに描いた作品でした。
途中、最初の打ち掛けから舞台上に飾られた紫の打ち掛けに変わるところがあり、目にも大変楽しませてもらいました。
踊りは、舞台の中央あたりで品良くゆったり踊る作品でしたので、上演時間はとても短かったですが、このくらいで調度いいと思いました。
【お祭り】 清元連中
(坂東三津五郎、他)
続いて『お祭り』ですが、これがもう粋で楽しい作品。
今回踊られる三津五郎さんのお家の芸とのことですし、踊りは特に素晴らしいと評判の方なので期待して見ました。
舞台転換はとても見事なもの。『傾城』は舞台前方を使っていたので、奥の襖が取り去られると祭りで賑わう江戸の町。脇のセットも一枚はがすと後ろに「お祭り」の美術が仕込まれています。
鳴り物連中は、大きな布で隠す形で総入れ替えしていました。このような転換を見せてくれるのはけっこう嬉しいことですね。
「お祭り」はとにかく面白い舞踊作品。山王祭が舞台で、ほろ酔い気味で登場したいなせな鳶頭は周りからも一目置かれる存在ということで、けんかに関してもその辺の若いものなど、軽く手玉に取るくらいのカッコイイ役です。その上、粋なユーモアも兼ね備えていて見ていて楽しいこと。
そして、三津五郎さんがとってもいいんです!! 踊りが本当に上手くて見惚れました。
序盤に客席から「待ってました!」との掛け声とそれに答える鳶頭。おかめ・ひょっとこのお面を被って踊るなど、お楽しみの部分もありますが、からみ相手として「若い者」が登場し、言いがかりをつけて飛び掛ってくるのを、軽くいなす三津五郎さんの踊りぶりが、とても晴れやかで気分がいい!
このように気風が良くてスッキリする出し物が最後というのは、気持ちよく劇場を後にできて良かったと思いますよ。
とても満足するプログラムでした。
|
|