前にも書いたことがあるが、ぼくが本格的に本を読み出したのは、高校3年の頃からだった。
その頃ぼくはミュージシャンを目指していたのだが、どうも作詞がだめだった。
もちろん人生経験が浅かったせいもある。
しかし、同じ世代の人間でもいい詞を書いている人はたくさんいた。
「この差は何だ?」と考えた。
そして「これは読書量の差だ」と思うに至った。
高3の頃は、クラスの中の浮いた存在であったため、休み時間なども一人でいることが多かった。
この一人でいることが、大いに読書に役立ったのだ。
その頃よく読んでいた本は、なぜか宗教書だった。
宗教書と書くと、何かカルト的なものを想像するかもしれないが、ぼくが読んでいた本はそういう類の本ではなく、当時よく読まれていた高田好胤師の一連の本や、『般若心経入門』などであった。
詩を読み出したのは、予備校に通い出してからだった。
新潮文庫や角川文庫から出ている『○○詩集』なる本は、ほとんど読んだ。
その中でも特に好きだったのが、中原中也と高村光太郎だった。
中也には詩の作法を習い、光太郎には崇高な精神を教わった。
中国の古典も、その頃読んだ三国志の影響から読み始めた。
特に老荘思想には惹かれるものがあり、よく読んだ。
が、その思想にのめり込んでしまい、予備校の勉強が馬鹿らしく思えるようになってきた。
そして予備校を退学してしまった。
東京にいた頃は、老荘思想と併せて再び仏教書を読むようになった。
そのせいで、ぼくは大人であることを避けるようになった。
その頃によく読んだ仏教書は法句経だった。
そのお経は「無邪気」を説いてあった。
「恰好つけても何にもならない。あるがままが一番」という老荘思想にも通じる内容に、ぼくは感化されたのだ。
ぼくが作詞のために読み始めた本は、結局老荘思想や仏教関係に行き着いたのだった。
さて、そういった本が作詞に何か好影響を及ぼしたのか?
答は否である。
確かに人生の歌のようなものは存在するが、人の心には響かない。
やはり作詞の基本は、より身近な「好いた」「くっついた」「別れた」なのである。
そういう路線をぼくは目指して、ぼくは本を読み始めたのだ。
が、先にも言ったとおり、結果的に行き着いたのは老荘思想や仏教の本だった。
そういった本には、そういうことは一切書いてない。
…いや、あることはある。
それは「別れ」だ。
が、その別れは「恋愛の別れ」ではない。
「永遠の別れ」である。
そういうわけで、ぼくが作った恋歌は、変に小難しくかつ主観的なものになっている。
そこには「しぐさ」が見えない。
言い換えれば「色気」がないのだ。
恋愛ものを読んでおくべきだった、と思う。
ちなみに、その後作詞を諦めたぼくは、人生のために本を読み始めた。
が、その行き着いた先は、歴史書や中国・韓国・北朝鮮のこき下ろし本だった。
どうも予定どおりにはいかない。
| 2004年06月29日(火) |
地味な運動をやっています |
数ヶ月前から、肩に痛みが走るようになった。
それに気づいたのは、ラジオ体操をやっている時だった。
例の「体をねじる運動」で腕を振った時、肩のつけ根に激痛が走ったのだ。
最初は1月後半、凍結した道で転倒したのが原因かと思っていたのだが、痛いのはその時痛めた左肩だけではなく右肩も同じように痛いのだ。
その状態が数ヶ月の間ずっと続いている。
人に聞くと「それは四十肩だ」と言う。
しかし、四十肩ではない。
確かに痛み方は四十肩に似ているのだが、腕はちゃんと上がる。
それに四十肩の時にはどの方向に腕を上げても痛いのだが、今回は腕をねじった時や、机などに肘をついていた時だけ痛いのだ。
そのことを人に言うと、「ただそれだけのことじゃないか。その歳になれば、多かれ少なかれ誰でも痛みは持っているものだ」と言われたのだが、その痛みが尋常じゃないから困っている。
ある時ふと気づいたことがある。
荷物を持っている時、肩が抜けるような感触があるのだ。
この感触をどう説明したらいいのだろう。
例えば、指を引っ張った時に、関節が抜けた感じがしたことがないだろうか。
その感触を肩に感じる、と思っていただいたらいい。
つまり脱臼したような状態になるのだ。
脱臼と同じような状態だから、当然痛みを伴う。
ということで、ぼくはこの痛みを脱臼、いや脱臼もどきの痛みだと思うようにした。
ぼくは過去に一度だけ脱臼をしたことがある。
3,4歳の頃だったと思うが、母が腕を引っ張った拍子に抜けたのだ。
まだ物心ついたかつかないかの頃だったが、その時の痛みだけは鮮明に覚えている。
まるで腫れ上がった虫歯の痛みが、肩にきたような感じで、手を触れられただけでも痛みを感じたものだ。
確かに今味わっている痛みがそうだ。
さて、脱臼もどきの症状だとしたらどうしたらいいのだろうか?
誰でも考えつくことは病院に行くことである。
しかし、ぼくは病院には行かない。
おそらくこの痛みは病院では治せないだろう。
レントゲン撮られて、痛み止めの注射を打たれ、「しばらく様子を見て、また痛くなったら来て下さい」と言われるのがオチだ。
こういう時は整体院なのだろうが、それも今のところ行っていない。
なるべくそういうところに行かずに、自力で治したいのだ。
ということで、最近肩の筋肉を鍛え始めた。
それは元横綱の千代の富士が、脱臼癖を克服するために筋肉を鍛えたということを何かの本で読んだからだ。
その本を読んだ時、ぼくは思わず膝を打った。
ぼくは若い頃激しい運動をやっていたのだが、一度も脱臼や骨折をしたことがない。
その理由を、今までぼくは「運が良かった」と思っていた。
が、よくよく考えてみると、それは少し違うような気がする。
その頃のぼくは筋肉隆々だった。
おそらく、怪我をしなかったのは、その隆々の筋肉が骨を守ってくれたおかげだったのだろう。
そういえば、「体が痛い」などと泣き言を言い出したのは、運動をやめてしばらく経ってから、つまり筋肉が萎えた頃からだった。
さて、今ダンベルや腕立て伏せで肩の筋肉を鍛えているのだが、そういった運動のあとには不思議と痛みが消えている。
腕をねじっても痛くないし、肘をついても痛くない。
だが、時間が経つとまた痛みが戻ってくる。
ということは、筋肉を往時に戻さない限り、痛みは完全に消えないということになる。
ダンベルや腕立て、競技も何もなしの地味な運動である。
飽きっぽいぼくが、どこまで続けることが出来るのか。
今は肩の痛みより、そちらのほうが心配である。
| 2004年06月28日(月) |
最近、金縛りに遭ってない |
ここ2週間ばかり金縛りに遭ってない。
少し前まで毎日のように金縛りに遭っていたのが嘘のようである。
しかも、その金縛りに遭っていた時によく聞こえていた、「バシッ!」というラップ音も聞こえなくなった。
ぼくは以前、この「金縛り」を疲労や寝不足からくるものだと思っていた。
確かに、疲れていた時や夜更かしした時に、金縛りに遭うことは多かった。
しかし、ここに来て「その認識は間違っていたのではないのか」と思うようになった。
その理由は、充分に休養をとっても金縛りに遭っているし、早く寝ても襲ってくることがあったからだ。
それに金縛りが疲れや夜更かしに関係あるのなら、ラップ音もそういうことと関係あるのだろうか?
ラップ音は幻聴とは違ったものである。
疲れているから、夜更かししたからと言って聞こえるものではない。
気力の充実した朝にも聞こえることもあるのだ。
ということで、今またぼくは、金縛りを霊現象だと思うようになった。
では、この2週間ばかり金縛りに遭ってないのは、何か特別なことをやっているからかといえば、そうではない。
2週間ばかり、詳しくいえば6月15日からである。
その前の数日間は、続けて金縛りに遭っていたのだが、その日を境にいくら寝不足であっても金縛りに遭わないのだ。
その日何があったのか。
今月16日の日記を読んでもらったらわかるが、15日にぼくは宗像大社に行っている。
実はこの時、二つのお札を買ったのだ。
一つは『天照大神』と書かれたお札で、もう一つは『宗像大社』と書かれたお札である。
いや、別に金縛りから逃れたくて、これらのお札を買ったのではない。
昨年だったか、嫁さんの姪からマンション用の神棚をもらっていたのだが、ずっと神様が不在だったのだ。
宗像大社に行った時、そのことを思い出して、お札を買ったわけである。
さっそく家に帰ってから神棚を取り付け、お札を奉った。
で、その夜から金縛りから解放されたのだ。
しかし、神社のお札にこういう力があるとは思ってもいなかった。
だいたい霊封じのお札というのは、梵字やお経が書かれていなければならないのだと思っていたのだが、どうもそうではないようだ。
そういえば、何年か前の年末に、母が交通事故に遭った。
その翌年の正月、一時退院した母と、宗像大社に厄払いに行った。
本殿に入った時だった。
急に母が「あれ?肩が軽くなった」と言った。
その感触はぼくにもあった。
知り合いに霊感の強い人がいるのだが、その人がかつて「宗像大社は非常に霊格が高い神社だ」と言っていたのを、その時思い出した。
おそらく、霊格の高い神社に入ったため、憑きものが取れたのだろう。
それほど霊格の高い神社のお札を寝室に奉ったため、金縛り霊が来なくなったのだろう。
そういえば、金縛りとは無関係なのだが、寝てる時に何かが寝室の入口から入ってきて、そのままぼくたちの上を通り西側の窓に抜けるようないう気配をよく感じていた。
ところが、最近はそれもなくなっている。
これもお札のおかげだと思いたい。
なぜなら、神棚を取り付けたのが西側の窓の上だからである。
さて、ぼくを金縛りに遭わせることの出来なくなった霊や、寝室を抜けていくに入ることの出来なくなった霊は、いったいどこに行ったのだろうか?
金縛りに遭ったり気配を感じたのはいつも夜中だった。
もしかしたら、行き場を失った霊は、この日記を通じて皆さんのところに行っているのかもしれない。
最近、浪曲などとともに、世間から遠ざかっている歌の一つに軍歌がある。
ぼくが子どもの頃は、ごく普通に歌われていた。
当時はカラオケなどなかったから、おっさんたちは酒が入ると手拍子で歌をうたっていたのだが、その時歌われていたものはほとんどが軍歌だった。
子どもの間にもそれは浸透していて、ぼくが小学生の頃には、友だちと「軍歌の中で何が一番好きか?」などと言っていたものだ。
一番多かったのは『加藤隼戦闘隊』だった。
ちなみにぼくが好きだったのは『麦と兵隊』だった。
これは母親が好きでよく歌っていたから、その影響を受けたのだろう。
また、ぼくが小さい頃に流行ったドラマやアニメの主題歌は、どう聴いても軍歌というものが多かった。
まあ、まだ軍歌からそう離れていない時代だったから、そうなったのだろうが。
その中でも『ゼロ戦ハヤト』の主題歌は、まさに軍歌と言っていいものだった。
この歌が戦時中に歌われていたとしても、別に違和感はなかっただろう。
軍歌はテレビのCMでもよく使われていた。
森永エールチョコレートの「大きいことはいいことだ〜♪」という歌があったが、ずっと後に何かの本で「あの歌の元は軍歌である」と書いてあったのを読んだことがある。
それを読んでぼくは「なるほど」とうなずいたものだ。
また、かつてこちらの九州電力のCMで、「煙も出ない、火も出ない、ガスも出ないし、汚れない〜♪」という歌が流れていたのだが、これは『勇敢なる水兵』の替え歌だった。
ぼくが高校の頃だったか、酒か何かのCMの中で、松村達雄が「遼陽城頭(りょうようじょうとう)夜はたけて〜」と歌っているシーンがはあったが、あれは印象的だった。
その歌『橘中佐』という歌は、あの頃けっこう流行ったような気がする。
高校野球の応援も軍歌が多かった。
『敵は幾万』なんかは今でもやっている。
しかし、今の高校生は、それが軍歌だということを知らないだろう。
なぜ今頃軍歌の話をするかといえば、実は昨日カラオケテープの卸元から『軍歌』のCDが入ってきた。
何が入っているのかと見てみると、ぼくが小さい頃に母が歌っていた歌がほとんどである。
『麦と兵隊』『紀元は二千六百年』『加藤隼戦闘隊』『空の神兵』『ラバウル小唄』『月月火水木金金』『雪の進軍』などなど。
中には、ぼくが中学の時に遠足で歌った『戦友』も入っていた。
そういうタイトルを見て、ふと昔を思い出したわけだ。
今時軍歌などと言い出すと、普通に引いてしまうものだ。
なぜなら、軍歌には戦争という負のイメージがあるからである。
しかし、それを言うなら、ロックだって元は不良の音楽だったし、矢沢永吉にいたってはヤンキーのカリスマ的存在である。
はたして今時、そういうイメージでロックや永ちゃんを聞く人がいるだろうか?
歌というものは文化なのだ。
時代背景がどうであれ、それをやっている人がどうであれ、いいものはいいのだ。
軍歌だってどんどん歌い続けていけばいいのだ。
きっと今の日本人が忘れている、『勇気』を与えてくれるだろうから。
【金さん殺害】
実は、痛ましい映像を見てしまった。
痛ましい映像とは、イラクの武装勢力に拉致された金鮮一さんの殺害シーンである。
テレビのニュースでは、犯人たちが声明文を読み上げているところで終わっているが、ネットではその後の映像が流れていた。
その後犯人たちは、金さんを蹴り倒し、体を押さえつけて、何か呪文のようなものを唱えながら、巧みに金さんの首を掻き斬った。
最後に犯人は、首を片手に何かわめき、その首を胴体に乗せた。
映像はそこで終わっていた。
実に残酷なシーンだった。
が、実にあっさりとしたものだった。
食事前に見たのでちょっと刺激が強かったものの、人間の首とはああも容易く取れるものなのかなどと、冷静なことをぼくは考えていた。
斬首シーンは時間的には比較的短いものだった。
しかし、その場に座らされてから息絶えるまでの金さんにとっては、長い長い恐怖の時間だったのだろう。
ご冥福をお祈りします。
【介錯】
現代では、首を斬るという行為は、残酷かつ野蛮ということになっているが、つい100年ちょっと前までは、日本でも頻繁に行われていた行為である。
江戸時代には打ち首という刑があった。
その首をさらすことを獄門と言った。
また、武士の世界には切腹という刑・自決法があった。
切腹の際、必ず介錯人というのがついたのだが、腹を切ったのを確認して、彼らは首をはねていた。
首を斬るのは、切腹した人を早く楽にさせるためだったという。
居合に、その『介錯』という型がある。
居合は「静中動ありの武術」だが、この『介錯』の時だけは静で行う。
それは介錯というのが、厳かな儀式であるからだ。
ちなみに、この介錯、一歩間違うと自分の身に被害が及ぶ。
間違いというのは、首を斬り落とした時である。
介錯には、首の皮一枚だけでも胴体と繋がっていなければならない、というルールがあったらしく、もし切り落としたりすると、今度はその介錯人が罪に問われることになる。
つまり、腹を切らなければならないのだ。
ということは、だ。
今回の武装勢力の斬首の場合、完全に首を切り落としていたから、日本式であれば、武装勢力は腹を切らなければならないことになる。
【巌頭和尚】
江戸時代、白隠という名僧がいた。
彼が大悟したきっかけが、実は斬首であった。
白隠は19歳の時に、唐の巌頭和尚が賊のために首を斬られ、数里に聞こえるような大きな叫び声を出して死んだという記事を読み、「仏門の修行をしても賊難でさえ避けることが出来ないではないか」と落胆する。
ところが、その5年後、暁の鐘の音を聞いて彼は大悟した。
その時白隠は、「巌頭和尚はまめ息災であったやわい」と叫んだという。
白隠が何を悟ったのかは知らない。
が、おそらく巌頭和尚の中に生死を超えたものを見たのだろう。
だからこそ「まめ息災」なのだ。
巌頭和尚は、生死を超えたところで首斬りを受け入れたということになろうか。
ということは、巌頭にとって賊の刃は、きっと春風が首をなでているようなものだったのだろう。
金さんの斬首シーンをハラハラしながら見ていたぼくには、その心境にはなれない。
こんばんみ〜。
今日は昨日の続きで〜す。
【6月22日『タマコの伝言』】
『「ORさんから皆さんへ」
まだ決まってはないみたいなんですけど、親戚の方が亡くなるみたいで、22日23日24日3日間(他の日になるかも…)休むそうです。
タマコが出たかったんですが、休みの日は用事が入ってるんで出れないんで、すみません。
またORさんから電話するみたいなので、、、。』
ORとは、タマコと同じ部門でバイトするタマコよりは九九が出来る分何ぼかマシな女子高生である。
この伝言はもちろんタマコが書いたのだが、普通なら『ORさんから、皆さんへ伝言でーす』などと書くはずである。
さすがにタマコでも、こういうことは真面目に書かないといけないと思ったのだろう。
が、それにしても変な伝言である。
『まだ決まってはないみたいなんですけど…』と、まるで旅行にでも行くような軽いノリ、それに加えて『親戚の方が亡くなるみたいで…』、おそらくタマコのことだから『危篤』という言葉を知らなかったのだろうが、すでに死ぬことを見通しているような書き方である。
捉えようによっては、予言とも思える。
ということは、タマコは会ったこともない、ORの親戚の方の死を予言していることになる。しかも日にち指定で。
天才タマコは予言者でもあったのだ。
さて、タマコが言っている『休みの日は用事が入ってる』ということだが、いったい何の用事だったのだろう。
翌日タマコにそのことを聞いてみると、何とその日はデートだったらしいのだ。
彼氏が家に遊びに来たらしい。
だが、疲れていたらしく、すぐに寝てしまったというのだ。
面白くないタマコは、しばらく一人でビデオを見ていたのだが、それも飽きて、眠っている彼氏にちょっかいをかけた。
ところが、それが原因でけんかになったという。
一時は別れ話まで出たらしいが、ほどなく仲直りしたらしい。
「よく彼氏が許してくれたのう。で、おまえ、何と言って仲直りしたんか?」
「何も言うてないよ。ただチューしただけ」
タマコには、『チュー』という言葉は似合わない。
【タマコの弱点】
タマコには弱点がある。
いや、脳が弱いということではない。
実は、タマコの鼻の下に、ニキビを潰した跡があるのだ。
最近潰したらしいのだが、タマコはそれを気にしている。
ぼくがその部分を見つけた時、なぜかタマコがソワソワしだした。
「もしかしたら」とぼくは思い、別の折に、その部分を見ていると、やはりタマコの様子がおかしい。
そこで、ぼくはタマコに聞いてみた。
「お前、そこどうしたんか?」
すると、タマコは急に真っ赤な顔をして「クーン」と犬の鳴くような声を上げて、逃げていった。
『これはいいことを知った』と思ったぼくは、それ以来タマコが大きな口を叩くたびに、その部分を凝視するようになった。
案の定タマコは大口を叩くのをやめ、頬を真っ赤に染め、何ともむず痒そうな顔をして逃げていく。
そろそろそのニキビの跡も目立たなくなってきているが、なるべくこちらが治ってないように振る舞って、タマコ・カードが途切れないようにしなければならない。
【6月15日、16日】
『こんばんみ〜。タマコの日記でぇ〜す。二日分の日記を書いちゃいます。
15日はバイトが14時〜20時までの勤務でしたぁ。
この日はしんた兄ちゃん(しんたさん)は休みだったので平和な一日でした。だけど、この日はかなり調子悪くて、テンションダウンでしたぁ。イライラの日でしたぁ。
16日今日は、私は朝学校に行ってピアノのレッスンをしましたよ。
ピアノは本当に難しいので大変だけど〜私は天才なので楽勝ですっっ(笑)バイトは五時半からで、相変わらずしんた兄ちゃんは私の事バカにしてる感じがするのですが、一番変な人はしんたさんなので…私はそれを理解してるんで大変です。まぁ今日はこんな感じです!!
以上タマコの日記でしたぁ。 ーおしまいー』
『こんばんみ〜』っちゃ何かのう?
こんな言葉が流行っているのか?
もしくはタマコ語なのか?
後日そのことをタマコに聞いてみた。
正解はタマコ語だった。
友だちへのメールは、いつも『こんばんみ〜』から始めているらしい。
これをもらった友だちは、「やっぱりタマコって…」と思っていることだろう。
あ、そうだった!
この日記はメールでぼく宛に届いたものである。
ということは、タマコはぼくのことを『友だち』と思っているのだろうか?
それは困る。大いに困る。
いや、別に若い子からメールが届くのが困るのではない。
タマコがぼくのことを、友だちと同等に扱っていることが困るのである。
もしかたらタマコは、ぼくも『こんばんみ〜』などと言っていると思っているのではないだろうか?
ところで、ピアノのレッスンで学校に行くのはいいけど、先生に迷惑かけてないだろうか。
それが心配である。
あ、もしかしたら、ピアノの先生もぼくたちみたいに、タマコに「これなんて読むか知ってる?」などと言っているのかもしれない。
【6月19日】
『こんにちは。タマコです。台風が近ずいて来てますねぇ。今日は14〜20までのバイトだったのですが、かなりひまでした。客さんはすくないし、、、。だけん、日記も書くことがあんまし無いです。
なので、、、今日はおしまい、、、。
IQ200タマちん
本当はIQ200以上☆
{天才の中の天才}』
「ず」は、「づ」やろうが!
しかし、前日の日記で、ようやくタマコは24時間の使い方を覚えたのかと思っていたのに、またこの日は『14〜20』と書いている。
これでは、初めて読んだ人には、この数字が何なのかよくわからないだろう。
ところで、この子はいったい何の天才なんだろう?
おそらく天才の意味も知らないで使っているのだろう。
ついでにIQの意味も。
【6月20日】
『今日は、10:00〜14までの勤務でした。明日には台風が来るみたいだけど、バイトが14〜あるので大変。
今日は、バイト終わって、ピアノの練習します。
ベートーベン並みにプロ級なので練習する必要ないけど、今日はヒマ②なのでします。
皆さん台風には注意して下さいね。。』
ベートーベン並みのプロ級なら、何も幼稚園の先生を目指さなくても、ピアノや作曲だけで充分に食っていけるはずである。
それにそれだけうまいのなら、逆に先生を教えているはずだ。
タマコ、だんだんボロを出す。
| 2004年06月23日(水) |
何が「社会党に入れてくれんか?」だ! |
選挙のたびに思い出すことがある。
それは高校2年生の時のことだ。
その当時ぼくは、担任との仲がすこぶる悪かった。
担任はクラスで何か事が起きると、すべてぼく絡みだと決めつけていた。
簡単に言えば、担任はぼくを不良だと思っていたわけだ。
おかげで、父兄会の時、ぼくの母は他の誰よりも時間が長くかかったという。
担任はその時、母に面と向かって、
「おたくの息子さんが、クラスで一番素行が悪い」
と言ったそうだ。
当然母は憤慨して家に帰ってきた。
が、憤慨していたのはぼくに対してではなく、担任に対してだった。
「いくらあんたの素行が悪くても、言い方というものがあるやろ!」
と言っていた。
そういうことがあって、ぼくは担任に対して『嫌い』を通り越し、敵愾心まで抱くようになった。
担任もそれに気づいたのだろう。より以上に、ぼくに対する態度が硬化した。
ところが、そういう担任が一度だけぼくに笑顔を向けたことがあった。
参院選前のことだった。
ぼくが廊下を歩いていると、向こうから担任がやって来た。
担任はぼくを見つけると、急に笑顔になって、珍しくぼくに声をかけてきた。
「おい、しんた」
妙に上機嫌である。
「ちょっと話しがあるんやけど、いいか?」
そう言って彼は、ぼくを物理室に連れ込んだ。
「まあ、座れ」
ぼくは一瞬『何かやらかしたかなあ?』と思ったが、思い当たることがない。
「何ですか?」
「いや、他でもないんやけど…」
「?」
「お前んとこ母ちゃん、どこか支持政党あるんかのう?」
「えっ、知りませんけど、何か?」
「実は今度の参院選のことなんやけど…」
「参院選?」
「ああ。お前から社会党(現社民党)に入れるように言ってもらえんかのう?」
「えっ?」
「いや、無理にとは言わんけど」
ぼくはまだ若かった。
こういう時、何と答えていいのかわからない。
ぼくが躊躇しているのを見て、担任は
「あっ、そうか。お前んとこは新日鐵やったのう」
「はあ…」
「じゃあ、だめかぁ」
「えっ?」
「いや、いい。新日鐵は民社党(現いちおう民主党か?)やったか。そうかそうか…」
「・・・」
「あ、悪かったのう。もういい」
そう言うと担任はさっさと物理室を出て行った。
ふざけた男である。
そういうことに生徒を利用しなくてもいいじゃないか。
父兄会の時と同じように、面と向かって「社会党に入れて下さい」と母に頼み込めばいいのだ。
確かに母は新日鐵に勤めてはいたが、会社の支持政党である民社党はけなしていたのだ。
それ以来、ぼくと担任の溝はいっそう深くなった。
重ねて、こういうことをやらせる社会党も日教組も大嫌いになった。
それが現在まで続いている。
「参議院選か。ということは、またあれが始まるのか」
今日はそんなことを思いながら家にいた。
「あれ」とは、ご無沙汰電話のことである。
以前、古い友人から突然の電話をもらったことがある。
「はい、しんたですが」
「おお、しんたかぁ!」
「えっ…」と、ぼくは電話の前で困った笑みを浮かべた。
あまり聞き慣れない声なのである。
「えーっと…」
「ああ、おれおれ」
「『おれ』…??」
「○○よ。○○」
「○○…さん?」
「前に一緒にバイトしてた」
「ああ、ああ!○○ね。久しぶりやのう」
「いやね、電話帳めくっていたら、しんたの名前を見つけてねぇ。懐かしくなって電話してみたんよ。元気か?」
「おかげさまで」
「奥さんは…。ああ、しんた結婚しとったんかのう?」
「いちおうね」
「そうか。あの時の彼女か?」
「ああ」
それからお互いの近況報告をし、昔の話に花が咲いた。
彼は「今度飲みに行こう」と言ったあと、間を置いて「ところで…」と話を変えた。
「今度選挙があるやろう」
「ああ」
「誰か入れる人決まっとるか?」
「いや、別に決まってないけど…」
「そうか。じゃあ××さんに入れてくれんかのう」
「××さん?」
「おう、公明党の」
ということで、この電話は『懐かしくなってかけた』ものでないことが判明した。
それと併せて、○○が学会さんだということも判明した。
もちろん「飲みに行こう」は口実である。
なぜなら、それから選挙のたびに電話が入るようになったのだが、一度も飲みに行ったことがないからだ。
嫁さんにも同じような経験があるらしい。
電話をかけてきたのは嫁さんの高校時代の同級生だった。
彼女は唐突に「選挙行くやろ?」と言った。
そこで嫁さんが「いや、その日は8時から仕事やけ行かれん」と答えると、その人は「じゃあその日、私が会社まで送っていく」と言う。
嫁さんが『おかしなこと言う人やね』と思っていると、彼女は「だから、会社に行く前に、選挙につきあって。で、公明党の××さんに入れてくれん?」
と言ったらしい。
電話を切ったあと嫁さんは、「大人しい人やったけど、まさか学会の人だとは思わんかった」と言っていた。
「迎えに来てくれるなら、いいやないか。別に××に入れんでもいいんやけ」
「よくないよ」
「で、その人どこに住んどるんか?」
「下関」
「えっ…」
海の向こうである。
嫁さんが会社に出る前に向かえに来る、しかもその前に選挙に行くとなると、彼女は6時過ぎに家を出なければならない。
熱心な信者さんである。
ということで、まもなくぼくと嫁さんにこの二人から電話がかかる。
| 2004年06月21日(月) |
共産党さん、「チラシを入れないでくれ」と言っておいたでしょ! |
「参議院選か。ということは、またチラシ攻撃が始まるのか」
そんなことを思いながら家に帰ってみると、さっそくポストに入っていた。
表紙に、−こんにちは 日本共産党です−、と書いてある、ぼくが一番見たくない党のパンフレットだった。
その場で破って捨てようかと思った。
が、思い直して家まで持ってきた。
「日記のネタにしてやれ」と考えたのである。
そのパンフレットの2ページ目は、
−日本共産党は こういう日本をめざします−
である。
日本を陥落させようとしている売国党には、もう日本という言葉は無かったんじゃないのか。
しかも、『国民が主人公』と書いている。
えーっと、おたくは『国民』じゃなく、『地球市民』じゃなかったっけ?
都合のいい時だけ、『国民』という言葉を使わないでほしいものだ。
しかし、このパンフレットはわざとらしく『国民』という言葉を多用している。
ふざけるな、である。
さて、注目したのは『外交』のページだった。
−安保条約をなくし、独立・平和・非同盟の道をすすみます−
『平和外交にとりくみ、非同盟・中立の流れに合流する』
と言っているが、平和外交とは中国・韓国・北朝鮮という馬鹿三国にひざまずく外交のことを言っているのか?
すべての国に、「先の戦争では、多大なるご迷惑を…」と謝罪することを言っているのか?
さらに『憲法9条の完全実施にすすむ』である。
非同盟の上、自衛隊の軍縮ときている。
もし外国からテロ攻撃を受けた時、いったい誰がどうやって国を守るのだろうか?
よく言われているように、一国平和なんていうのは絵空事にすぎないのだ。
彼らが好む言葉、「話し合いましょうよ」で、いったい何が解決するというのだろう。
実際の話、銃を持っている人間を目の前にした時、「話し合いましょうよ」と言える人間が何人いるというのだろう。
丸腰相手、しかも味方が多数いるからこそ、居丈高に「話し合いましょうよ」と詰め寄ることが出来るのだ。
映画『ダイ・ハード』で、「交渉してくる」と言って、犯人グループのもとに話し合いにいった人間がいたが、確か殺されたんだったよなあ。
世の中、そうは甘くない。
話し合いで片を付けようとする場合は、相手に何らかのメリットを与えないことには無理なのである。
そのメリットについて、売国夢見党の共産党さんは、どういうお考えを持っておられますか?
最後に、『未来』というページ。
−人間の自由・個性が花ひらく社会へ−
あのう、中国と、北朝鮮はいまだ共産主義なんですが、いったいどこに『人間の自由』といったものがあるんでしょうか?
さらに北朝鮮に関しては、『個性』も認めていない。
あの国にあるのは、金正日の個性だけである。
さすが絵空事の好きな売国夢見党、現実が見えていない。
さて、このパンフレットだが、これは例の『マニフェスト』なるものなんだろうか?
ああ、そうか。
元々『マニフェスト』というのは、共産党宣言のことだった。
ということは、『マニフェスト』で間違いないのか。
台風6号が近づいている。
が、こちら北九州のほうは天気予報が外れ、終日快晴の日曜日だった。
しかし日差しが強く、最高気温37度という暑い一日となった。
で、風のほうはというと、多少はあったものの昨日ほどではなかった。
ぼくの売場にはテレビが置いてあるため、仕事中に他の売場の人が何度も「台風はどうなった?」と聞いてきた。
が、テレビが置いてあるとはいえ、テレビを見ているわけではない。
それにいつ天気予報をやっているのかを、ぼくは知らない。
そこで「知らん」と答えると、「じゃあ、見とって」と簡単に言う。
しかたなく、今日は暇が出来たらテレビを見るように心がけていた。
が、なかなかその暇が出来ない。
時折、テレビの前に行ってみたが、ニュースなどやっていない。
やっていたのは、ダイエーの負け試合や、競馬やゴルフだった。
台風情報に出くわしたのは、夕方の5時半を過ぎた頃だった。。
NHKで、現在の台風状況と予想進路図が映っていたのだ。
その予想進路図を見ると、今回の台風は鹿児島から直接四国に抜けるルートのようだ。
ということは、北部九州への直撃はない。
せっかく台風対策を充分にやっていたのに、またしても台風に振られることとなった。
北部九州というのは、全国の人が思っているよりも、ずっと台風の少ない地域である。
年に何度か鹿児島から九州に上陸し、そのまま北上する台風があるのだが、その台風は、途中で阿蘇山や九重連山などに遮られ、北上出来ない。
遮られた台風がどこに行くのかというと、東向きに進路を変える。
つまり豊後水道方面に向かうのだ。
そして、四国に抜ける。
ということで、多少風の影響はあるものの、北部九州に直撃することはない。
ちなみに北部九州を直撃するルートは、東シナ海から対馬海峡に向かうルートである。
平成3年、北部九州や東北地方に大被害を及ぼした台風19号は、このルートを通っている。
元寇の時に吹いた『神風』も、おそらくこのルートを通ったのだろう。
7時を過ぎて、ぼくはタバコを吸いに外に出た。
明日が夏至ということもあって、空はまだまだ明るかった。
で、風のほうはというと、さほどでもない。
少し風が強いかな、という程度だった。
「もしかして進路を変えて、こちらに向かっているのか!?」と思ったのは、帰宅時間である8時を過ぎた頃だった。
7時の風よりはるかにひどくなっていたのだ。
運転中、何度かハンドルを取られそうになった。
道上を舞い上がる紙くずも、「台風近し」の演出をしている。
しかし、その風もそう長くは続かなかった。
10時にコンビニに行った時には、7時の風に戻っていた。
で、今はというと、生ぬるい風が吹いている、が、強い風ではない。
予想進路図を見ると、台風は明日の午前6時頃に、関門に接近するらしい。
が、その時間、ぼくは夢の中である。
会社に行く頃には、風もやんでいることだろう。

(6月20日午後7時の北九州の空)
| 2004年06月19日(土) |
それでもぼくはタバコを吸う |
今日の朝礼で店長タカシが、
「今まで休憩室は時間を区切って禁煙にしていましたが、これからは時間に関係なく終日禁煙にします。尚、どうしても吸いたい人は外にバケツを用意しておりますので、そこで吸って下さい」
と、宣言した。
現在うちの店には5人の男子社員がいるのだが、店長タカシ以外はみんなタバコを吸う。
それを店長タカシは苦々しく思っていた。
と同時に、自分だけ仲間外れにされている気分になっていた、と思う。
しかし彼は小心者だから、面と向かって「みんなで禁煙しましょうや」とは言えない。
そういう時、安全週間に向けての各店の取り組み方を紹介したパンフレットが回ってきた。
そこに、ある店の事例として「完全禁煙を実施」ということが書いてあった。
それを見た店長タカシは、「これだ!」と思った。
そしてこの事例をうちでも採用しようと、他の社員に何の相談もなしに勝手に決めたのだ。
安全週間の事例を楯に取って、「よそがやってることですから」と店内完全禁煙を断行するとは、卑怯な男である。
調子に乗った店長タカシは、さらに続けた。
「タバコを吸っている人は、このさい禁煙したどうですか。体にも悪いし」
ふざけるな、である。
タバコが体に悪いと、誰が決めたのだ?
ぼくの祖父や叔父は、タバコを止めた途端に死んでしまっている。
友人や知人からも、こういう話はよく聞いている。
「タバコは体に悪い」、そんな無責任なことを言って、もしそれが原因で寿命が縮まったとしたら、禁煙を推進する人たちは、いったいどう責任をとってくれるのだろうか。
例えば、医者が「体に悪いから、タバコをやめなさい」と言ってきたら、念書をとっておかねばならない。
『喫煙』『禁煙』、この問題については、この日記でも何度か書いている。
その件で、ぼくは会社の担当医に、
「嫌煙権というものが認められるなら、喫煙権も認められていいんじゃないですか」
と、噛みついたこともある。
その時は、
「それなら、換気扇のあるところに、ビニールのカーテンをつけて、そこで吸うようにして下さい」
ということで話はまとまった。
が、そのことを担当医から指示された店長タカシは、何も行動を起こさなかった。
結局2年近くそれまで通りとなっていた。
ようやく腰を上げたと思ったら、この仕打ちである。
だいたい禁煙を勧める医者なんていうのは、ろくな奴がいない。
そうでしょ?
彼らが「体に悪い」としている根拠は、すべてが体調を崩した患者のデータなのだから。
それほどタバコをやめさせたいのなら、自分が実験台になってみるべきである。
自らがタバコを吸ってみて、タバコを吸ったがためにどういう障害が起きたのか、また、タバコをやめた時に体調がどう好転したのか、などということをつぶさに調べて報告しないことには、喫煙者は納得しないだろう。
それが出来ないのなら、人の嗜好にケチをつけ、「体に悪い」などという脅しをかけるような真似はやめるべきである。
それに本当の医者なら、タバコをやめさせずに体を治すことを考えるはずだ。
しかし、おかしい。
安全週間なのに、どうして禁煙なんだろう?
そういうことは、衛生週間の時にやるべき事柄じゃないか。
安全週間なら、
「タバコを吸う方は、安全のため、火の後始末をちゃんとやって下さい」
で、いいじゃないか。
今日、たまたま読んだマンガの本に、こんなことが書いてあった。
『彼は朝鮮人で、李さんといい、奥さんと子ども二人があるそうだ。
彼のかもし出すムードにのまれてしまったのか、大法螺に惑わされてしまったものなのか、一家四人がいつのまにか二階の六畳に住みついてしまったのだ。
李さんには定職がなく、おまけにそうとうな怠け者なので、生活はかなり苦しいらしい。
それは僕が作ったキューリを時たま奥さんが失敬して行くのを見てもわかる』(つげ義春「李さん一家」より)
昨日の日記で、竹島のことを書いたついでに、ぼくが知っている範囲の朝鮮人の性格を書いたのだが、つげさんも朝鮮人李さんの性格を同じように見ていたということになる。
おそらくこれが一般的な朝鮮人気質なのだろう。
では、日本人の気質はどうなのか。
終戦後、台湾に渡った蒋介石たちは、彼の地でさんざんひどいことをやったらしい。
その当時の台湾の人たちは、『犬去って豚来る』と言ったそうだ。
台湾の人たちは、日本人を『犬』と見ていたのである。
また満州国時代から満州地方に住んでいる人は、「日本人は一般に真面目で勤勉だった。口やかましいけどやることやっていたら何も言いませんでしたよ」と言っていたらしい。
『口やかましい』=『よく吠える』、やはりイメージとしては『犬』に近いものがある。
かつて欧米人は『狐』というイメージで日本人を見ていた。
つまり、日本人が「ずるい人種」に見えていたのだ。
が、それは違う。
自分たちがさぼっている間にも、日本人は働いていたから、当然業績が上がる。
きっと欧米人は、自分たちが休んでいる時も日本人が働いていることを知らず、いつも日本人の業績がいいのは、何か裏で悪いことをやっているからだとでも思っていたのだろう。
元々欧米人は仕事を『贖罪』と捉えているのだから、仕事を『道』として捉えている日本人が理解出来ないのだ。
つまり、欧米人はキリギリスであり、日本人はアリというわけである。
もし彼らが日本人を理解しようと思うなら、日本の歴史や宗教を深く研究しないとならない。
歴史といっても、日本の歴史を「搾取の歴史」だとか「侵略の歴史」などというふうに見ていては、どれだけ時間を費やしても、日本人というのは見えてこないだろう。
日本人でも、教科書に書いてある歴史を絶対だと思っている人や、首相が靖国神社に参拝するたびに文句を言っている人たちは、日本人というのが見えてないのだから。
そういえば、日本人が世界の人に理解されない理由の一つに、『暴走癖』というのがある。
いったん走り出すと、周りが見えなくなり、気がついたら取り返しのつかないことになっているのだ。
それをやるのは、決まって頭がいいと言われる馬鹿たちだ。
彼らは「自分たちはいいことをやっている」としか思ってないから、始末が悪い。
誰のことを言っているのかと言えば、昔なら陸軍、今は左翼である。
彼らは国の方針というものを、全く無視して、自分たちの信じる「いいこと」を追求していく。
そのため他国の人たちから、「言うこととやることが全く違うじゃないか」ということになる。
昔陸軍がそれをやったため、日本のイメージが悪くなり、結局戦争を避けられなくなったのだ。
今また左翼たちが暴走し、日本のイメージを悪くしようとしている。
いったい、左翼たちがやっている暴走とは何か?
それは、謝罪である。
国家間では終わっている問題を、くどくどと蒸し返しているのだ。
※ホ−ムページから日記を開く際、メニューをクリックするのが面倒な方は、トップページのタイトルロゴをクリックして下さい。最新日記に飛びます。
| 2004年06月17日(木) |
金さん、李さん、そこはうちの土地だ |
何日か前の新聞に、韓国の海運会社が竹島に毎日観光船を運行すると発表した、という記事が載っていた。
その会社の社長は、生意気にも「日本人も金を払ったら乗せてやる」と言ったそうだ。
昨日も言ったが、竹島は日本の固有の領土である。
それを盗っ人猛々しい韓国国家は、勝手に『独島』と名づけ、自国の領土だと言い張っているのだ。
喩えて言えば、金さんや李さんが、勝手にうちの庭で商売を始めた、ということである。
そういう場合、その家主は文句を言って追い出すはずだ。
しかし、相手が国家となると、対応が違ってくる。
「また韓国か。言っても聞かんだろうし、また過去のことを言い出すとうるさいから、知らん顔しておこう」
と、見て見ぬふりをするのだ。
排他的経済水域を侵犯した韓国漁船に催眠弾を撃ち込むなど、ようやく普通の国家らしいことをやりだしたのに、何で竹島に関しては及び腰になるのだろう。
たとえそれが観光船であったにせよ、領海を侵すものは漁船と同じように脅しをかけてやればいいのだ。
それでもし韓国側が文句を言ってきたら、国交を断絶してやればいい。
そうなって困るのは、日本の後押しがなければ歩いて行けない韓国のほうだ。
こちらは何も困らない。
しかし、どうして韓国は日本に対して居丈高なのだろう。
日本人の大半が在日だと言うし、日本の伝統的なものはすべて韓国起源だと言い張るし、日本のアニメも韓国のオリジナルにしてしまっている。
こちらから見ると、日本コンプレックスが見え見えなのだが、そういうことすらも彼の国の人はわかっていらっしゃらないようだ。
韓国といえば、かつては日本人から尊敬される国だった。
朝鮮出身といえば良家の人と捉えられていた、ということからもそのことがわかる。
しかし、それは江戸時代までの話で、明治以降韓国の内情がわかるに連れて、日本人から尊敬の念が消えていった。
その内情とは、世界一だらしない国だったということだ。
とはいえ、中にはちゃんとした人もいたのだ。
が、いかんせん大多数がだらしない
仕事をする気力がない。
盗賊が多く、ゆすりたかりを繰り返し、要求を拒めば村全体に火を放つ。
一族の中に成功者が出ると、一族の者は仕事もせずにその人の家に居候する。
こんな有様だった。
で、現在はどうかというと…
個人的にどうかは知らないが、日本の功績を自分の功績にすり替える。
島を盗む。土地を盗む。
文句を言えば、「差別だ」と騒ぎ、謝罪と賠償を要求する。
何かと言えば、日の丸を燃やしたがる。
東アジアの成功者である日本に依存し、ことあれば金を引き出そうとする。
そしてしつこい。
やはり祖先の血である。
100年以上も経った今日でさえ、この性格は変わらないのだ。
こういう国とつきあっていくのは、本当に疲れる。
出来ることなら、こういう人たちとは関わりたくないのが本音である。
友好というのも空々しい。
確かに、在日の人の中には立派な人も、いい人もたくさんいる。
また、ぼくは在日のおばさんたちと話す機会も多いのだが、口に泡を飛ばして一方的にしゃべり続けるおばさんたちは、ユーモラスで親しみさえも持てる。
が、それはその人たちが、ぼくたち日本人と同じ水を飲み、同じ物を食べ、同じ文化を味わっているからこそ、そういうふうに受けとめられるのだ。
問題は、海の向こうの韓国なのである。
竹島を守る、何かいい手立てはないものだろうか。
| 2004年06月16日(水) |
日露戦争から100年か |
『敵艦見ゆとの警報に接し、連合艦隊はただちに出動、これを撃滅せんとす。本日天気晴朗なれど波高し』
『皇国の興廃この一戦にあり。各人いっそう奮励努力せよ』
前にも書いたかなあ。
まあ、何度書いてもいいや。
まさに名文である。
これほど日本人の血を沸かす言葉はないだろう。
実は昨日、宗像大社に行ってきた。
「東郷元帥の言葉が、どうして宗像大社と繋がるのか?」
と思われる方もいるかもしれない。
いや、大いに関係あるのだ。
司馬遼太郎の『坂の上の雲』に、日本海海戦が火ぶたを切った時のことを、玄界灘上にある宗像大社沖津宮(沖ノ島)の神職宗像繁丸の付き人佐藤市五郎の談として紹介している。
『・・・宗像繁丸が受話器をとりあげると「バルチック艦隊が沖ノ島近海にせまった」という望楼の水兵の声がとびこみ、すぐ切られた。宗像は突ったったままみるみる血相が変わり、その場で褌一本の素っ裸になった。「市五郎、来い」というなり、海岸へ駆けおり、岩の上から海へとびこみ、潔斎をしたあと装束をつけ、社殿へかけのぼった。坂をのぼりつめたとき、西南の沖にあたって、濛気がピカッと輝いて消えた。そのあと、身のすくむような砲声がきこえた。・・・・。
宗像は神殿で懸命に祝詞をあげた。その間、砲声が矢つぎばやにひびいた。・・・』
つまり、日本海海戦は宗像大社のすぐそばで行われたのだ。
今年は日露戦争開戦100周年である。
日本海海戦は、その翌年の5月27日だったから、もしかしたら来年のその日、何か催し物が行われるかもしれないと思い、寄ってみたのだ。
しかし、そこでもらったパンフレットには、今年の行事しか書かれていなかった。
まあ、八幡様のような戦の神様ではないのだから、何もなくてもしかたがない。
だが、宗像の神様は日本海海戦を知る唯一の神様なのだから、ぜひともやってもらいたい行事ではある。
それはそうと、日露戦争からたった100年しか経ってないのか。
もうとっくに100年以上過ぎていると思っていた。
しかし、学生時代に日本史で覚えた年号は、確かに1904年だった。
ということは、年号を時代と関連づけて覚えずに、ただ暗記の対象として覚えていただけということになる。
つまり、点数とるだけの勉強をやっていたということか。
実に味気ないものである。
さて、その日露戦争で手に入れたのが、南樺太だった。
その後韓国と合併し、一等国の仲間入りを果たした。
しかし、日露戦争から40年後、対米戦に敗れたために韓国や台湾は日本の手から離れ、南樺太はソ連に戻った。
が、それだけでは終わらなかった。
千島列島を盗まれたのだ。
そのため、今の日本の領土は、日清戦争以前より、実質的には減っているのだ。
まあ、韓国や台湾に関しては、行く行くは独立させるものだったから、その期日が早まっただけの話だが、千島列島は明治以来の日本の領土である。
明治以来、ご先祖様が必至に守ってきた領土なのに、一体何と言ってお詫びしたらいいのだろう。
このままではいけない。
何とかして泥棒国家のロシアから千島列島を取り戻し、同じく泥棒国家である中国から尖閣諸島を、その子分である韓国から竹島を、死守しなければならない。
宗像の本殿に参り、その力添えをお願いしてきた。
【1】
『皆さん初めまして、タマコです。
しんたさんが変な事ばかり書いていますが、あれはウソです。
本当の事は、幼稚園の先生をめざしている事だけです。
私は本当はIQ200ぐらいの天才で、都会育ちやし、全くパーフェクトの女なんで、しんたさんが言ってる事は信じないで下さいね。
タマちゃん』
算数や国語のテストの後、ぼくはタマコの文章力を見てやろうと思い、タマコに、
「これから毎日日記を書いてこい」
と言った。
「日記書いてどうするんですか?」
とタマコが聞くので、ぼくは、
「ホームページに載せて、おまえの馬鹿さ加減を、全国の人に知らせてやる」
と言った。
その結果が、上の日記である。
そうか。
これが、「IQ200ぐらいの天才」が書く文章なのか。
見習わなくてはいけない。
天才の文章は、「都会育ちやし」などと標準語の中にさりげなく方言を入れていくのか。
これは勉強になるわい。
ちなみにタマコの言う「都会」というのは、パチンコ屋のネオンがギラギラしているところである。
【2】
『6月12日
今日は1:30〜20までのバイトでした。
T子さんと一緒に働きました。
T子さんは、はっきり言っておかしい人です。
私とかマジでまともです。
T子さんは、いきなり「あっ、そうそう」などと言い出したり、時々変な事を真顔で話したりします。
だから、私より大先輩だけど、一緒に働いている時は、私がT子さんをまとめています。
だけど、そんなおかしなT子さんは、私は好きです』
「1:30」と書いているくらいだから、「20」というのは、おそらく「20:00」ということなのだろう。
ということは、彼女は1時半から20時まで仕事をしたことになる。
6月12日と言えば、先週の土曜日だが、あの日タマコはいつ寝たのだろう。
まあ、タマコは元気いっぱい油を売っていたから、きっと2,3日寝なくても大丈夫なんだろう。
しかし、ぼくの会社では、こんな長時間の労働は認めていない。
というより、店の営業時間は「10:00〜20:00」なので、当然「1:30」に店は開いてない。
いったい、タマコは1時半から10時までの8時間半、どこで仕事をしていたのだろう。
【3】
ところで、先日、「七夕の飾り付けをするので、短冊に何か書いてくれ」と頼まれた。
別に、ぼくは願い事があるわけでもない。
いったんは「書くことがない」と辞退したのだが、「数が足りない」としつこく頼むので、渋々短冊書きを引き受けた。
「さて、何を書こうか?」と、いろいろ悩んだ末、あることを思いついた。
「ああ、あれがあった!」
ということで、「あれ」を書いた。
『タマコが無事幼稚園に入園出来ますように』
タマコは今21歳。幼稚園の先生を目指している。
ぼくはスポニチのメールマガジンをとっているのだが、昨日の内容には唖然とさせられた。
昨日の夜からさんざんニュースで流れている、『オリックスと近鉄の合併』である。
ぼくは毎朝『とくダネ!』を見ているのだが、今日はそのニュースがトップで取り上げられていた。
西武ファン(パ・リーグファンでもあるのか?)である司会の小倉さんも、このことには嘆いていた。
いったいパ・リーグはどうなってしまうのだろう。
このまま放っておくと、来季から5球団で闘わなければならない。
今季からクソ面白くもないプレーオフ制度を導入したばかりだ。
もし5球団で闘わなければならなくなるとすれば、3球団で闘うプレーオフに、ファンはどういう意味を見いだせばいいのだろうか。
ここ数年、西武に加えてダイエーも常勝軍団に名乗りを上げたが、これでようやく往年の好カードであったH-L戦が復元され、パ・リーグの目玉になるはずだったのに、その期待もぶちこわしになってしまう。
これではますますパ・リーグ離れが進むばかりである。
はっきり言って5球団ではだめだ。
1シーズンに1球団との対戦を28試合とすれば、5球団制では112試合になってしまう。
今までが140試合だったのだから、この試合数で優勝したとしても、素直に喜べないし、球団としても収入減は必至である。
しかも、この球団数だと、当然いつもどこかのチームがオフになる。
そうなると、球場の収入減も避けられない。
そのうち、また1球団減るといった事態にもなりかねない。
いったいパ・リーグの会長だとかコミッショナーだとかは、やる気があるのだろうか。
「知恵を絞って」だと?
知恵を絞った結果が、くだらんプレーオフ導入であり、今回の合併騒ぎだったわけじゃないか。
試合数が減って、動員数が減って、収入が減って、面白みがなくなる。
嫌気がさした選手は、FAを行使し、セ・リーグやメジャーに去っていく。
悪いことづくしの「知恵」しか出せない関係者こそ去ってしかるべきである。
「こうなった以上1リーグ制にするしかない」という意見がある。
当然数合わせのためにもう1球団減らして10球団で編成していくことになるのだろうが、仮にそうなったとして、先に書いた試合数だと年間252試合戦わなければならない。
実際この試合数をこなすことは可能なのだろうか。
もし、現状の試合数である140試合を目安にするなら、対1球団15〜16試合となるわけだが、これだと巨人戦に頼ってきたセ・リーグのチームの収入減は避けられない。
そのうち、どこかのチームが脱落して、ゆくゆくは8球団となり、あげくに6球団になってしまうかもしれない。
そうなると、プロ野球界はますます狭き門になってしまい、おのずと野球人口も減っていく結果になるだろう。
ということは、プロ野球界、いや野球界全体のためにも、2リーグ制は残しておかなければならない。
しかし、パ・リーグだけ5球団だと、先に書いたとおりの結果になってしまう。
こうなったら、セ・リーグにも1球団減らしてもらうしかない。
セパ共に5球団体制でやっていくのだ。
当然いつも試合のないチームがセパ1チームずつ出てくるわけだから、そのチーム同士で交流試合をしていけばいい。
その試合もペナントの成績に加味していけば、いかに交流試合といえど真剣に戦わざるを得なくなる。
こうすれば興行収入も増えるし、仮にそれが巨人戦だったら莫大な放映権の収入も入ってくる。
これで少しは、パ・リーグ球団が抱える赤字も減っていくのではないだろうか。
しかし、一番いいのは今までどおり両リーグ6球団制である。
この体制になったのは昭和33年からというから、もう46年も続いていることになる。
ということは、これが日本という国の、身の丈に合ったプロ野球の姿ではないのだろうか。
今日は快晴だった。
外に出ると、紫外線が強いせいか、目を開けているのが辛いくらいだった。
この天気と南よりの風が吹いて、初めて真夏となるのだろうが、今日は北東の風が吹いたためか、風は少し冷たく感じた。
もし梅雨というものがなかったとしたら、6月というはきっと今日のような気候なのだろう。
こういう日は決まってのどが渇く。
天候もさることながら、店の中がエアコンの効きすぎで乾燥してしまっていたためだ。
のどが渇くといえば、ぼくたちが子供の頃は、のどが渇くと水道の蛇口に口をつけてがぶ飲みしていたものだった。
これがかなりおいしかったような記憶がある。
確かにその当時からジュースやコーラはあった。
しかし、お小遣いが10円20円の子供には高嶺の花だった。
必然的にのどが渇くと、水を飲むことになる。
しかし、その当時の水が本当においしかったのかどうかは疑問である。
さして今と代わりはなかったのではないだろうか。
水質も今より良かったとは言い難い。
雨が降ると水が濁ったし、カルキー白さは今よりも顕著だったし、時には赤茶けた水も出ていたものだ。
浄水器もなかった。
それでもおいしく感じたのは、きっと本当に渇いてからだろう。
ところで、今日はあまりにものどが渇いたので、滅多と飲まない清涼飲料水を3本も買ってしまった。
昼食で飲んだカテキン茶を含めると、今日は持ち金の半分以上を飲料水に費やしたことになる。
そのうちの一本が、緑茶(まろ茶系の新製品)だったのだが、その缶の裏に雑学コーナーのようなものがあった。
そこには、
「1960年代に、お金を入れてコーラのビンをそのまま引き抜く『手動販売機』なるものがあった」
というようなことが書かれていた。
あったあった、ありましたよ。
たしか、その手動販売機は2つのタイプがあったように記憶している。
縦型と横型と言ったらいいか。
縦型とは、今の自動販売機のようなもので、コーラを横に寝かせて置いてあった。
また横型とは、どでかいクーラーボックスのようなもので、コーラは立てた状態で置いてあった。
ぼくがよく利用したのは後者のほうだった。
中学の頃、柔道場に通っていたのだが、そこにそのどでかいクーラーボックスが置いてあったのだ。
フタを開けて、お金を入れて、引き抜くのだ。
柔道をやった後のコーラは、また格別なものがあった。
ところが、その手動販売機はすぐに撤去された。
理由は、そのコーラの置き方にあった。
立てて置いてあったと書いたが、コーラのビンは飲み口の下に出っ張りがあった。そこをレールに引っかけて宙づりにしていたのだ。
もちろん、お金を入れないと引き抜くことは出来ない。
が、飲むことは出来た。
そう、栓を開けて、ストローを使えば飲めるのだ。
誰かがその方法で飲んでいたのが広まり、みんながやるようになった。
気がつけば、フタを開けたら空ビンばかりになっていた。
そこで、撤去ということになったわけだ。
そのため、柔道後にコーラを飲む楽しみはなくなった。
渇きは、道場にあった井戸水で潤していた。
しかし、今日はのどが渇く。
この日記を書いている今も、のどが渇いてしかたない。
いや、決して糖尿なのではない。
季節的なものである。
そう信じている。
ところで、こういう時こそ、昔に戻って水を飲めばよさそうなものだが、どうも気が進まない。
昔より衛生的な水、しかも浄水器までつけている。
それでも飲む気がしない。
ということで、今はお茶を飲んでいる。
| 2004年06月12日(土) |
佐世保の事件を受けて |
【1】
「なんか、ああいう事件があると、パソコンが悪者みたいに見えるね」
佐世保の事件を受けての、ある人の意見である。
こういうことを言わせているのは、いつも教育者であり、マスコミである。
彼らは目の付け所がずれているように思える。
パソコンが原因だと言われると、パソコンをやめさせようとする。
カッターで人を傷つけたとなると、カッターを持たせないようにする。
いつも、そこには心の問題というのが欠落している。
きっと自分たちが心の教育を怠ってきたから、その責任を物に転嫁しようとしているのだろう。
いや、心の教育を怠ってきたこともわからないのが実状なのではないだろうか。
【2】
こういう事件が起きるたびに、いつもその学校の校長が、
「全校集会で、命の尊さを生徒たちに言って聞かせた」
などと言っているのを聞くが、では普段は、いったいどういうことを言って聞かせているのだろうか?
きっと大したことは言ってないのだと思う。
事件が起きて初めて「言って聞かせ」るような教育が、また次の事件を引き起こすのだ。
つまり、付け焼き刃的な教育では、何も効果がないということである。
【3】
それにしても、こういう大切なことを、通り一遍の学校教育の範疇で教えようとするのに問題はありはしないだろうか。
思うに、学校教育だけの命の尊さなんて、ちっとも尊くはない。
宗教と離れた、政治の一環である学校教育で、命の尊さを教えようとするほうが、土台無理なのだ。
そういう時こそ、その方面の専門である、坊さんや牧師さんを学校に招いて、説法してもらうがいい。
彼らは心の問題のプロだから、大上段に「言って聞かせる」ようなことはしない。
わかりやすい言葉で教え諭し、そして学ばせることをするだろう。
【4】
小学校5,6年生の頃、ぼくのクラスの担任は敬虔なクリスチャンだった。
別に、先生は宗教的なことを言って聞かせるようなことはなかったが、その立居振舞にぼくたちは、少なからず影響を受けたものだった。
むやみに生徒を叱ることはしなかったが、かといって甘やかすようなこともしなかった。
一度、クラスで友人がケガをする事件が起きた。
先生は、何も言わず涙を見せた。
その時誰もが、
「この先生を泣かせたらいけん」
と思ったものだった。
その後クラスはまとまり、けんか一つなくなった。
【5】
中学1年の時だった。
3年生が、みんなを脅かせてやろうと思い、首を吊る真似をしていたら、本当に首を吊ってしまい、死に到った事件があった。
その時、3年の不良と呼ばれていた、普段は刃物をポケットに入れているような人たちが、こぞってその人の家に線香を上げに行き、涙を流したという。
素行はどうあれ、少なくとも彼らは、命の尊さを充分に知っていたのだ。
【6】
「都会では自殺する若者が増えている〜」という陽水の歌が流行った頃、ぼくの周りでも数人の人間が自殺した。
それを受けて、先生たちは諄々と命の尊さを教えてくれた。
今と違うことは、その当時はまだ戦争を経験している先生が多くいたことだ。
それ故に、先生の吐く言葉には説得力があった。
また、戦時中のことを親たちから聞いて知っているぼくたちの世代は、その言葉を受け止める下地があったのだ。
そういった意味では、今の子供たちは、不幸であると言えるだろう。
| 2004年06月11日(金) |
日本が侵略されていく(下) |
こうなれば、相手の弱点につけ込むしかない。
相手も、日本人の弱点である、情につけ込んでいるのだからだ。
ということで、支那人の弱点を探さなくてはならない。
支那人の特長として、まず残虐さが上げられる。
漢の高祖の妻呂后は、高祖の愛妾であった威夫人の手足を切り落とし、目をえぐり出し、耳を焼ききり、薬でのどをつぶした上で、便所に捨てて「人ブタ」と名付けたという。(史記)
また、西太后は咸豊帝に寵愛されていた麗姫の手足を切り落とし、水瓶の中に首だけ出して入れていた。
日清戦争の時も、捕虜にした日本兵の目をくり抜き、鼻をもぎ、耳をちぎり、手足を切り落として殺したという話がある。
それに関連して、支那人は過去、人肉を食べる文化を持っていた。
その昔、斉の桓公は子供の丸蒸しを食べたというし、あの劉備元徳も、山中の民家で一泊した際、そこの妻の肉を食している。
また、近代では食うに困って、自分の身内を殺し、その肉を売ったという話もある。
そこでだ。
相手が『南京事件資料館』なるものを作っているくらいだから、こちらも負けずに、『支那人残虐歴史館』や『支那人食人文化資料館』などを作ったらどうだろうか。
それを抗議してきたら、
「南京大虐殺の嘘を認め、南京事件資料館を閉鎖したらやめてやる」
と言ってやればいい。
そういえば、支那人には、物欲が強いという特長もある。
人は誰でも物欲が強いものだが、彼らは特にその傾向が強い。
他人の領土でさえ、自分たちの領土だと言い張っているくらいだからだ。
そこで、それを利用したらどうだろうか。
「南京大虐殺の嘘を暴いたら百万円出す」
という広告を、支那全土で出したらどうだろう。
すぐにたくさんの情報が集まるだろう。
元々支那民衆が金欲しさに売った嘘の資料が、南京虐殺の証拠となっているのだから、「嘘の資料を売りました」と言って、また金儲けをすることくらいするだろう。
彼らは歴史の事実よりも国益よりも、我が欲を満たすことのほうが大切なのだ。
相手も日本人の弱点である情の部分に訴えてきているのだから、おあいこである。
ついでに、半島の『従軍慰安婦問題』もその手で解決したらどうだろうか。
「従軍慰安婦の嘘を暴いたら百万円出す」
という広告を出したら、これもまたすぐに情報が集まることだろう。
もしかしたら、元従軍慰安婦なる人が出てきて「私が言うんだから間違いないよ」「従軍慰安婦なんてなかったよ。ただ親に売られただけだよ」などと証言するかもしれない。
手続きの面倒な訴訟を起こすより、そちらのほうが手っ取り早いし、金になる。
とはいえ、こういった案も、すべて机上の空論であることが歯痒く感じる。
誰か、本当にやってみらんかなあ。
| 2004年06月10日(木) |
日本が侵略されていく(上) |
歴史を見てみると、日本は支那単独との戦争に敗れたことがない。
確かに「白村江の戦い」では敗れているが、あれは支那単独との戦いではなく、新羅との連合軍との戦いだった。
元寇「文永・弘安の役」では勝っているし、近代に入っての「日清の役」では圧勝している。
また、先の大戦では全体的な戦争には敗れたとは言え、支那軍に敗れたわけではない。
最後の最後まで、日本軍は支那軍を圧していたのだ。
日本の敗戦後、台湾に支那軍が渡ってきたが、その態は、戦勝国の態ではなく、敗者の態だったという。
さて、偉そうにもその弱い支那が今、日本を侵略しようとしているという。
尖閣諸島を支那固有の領土だと言っているのは知られたところだが、何と琉球列島も固有の領土だと言い張っているのだ。
ご存知の通り、東シナ海日本領には膨大な資源(天然ガスや石油)が眠っている。
支那が、尖閣諸島や琉球列島を固有の領土だと言い張るのは、他でもない、この資源を我が物にしたいがためである。
何日か前の新聞には、すでに支那は採掘施設を建設している旨の記事が載っていた。
これに対して、日本側は何のアクションも起こしていなかったという。
「日中関係を悪化させたくない」との理由からだったらしい。
これを受けて、有識者の多くが、日本の堕落を訴えている。
それでも、元寇を防ぎ、大航海時代のスペインやポルトガルからの侵略を防ぎ、大国ロシアの南下から国を守った、誉れ高い日本民族の子孫だと言えるだろうか。
しかし、なぜこうなったのだろう。
なぜ弱い支那にガツンと言えないのだろう。
理由はちゃんとわかっているのだが…。
わかっているだけに腹が立つ。
『南京大虐殺』
あの忌まわしい狂言事件である。
言うに事欠いて、あの事件で当時の南京の人口以上の人が殺されたとまで言っているのだ。
どうして、日本人は、あんな嘘つき民族のいうことを真に受けるのだろうか?
どうして、あの大ボラ事件を政府主導で解明しようとしないのだろうか?
とはいえ、歴史の真実がわかったところで、あのたかり国家がこの狂言をやめるとは考えにくい。
面の皮の厚さが尋常ではないからだ。
もし、南京大虐殺が嘘だということがばれても、奴らは次の手を打って、新たな南京大虐殺を作り上げるだろう。
悔しいのう。
どうかやって、弱い支那をぎゃふんと言わせる手はないものだろうか。
| 2004年06月09日(水) |
頑張るタマコ!21歳(算数編) |
今日、タマコは知恵熱を出して、バイトを休むと言ってきた。
ラーさん曰く「しんちゃんが、いろいろと詰め込むけよ」
が、ラーさん。それは違う。
はっきり言って、この間はラーさんの問題のほうが難しかった。
最近、夕方から極端に暇になる。
ほとんど接客をすることがないのだ。
以前は何本か電話もかかっていたのだが、最近はそれもない。
売り出し準備でもすれば気も紛れるのだが、今週は売り出しがない。
それに加えて、今日はタマコもいなければ、暇つぶし仲間のH先生もいない。
『今日は面白くないのう。どうやって過ごそうか。それにしてもタマコの奴、あの程度で知恵熱とは情けない』と思っていた時だった。
『あ、もしかしたら…』と思い当たることがあった。
あの日、ぼくはタマコに、国語の問題を出した後、続けて算数の問題を出したのだった。
【問題1】
はたしてタマコは九九が出来るのか、と思ったぼくは、タマコに問題を出してみた。
「おい、タマコ。8掛ける9はいくつか?」
タマコは自信ありげに、
「そのくらい書けますよ」
と言った。
「書ける?」
「ええ」
そういうとタマコはメモ用紙に、
『八×九』
と書いた。
「おい、8×9はいくつかと聞いたんぞ」
「ああ、計算するんですか」
「そう」
「簡単じゃないですか」
「そうやのう。簡単やのう。で、いくつか?」
「63」
【問題2】
『お父さんは280円のタバコを5個、タマコさんは270円のタバコを10個買いました。これらを合わせて買う時、6000円のお釣りをもらうためには、レジでいくら払ったらいいでしょう』
この問題を紙に書いて、タマコに渡した。
さっそくタマコは計算を始めたが、何せ九九が出来ない。
そこで電卓を持ってきた。
5分ほどして、タマコは
「しんたさん、出来ました」
と言ってきた。
「いくらか?」
「4000円です」
「何でそうなるんか?」
「えっ、違うんですか?」
「4000円払って6000円のお釣りがもらえる店があったら、行ってみたいわい」
その後、タマコはその問題に手を付けなかった。
理由は、「頭がこんがらがる」ということだった。
『そうか、あれが原因やったんかもなあ。ということは、次からはもっとレベルを下げるしかないのう』
しかし、漢字の読み書きや、九九は基本だし、それ以上レベルを下げるとしたら、それこそ幼稚園のレベルに落とすしかない。
いったい、今、幼稚園ではどんなことを教えているのだろうか?
今度タマコに聞いてみよう。
6時前のこと。
ちょうどぼくがオナカ君と話をしている時だった。
何と休むはずのタマコが、ヘラヘラと笑って現れた。
「おい、タマコ。おまえ、今日は知恵熱出したけ休むんやなかったんか?」
「昼間は気分が悪かったけど…」
「もういいんか?」
「はい」
もちろんオナカ君に、タマコを紹介した。
そしてオナカ君に、
「何か質問してみろ」
と言った。
が、オナカ君は何も質問しなかった。
オナカ君が帰った後、タマコを鍛えてやろうと思い、タマコのところに何度か行った。
しかし、また知恵熱を出されたら困るので、何も問題を出さなかった。
タマコは今21歳。幼稚園の先生を目指している。
8×9は72だよ、タマコ君。
※人名は日記内検索で検索して下さい。該当日記が出てきます。(申し訳ない。PCだけです)
| 2004年06月08日(火) |
頑張るタマコ!21歳(国語編) |
先日、お客さんが少なかったので、暇つぶしにタマコに国語のテストをさせた。
メモ紙に、
『梨』『蛍』『西瓜』『南瓜』『蜜柑』
と書き、
「この漢字に読み仮名をつけてみ」
とタマコに言った。
さっそくタマコはボールペンを持ってきて、問題を解きだした。
「これは『なし』、これは『ほたる』…」
「おっ、タマコ出来るやないか」
「あたりまえじゃないですか、このくらい」
「じゃあ、次のは何か?」
「これは『にし』だから…、ああ『にしづめ』じゃないですか。で、次のは『みなみづめ』でしょ」
「『うり』やろが。それにそんな読み方はせん」
「えっ、違うんですか?」
「違う。次のは何と言うんか?」
「みっこん」
「『みっこん』ちゃ何か?」
「みっこんです」
これを見ていたラーさんが、
「三つとも食べるもんよ」
とヒントを与えた。
「ああ、食べるもんですか。じゃあ簡単じゃないですか」
と、『にしづめ』を消して『つけもの』と書き、『みなみづめ』を消して『なすび』と書いた。
「おい、何でこれが『つけもの』で、これが『なすび』になるんか?」
とぼくが言うと、タマコは
「だって、わたし、なすびが好きなんです」
と言う。
「好きやけと言って、勝手に字を変えるな。じゃあ、『みっこん』は何なんか?」
「ああ、『みっこん』は間違いです。これは『みつまめ』です」
いよいよアホである。
続いてラーさんが、
『閑かさや ○○にしみ入る 蝉の声』
『古池や ○○○飛び込む 水の音』
『雀の子 そこのけそこのけ ○○○が通る』
と書き、
「○の中、埋めてみてん」
と言った。
「蝉だから、これは『夏』ですよ」
確かに、蝉は夏の季語ではあるが…。
「えーっと、これは…、水の音だから『サカナ』、いや『イルカ』です」
タマコの中では、イルカは池の中に住んでいるらしい。
「そこのけそこのけ…、雀だから、これは『ネズミ』です」
わけがわからない。
あと、
「おまえ、『くだもの』を漢字で書ききるか?」とぼくが言うと、
ちゃんと『果物』と書いた。
「おお、書けるやないか」
「当たり前じゃないですか。馬鹿にしないで下さい」
「じゃあ、『やおや』は?」と言うと、
『八尾屋』と書いた後、
「あっ、違った」と言い、
『八屋八』と書き換えた。
「やっぱりタマコやのう」
ということで、国語は、
1,『蛍』=『ほたる』で、○
2,『梨』=『なし』で、○
3,『西瓜』=『つけもの』で、×
4,『南瓜』=『なすび』で、×
5,『蜜柑』=『みつまめ』で、×
6,『(なつ)にしみいる』で、×
7,『(イルカ)飛び込む』で、×
8,『(ネズミ)が通る』で、×
9,『くだもの=果物』で、○
10,『やおや=八屋八』で、×
10問中3問正解で、3点という結果になった。
100点満点だと30点になるから、ぼくの行った高校では、欠点をぎりぎり免れる点数(当時)だ。
タマコは今21歳。幼稚園の先生を目指している。
・・・道は険しい。
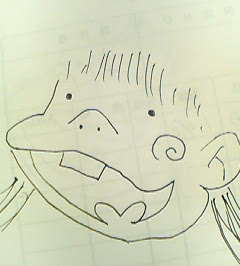
タマコ
昨日のこと。
食堂でタバコを吸っている時、店内放送で呼び出しがかかった。
そこに行ってみると、パートさんが困った顔をしている。
「どうした?」
「朝、時計を買ったお客さんがいるんだけど、その人が返品しに来たんです」
「で?」
「ベルトを調整しているし、返品はちょっと…」
「新しいベルトに交換することは出来んと?」
「うーん、それは出来ると思うんだけど、そのお客さん、今日が初めてじゃないんです」
「え?」
「返品常習犯なんです」
とりあえず、売場に行ってみると、そこにアロハシャツを着た遊び人風の男が立っていた。
こういう男は苦手である。
恐る恐る「はい、どういうことでしょうか?」と声を掛けてみた。
「どうもこうもない。この時計が気に入らんけ、金返せと言いよるんたい」
「気に入らんって、これお客さんが選んだんでしょ?」
「おれが言いよるんじゃない。女が『気に入らん』と言いよるんよ」
どうやらこの男、女性にこの時計をプレゼントしたらしい。
ぼくは、『あんたからもらう物は全部気に入らんのやないね?』と思っていたが、もちろんこういうことは口には出せない。
「そう言われましても、一度購入されたわけですし、ベルトのほうも調整してますから…」
「ベルトはまた元に戻せばいいやないか」
「そういう問題じゃないでしょ?」
ぼくがそう言うと、男は
「おまえは何が言いたんか!?」
と大声で言った。
周囲の目がこちらに注がれる。
ぼくは、自分の顔が赤くなっていくのを感じた。
『いかん!』
こういう時は、かなり頭に血が上っている証拠だ。
このままだと、ぼくは何を言い出すかわからない。
昔、頭に血が上って、やくざに文句を言い、大騒ぎになったことがある。
ここは冷静にならなければならない。
と思いつつも、
「返品を受け取りたくない、と言ってるんですよ!」
と言ってしまった。
男は一瞬黙った。
が、すぐに口を開き、
「おまえは何を言いよるんか!?」
と声を荒げて言った。
「お客さんが『何が言いたいんか』と言うから、言いたいことを言ったまでです」
再び男は黙った。
そしてまた口を開いた。
「もうそういうことはどうでもいいけ、早く金返せ」
「出来んと言ってるでしょうが」
「その分払ってもいいけ、早く金を返してくれ」
「その分?」
「おう、ベルト分よ」
「そうですか。じゃあ、2割頂きます」
「2割だぁ!?」
「はい、2割です」
「1割に出来んとか」
「駆け引きせんで下さい」
「何ぃ?」
「もし、自分が3割と言ったら、お客さんは『2割にしろ』と言うでしょ?それを見越して2割なんです」
「もういい」
「じゃあ、2割頂きます」
ぼくはレジの子を呼んで、2割引いた額を返すように言った。
お金を持って行くと、男は、
「まったく女の子の好みはわからん」
と言って苦笑いしていた。
ぼくはニヤッと笑って、
「今度はちゃんと、その女の人を連れてきて選んでもらって下さい」
と言った。
もちろん『その女性は、あんたのプレゼントを受け取らんと思うけど』と思いながら。
男は最後に「すいませんでした」と言って帰って行った。
ぼくは「ありがとうございました。これからもよろしくお願いします」と基本どおりに言いながらも、『もう二度と来るな!』と思っていた。
何年かかけて、ようやく答を得た。
『念彼観音力』は、やはりこの呼吸だった。
多くの書物や自らの体験が、それを証明してくれた。
悩みに流されている時、人は我を忘れているものだ。
ということは、悩みに流されていると気づいた時は、すぐさま我に帰らなければならない。
その方法こそが、禅であり念仏であったのだ。
その方法に一つ付け足したいものがある。
それは、「視線を正す」ということである。
悩みに流されている時、人の目は泳いでいるものだ。
ということは、その悩みを消し去るには、視線を正せばいいということになる。
「そんな単純なものなのか?」という疑問を持たれる人もいると思う。
が、そんな単純なものなのだ。
般若心経でも言っているように、すべての事象は元々何もない。
ということは、悩みも元々ないものである。
そもそも悩みというものは、自分の心で作りだした事象に、自分の心が執着しているだけのものなのだから、悩みを消し去るには、その執着を断ち切るだけでいい。
元々ないものであるからこそ、視線を正す、つまり悩みに目を向けずに「今、ここ」に向ける、つまり我に帰ることで、簡単に断ち切ることができる。
ただ、これを継続出来るか否かは、本人の努力次第である。
我に帰っても、またすぐに悩みに流されてしまっては元も子もない。
常に視線を体の中心線に置き、視線を正さなければならない。
ということで、17年間の『念彼観音力』探求は、今のところ『視線を正す』というところに落ち着いている。
今後また新たな展開が起きるかもしれないが、基本的なものは変わらないだろう。
いや、変わりようがないだろう。
【追記】
今回佐世保で起きた事件だが、おそらく殺人を犯した女子児童も、あの時視線が流れていたのだろう。
もしあの時視線を正しくしていたら、その動機自体が空しく感じていたにちがいない。
そうであれば、あの事件も事前に防げただろう。
事を起こした後に、人はみな視線を正しくする。
その後に襲ってくるものは、悔悟である。
そして、無間地獄へと堕ちていく。
「あの時、こうすれば」ということを、人はその時に出来ない。
その時、視線を正すための訓練を、普段から積んでないからだ。
あの少女は通り一遍のケアを受け、ふたたびいつもの生活に戻るのだろうが、無間地獄からは逃れられないだろう。
もし逃れられるとしたら、事件のことをすっかり忘れてしまうしかない。
だが、忘れようとして忘れられるものではないし、仮に忘れたとしても、忘却の奥に潜む苦痛を常に受けることになるだろう。
日常生活をやっていても、無間地獄からは逃れることは出来ない。
無間地獄の果ては、人格の破滅しか残ってない。
ではいったいどうすればいい?
ぼくは、供養しかないと思う。
そうすることで、彼女はこの世に生を受けた意義を知り、その時初めて自分を取り戻すことになるからだ。
無間地獄は自分を取り戻す、つまり我に帰ることによって、自ずと消滅してしまうのだ。
ということは、彼女にとっての残された唯一の救いは、殺めた命を一生かけて供養していくことしかないじゃないか。
彼女は今、『念彼観音力』を必要としている。
『念彼観音力』も今、彼女を必要としている。
『我に帰れば、心の中にある地獄は消え去ってしまう。だから、我に帰ろう』
妙法蓮華経観世音普門品第二十五、つまり観音経の要約である。
般若心経に比べて、観音経はだらだらと説教が続いているが、要はこういうことをいろいろな方面から説明しているにすぎないのだ。
30歳の頃、ある事情から、ぼくはこのお経にかかわりをもつことになった。
それまでは、のんびりと中国思想などと闘っていたのだが、そういったどちらかというと処世術的なものでは解決出来ない問題があるのを知ったのである。
そういう時に出会ったのが、般若心経であり、この観音経だったわけだ。
この観音経にはいろいろな霊験が書いてある。
火の中に落とされた時、大海に漂流した時、山から突き落とされた時、賊に襲われた時、魔物に襲われた時など、もろもろの苦難を受けた時、観音の力を念じれば救われるというものだ。
その、「観音の力を念じれば」の部分が『念彼観音力』という有名な言葉である。
この経を勉強していた頃、ぼくはこの『念彼観音力』にほとほと手を焼いた。
声を出して「ネンピーカンノンリキ」と唱えてみればわかるが、この言葉は実に力強い言葉である。
また、この言葉は、念力の『念』という文字を含んでいる。
超常現象物が好きなぼくは、この『念彼観音力』という言葉を見て、すぐに超能力を連想した。
そして、この『念彼観音力』の中に呪文を感じた。
そう、最初にこの言葉を見た時、ぼくは「念じれば、苦難から逃れることが出来、行く行くは超能力を得ることが出来るようになる」と単純に理解したのだった。
それからぼくは、毎日「念彼観音力、念彼観音力…」と唱えていた。
しかし、苦難からは逃れることは出来ない。
ましてや、超能力なんて、夢のまた夢である。
確かに唱え始めた頃は、心身共に軽くなっていくのを感じたのだが、日が経つにつれてそれは惰性になり、ついにはただの口癖になってしまった。
また経の解釈も、「呪文を唱えれば苦難から逃れる」となったため、言葉の苦難から逃れられなくなった時、「このお経は偽物だ」と認めざるをえなかった。
そういう時だった。
「観音経は人生の書だ」と書いてある本を見つけた。
そこには、「観音経は、字面ばかり捉えていても何も見えてこない。そこに人生を照らし合わせてみろ。はたと気づくことがあるはずだ」といった内容だった。
そう言われればそうである。
超常現象マニア限定の本なら、こうまで長く多くの人に読み継がれなかっただろう。
では、『念彼観音力』が呪文でないとしたら、いったい何なのか。
この疑問がぼくの、観音経の再出発点となった。
もはやそこに超常現象を見ることはなかった。
ある時、ふと我に帰った瞬間に、それまであった悩みがきれいさっぱりと消え去っているのに気づいた。
「これはいったい何だろう。もしかして『念彼観音力』は、この呼吸なのか?」
そこから、また探求が始まる。
東京にいた頃、ぼくは高田馬場に住んでいた。
早大生でもないのに、どうして高田馬場かというと、不動産屋に下宿を探しに行った時に、先方が「どういうところがいいですか?」と聞くので、「本屋の近くがいいです」と答えたら、「じゃあここはどうでしょう」と薦められたのが高田馬場だったというわけだ。
山手線内ということで、若干下宿代は高かったものの、資料を見ると、国電(当時)や西武新宿線の駅からは歩いて5分と近く、地下鉄駅にいたっては歩いて1分もかからない。
さっそく現地を見に行ったのだが、造りが古いことを除けば、日当たりもよく、台所も備えてあり、まずまずの印象だった。
何よりもよかったのは、駅を降りて下宿に帰るまでに、3軒の本屋があったということだ。
しかもそのうちの1軒は、地下鉄駅のすぐ横、つまり下宿から歩いて1分の位置にあった。
不動産屋に戻ると、係の人が「どうでしたか?」と聞くので、「今日からでも住みたいです」と答え、さっそく手続きをした。
で、高田馬場にどんな想い出があるのかというと、本を買った・立ち読みした、近くの牛丼屋の牛丼は妙に油は多かった、といった日常生活的な記憶以外に、そう大した想い出を持ってはいない。
それは、東京に出た最初の年こそ、せっせと下宿に帰っていたものの、次の年あたりから友人たちの家を泊まり歩くようになったためだ。
昨日は埼玉、今日は千葉、明日は神奈川といった生活をくり返していたのだ。
そのため、東京にいるのは週1回程度だった。
後で聞いた話だが、下宿のおばさんは、ぼくがいつもいないので、実家に「何で毎日下宿に帰ってこないんですか?」と馬鹿な電話をかけたりしていたようだ。
ぼくの知っている範囲では、高田馬場はのんびりした街という印象だった。
が、夜中の騒音には悩まされた。
さて寝ようかなと思っていると、突然「ドワー」という大音響。
「万歳」が聞こえてくる。
怒号が聞こえてくる。
嗚咽が聞こえてくる。
近くにこれと言った飲み屋がないのに、何の騒ぎかと思ったら、翌日の新聞を見て納得した。
東京六大学野球で早大が優勝したのだった。
大学内やその近辺の飲み屋で出来上がった学生が、その勢いで高田馬場に繰り出していたのだろう。
優勝は嬉しいかもしれないが、付近の住民にとっては迷惑な話である。
迷惑と言えば、駅前でよくヘルメットをかぶった早稲田の学生が、メガホン片手に何やらわけのわからない演説をしていた。
ぼくが東京にいた時期は、70年安保から10年近くもたっており、学生運動もかなり下火になっていた。
唾を飛ばして訴えている内容にも、具体性はなく、どこかピントのはずれたものだった。
何人かの学生がビラを配っていたが、受けとる人もいなかった。
ぼくはそれを見てある種の臭みを感じていた。
臭み、それは自己顕示・自己陶酔・自己満足だった。
きっと彼らは政治批判にかこつけて、自分たちの頭の良さを顕示していたのだろう。
後年、東京に出た際に、時間が余ったので高田馬場に寄ったことがある。
駅前はあいかわらずで、右手にビッグボックス、正面に芳林堂といった風景は変わっていなかった。
が、ぼくのいた下宿付近は大いに様変わりしていた。
第一、下宿自体がなくなっている。
しかも、そのへんに大きな建物が建っており、どの位置に下宿があったのかさえわからなくなっていた。
下宿は、早稲田通りから路地に入ったところにあったのだが、一瞬その入り口を間違えたのかと思ったものだ。
しかし、目印である地下鉄の階段はちゃんとそこに存在していた。
本屋もちゃんとあった。
ぼくが一度だけ利用したことのある床屋も、そこにあった。
しかし、あまり滞在したことのなかったところなので、感慨といったものはなかった。
これが十数年前の話であるから、今行ったとしたら、さらに様変わりしていることだろう。
案外、その路地もなくなっているのかもしれない。
| 2004年06月03日(木) |
『タンスヨウゴミヨウカン』 |
先日、2日間かけてタマコのことを書いた。
ラーさんがアルバイトの高校生に見せたところ、大受けだったらしい。
しかし一番受けていたのは当の本人、タマコだったということだ。
そのくせ、「何これ、そのまんま書いとうだけやん」と言ってうそぶいていたそうだ。
さて、今日タマコは、午後6時から8時までの2時間勤務だった。
タマコを書いた日から、ぼくはタマコに会ってないので、今日は4日ぶりの顔合わせとなった。
タマコはぼくの顔を見るなり、逃げた。
「おまえ、何で逃げよるんか?」
「またいろいろと書くでしょう」
「おまえがまともになったら書かん」
「私はまともです」
「どこがまともか!」
「ねえ、どうしてタマコなんですか?私は珠○なのに」
「タマコで充分たい」
その後もタマコは逃げ回って、なかなか隙を見せようとはしなかった。
ところが7時過ぎた頃だったか、タマコがヘラヘラ笑ってぼくの売場にやってきた。
「ねえ、しんたさん」
「何か?」
「小学生のタンスヨウゴミヨウカンってありますか」
「タンスヨウゴミヨウカン?何するものか?」
「いや、お客さんから電話なんですよぉ」
「それを先に言え!待たせとるんか?」
「はあ」
「じゃあ、『調べまして、こちらから折り返し電話します』と言っていったん切れ。あ、名前と電話番号をちゃんと聞いとけよ」
『さて、小学生用のタンスゴミヨウカンとは何だろう?』
こんなことを考えているところに、電話を終えたタマコがやってきた。
「わかりましたかあ?」
「わからん。何する物なんかのう?」
「もしかしたら、タンスのゴミをまとめて捨てる缶かもしれませんよ」
「そんなのがあるんか?」
「さあ?」
「知らんなら言うな!『学校の引き出し』というのがあるけど、その類のものかのう?」
「あ!」
「何か?」
「羊羹ですよ」
「え?」
「タンスヨウゴミという羊羹ですよ」
「そんなのあるか!それなら食品に電話するやろう。もういい、取引先に聞いてみる」
[あ、もしもし、しんたですが]
[お世話になっています]
[ねえ、タンスヨウゴミヨウカンち知っとう?]
[何ですか、それ]
[わからんけ、聞きよるんやないね]
[さあ、知らんですねえ。聞いたこともない]
やはり駄目か。
こうなったら、恥を忍んでお客さんに聞くしかない。
「タマコ、さっきのメモ」
「はい。これです」
[もしもし、○○店ですが、お世話になっています]
[はい]
[先ほど電話頂いたそうなんですが、よくわからなかったので電話差し上げたんですけど…]
[ええ!?あのですねえ…。知りませんかねえ、小学生用の『算数用5ミリ方眼紙』]
[ああ、方眼紙ですか]
やっとわかった。
『タンスヨウゴミヨウカン』は、タマコの聞き違いだったのだ。
当のタマコ、聞き違いとわかるや、「あー、違(ちご)たー」と言って、頭を抱えて逃げて行った。
電話が終わった後、ぼくがタマコを探しに行くと、タマコは商品の陰に隠れていた。
「コラー!何が『タンスヨウゴミヨウカン』か!おまえはどういう耳をしとるんか!?」
「だって、そう聞こえたんですよぉ」
「おまえは、電話番もしきらんとか!?」
ぼくはタマコにさんざん文句を言った。
そしてその後、思うところがあって彼女を日用品の売場に連れて行った。
そこには急須が置いてあった。
ぼくはその急須を指さして、「おい、これは何か?言うてみ」と言った。
タマコは「そのくらい知ってますよ。『湯飲み』でしょ」と自信ありげに答えた。
「これが湯飲みかっ!」
「ええっ、違うんですかっ!?自信あったのになあ」
次に傘の売場に連れて行った。
ぼくは傘の柄を指さし、「じゃあ、これは?」と聞いた。
「これは、『カサモチ』です」
・・・、勘弁してほしい。
タマコは今21歳。幼稚園の先生を目指している。
| 2004年06月02日(水) |
伯父は共産主義者だった |
知り合いに共産党かぶれの人間がいる。
この人、二言目には「おまえは『しんぶん赤旗』を読まんから、世相に疎いやろう」と言う。
別に『しんぶん赤旗』など読まなくても、世相に詳しい人はたくさんいるだろうし、『しんぶん赤旗』を読んでいる人すべてが世相に詳しいわけではないだろう。
高校の頃、よく郵便受けに『赤旗新聞日曜版』が入っていた。
ぼくは、それを毎週読んでいたのだが、世相に詳しくなんかならなかった。
もっとも、ぼくが読んでいたのは板井れんたろうのマンガ『六助くん』だけだったが。
共産党で思い出したが、ぼくの義理の伯父は、筋金入りの共産主義者だった。
戦前は治安維持法に引っかかって逮捕され、戦後はレッドパージで八幡製鉄をクビになった。
その後も共産党員として活動していたようだ。
伯父の家に行くと、当然のように赤旗新聞が置いてあった。
が、先の人みたいに、それを読んでいることを自慢するようなことはしなかったし、ぼくに「それを読め」などと言ったこともなかった。
たまに議論を闘わすこともあった。
そのたびに伯父はぼくに、「おまえは右寄りやなあ」と言っていた。
が、それを非難するようなことは一切なかった。
祖父の法事の時だった。
法要を終えた後宴会になったのだが、その折に坊さんが「先日、ソ連に行ってきましてねえ」という話をしていた。
坊さんはやや非難口調でソ連を語っていたのだが、それにカチンと来たのだろう、「いいや、ソ連に限ってそんなことはない。あんたはそういう見方をするから、そう見えるだけだ」といちいち反論していた。
そこにいた人たちは、みな「兄さん、ご住職はそんな意味で言ってるんじゃないでしょ」と言って諫めた。
が、聞くような人ではなかった。
さんざんソ連を賛美したあげく、持論を吐き、横になって寝てしまった。
きっと若い頃に憧れたソ連に、夢や希望を託していたのだろう。
伯父は会社を退職した後、大好きな釣りと読書三昧の余生を送った。
その頃にはすでに共産党からは脱退していたらしく、選挙のたびに立候補する共産党員を見ては、「あんな奴は、本物の共産主義者じゃない」と言ってけなしたものだった。
もはやその頃には、伯父の家には赤旗新聞は置いてなかった。
代わりに家にあったのは、なぜか読売新聞だった。
ある時、伯父は突然「腹が張る」と言い出し、それからまもなくして亡くなった。
‘92年1月のことだった。
ソ連が崩壊したのが、その1ヶ月前のことだったのだが、もしかしたら伯父の死は、それに気落ちしての死だったのかもしれない。
そういえば、その前年、「しんた、何か本を貸せ」と言って、うちに来たことがある。
興味深くぼくの書棚を見ていたが、ある本に伯父の目が釘付けになった。
歴史物が多くあるぼくの書棚だが、伯父が選んだのはそういう本ではなかった。
その本は、道元の『正法眼蔵』だった。
「これ貸してくれ」
「ああ、いいよ」
ということで貸したものの、その本はいつまで経っても返ってこなかった。
そこで伯父が亡くなった後、伯母に「おいちゃんに『正法眼蔵』貸しとったんやけど、あれどこにある?」と聞いてみた。
が、伯母は「え、そんな本読んでたかねえ。見たことないよ」と言う。
伯父の書棚を探しても、その本は出てこなかった。
もしかしたら、あの世に持って行ったのではないだろうか。
そうであれば、唯物論の共産主義崇拝者が最後に選んだ本は、唯心論の仏教書だったということになる。
共産主義は、魂を救ってくれなかったのだろう。
| 2004年06月01日(火) |
頑張るタマコ!21歳(下) |
まず手始めに、基本的なことからというので、メモ用紙に九州地図を描き、そこに県名を入れさせることにした。
「おい、ここが福岡県。じゃあ、ここは何県か?」
と、福岡の左横を指さした。
「わかりますよ、そのくらい。佐賀でしょ」
「お、わかるやないか。じゃあ、ここは?」
「バカにしないで下さい。長崎じゃないですか」
「じゃあ、ここは?」
と、ぼくは福岡の右下を指さした。
「こういうのは得意なんです。そこはですねえ、岡山県です」
ぼくは笑うのを必死に堪え、「じゃあ、ここは?」と、その下を指さした。
「岡山の南だから…、ああ、広島県です」
それを見ていたラーさんが、長崎の左横に彼女の出身地である五島列島を描き加えて、「タマコちゃん、ここは?」と聞いた。
タマコはいかにも自信ありげに、「そこは、島根県です」と答えた。
ラーさんは腹を抱えて笑い出した。
「おまえ、知っとる県名を並べよるだけやないか。ちゃんと勉強してこい」
と、ぼくは売場に戻った。
それから一時して、「しんたさん、わかりましたよ」とタマコがやってきた。
手に先ほどのメモ用紙を持っている。
それを見ると、そこには正しい県名が書かれていた。
「ちゃんと自分で考えたんか?」
「当たり前じゃないですか。任せて下さい」
ところがよく見ると、その県名、所々ひらがなで書かれている。
そこでぼくが「おまえは『大分』という漢字も書ききらんとか?」と聞いくと、タマコは「ちゃんと書けますよ」と言う。
「じゃあ、書いてみろ」
さすがタマコである。
期待通り書いてくれましたわい。
【大痛】
「じゃあ、鹿児島はどう書くんか?」と聞くと、【鹿ご鳥】と書く。
「おまえは、漢字から勉強せないけんのう」
最後にこの質問をしてみた。
「おまえは都道府県というのを知っとるか?」
「知ってますよ、そのくらい」
「じゃあ、東京は東京何と言うんか?」
「東京県」
「東京けん?ラーメン屋やないんぞ。じゃあ大阪は?」
「大阪県」
「北海道は?」
「北海道県」
さすがにバカボン似である。
これでは幼稚園の先生どころではない。
もし今タマコが幼稚園の先生になったら、「浴衣着てお祭りに行ったんやけど、その時下駄のタビが切れて困ったっちゃね」とか、「この間、東京県に行った時、ナンパされたんよ。『田舎どこ?』と聞かれたけ、『福岡県。岡山県の上の』と教えてやったっちゃ」とかいう会話が、タマコの教え子の間で、まかり通るようになってしまう。
「おまえねえ、幼稚園の先生になる前に、園児からやり直せ」とぼくが言うと、バカボン似のタマコは、人ごとのような顔をして、口をぽかーんと開けていた。
タマコは今21歳。幼稚園の先生を目指している。
|