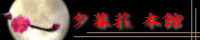| 2003年10月18日(土)
|
しろ君ときいろちゃん |
最近、昔話ばかりを書いていたので、周囲に、当時を思い出すべき資料が転がっている中、
中学の時の卒業文集の中に、当時から凄く気になっている文章を書いている子がいた。
その子は男の子なのだが、実に抽象的で美しい文章を書くなぁ・・・・と意外な一面を見た気がして、
15の時、あたくし自身の心が荒みきっていたにも拘らず、とても感銘を受けたことがある。
今読み返しても、かなり意味深で気になる文章だ。
彼自身がここを覗いているとは思えないし、かといって無許可で・・・・というのもどうかと思われたが、
是非とも、全文を転載したい。
あたくしは、わざわざ卒業文集にこういう文章を書くこの少年のセンスが
今更になりとてもキラキラと輝いているようにも見え、
どんな優等生の思い出話よりも美しい文章に見えた。
彼が怒鳴り込んでくるのを承知で、あたくしは書こう。
# しろ君ときいろちゃん
見た目はしろいが内に黒を秘めている。それがしろ君だった。
しろ君は以前から元気がないと批判されてきた。それはしろ君自身も認めていた。だからあか君のことがとてもうらやましかった。あか君を見習い、しろ君は努めて元気に振る舞った。が、「やっぱりしろは元気がないなぁ。」という、このおっさんの一言でしろ君は自信を失った。
しろ君のことを『利己主義者』 『無関心な奴』という人がいる。それは違う。しろ君は常に冷静なだけである。情熱ももっている。したがって他人にとやかく言われる筋合いは全くない。
ある日、しろ君は自分の存在について疑問を持ち始めた。自分は画用紙にぬられても、本当にぬったのかは分からない。しろ君はきいろちゃんに自分の存在を認めて欲しくなった。しかしきいろちゃんはしろ君に対して同じ仲間としての存在を認めなかった。きいろちゃんが言うには、しろは他の色を引き立てる存在であり、色として扱うのは私やあお君に対しての侮辱だ とのことだ。それはしろ君の持っている黒のせいであり、持ち合わせていない勇気のせいであった。
しろ君は次第に自分さえも信じられなくなった。しろ君は思った。一体なんだ。この黒は。全てこの黒が悪いのだ。自分は何も悪いことなどしていないのに。その考えはやがてしろ君の退廃した生活を生み出し、黒はしろ君を包むだろう。
はたして黒とは何だろう。確かなのは、自分自身の中のもう一人ということと、絶対に黒は消えないということだ。
皆が挙って、中学校時代の思い出を振り返って、ある行事に焦点を当てたり、部活動での出来事や
感動したこと、自分は3年間でこんなふうに変わったよ・・・・などといった文章が続く中、
彼の文章だけは、ひときわ異彩を放っているように見えた。
自分のことを書いたには違いないだろうが、B5版の半ページのスペースにコレだけのことを盛り込む
彼のやり方に、あたくしは当時から文芸人としての芽生えもあったため、衝撃的で、
素直に「凄いな」と思った。
きっと、彼はきいろちゃんに認めて欲しいと感じながら、恋をしていたのではないだろうか、とか、
あか君やあお君に対して憧憬の眼差しを送る反面、憎くて憎くて仕方がなかったんじゃなかろうか、とか、
明文化されているように、自分のことすらも信じられなくなって、自暴自棄になっていても
誰にも気付いてもらえない悲しさであるとか、そういったものがギュッと凝縮されている気がするのである。
多分「画用紙」というのは、「学校」という枠組みのことを指しているのだろう。
もしくは、それ以外のコミュニティであるとか・・・・。
あたくしたちは、15歳当時、そういう「集団」の中で生活することを強いられていたから、
そういう解釈が一番妥当だと思う。
彼は、卒業寸前まで、特に運動や勉強でも目立つことのない感じの子であった。
あぁ●●部だった子ね、とか、何組だった子ね、とか、そういう思い出し方も危ういくらいに
存在感も薄かった。
あたくしと彼は中学に於いては1年生の時だけ同じクラスだったのだけど、
彼が意欲的に何かに取り組んでいる・・・・という姿を見たことはなかった。
こちらが指揮を採るべき立場にいたので、彼のことを何度か注意したことは覚えているのだが、
彼が取り立てて先生や他の誰かに褒められているといった印象はなく、
寧ろ、この文面の通り、「認めてもらえない」存在だったかもしれない。
彼は、あたくしよりも1ランク上の高校に進学していった。
合格発表のその日まで、彼がその高校を受験していることすらも知らなかった。
彼はあの場所で、何か面白いものを見つけることができたのだろうか?
あたくしの母校は、卒業文集以外に、2年生の時に「立志式」というのを執り行い、
それに伴い、将来の夢や歩むべき指針をテーマにした文集も残している。
立志・・・・数え年で15・・・・つまるところ、ほぼ全員が満14歳になろうとしている時期、
3年生が卒業してから、この式は行なわれていた。
彼は、この文集に「自分はサラリーマンになりたい」と書いていた。
この時期、まだバブルは崩壊していなくて、全ての職業に「夢」や「希望」が満ち充ちていた。
願い、祈り、努力をすれば、絶対にその目指すべき道に辿りつくだろうと、凡その人間が信じていた。
が、彼はその中でもあえて「サラリーマン」という選択をしていた。
今や、そのサラリーマンこそが高きハードルだったりもするのだけれど、
当時、そんなことを書くのは彼くらいだったのだ。
あたくしは、彼の卒業に際したこの文章を読んで、奇妙な感動を覚えた。
他にも仲の良い友達や、クラスの内外を問わず、冗談を言い合ったりできる男子生徒らもいたが、
そんな少年少女の書く文章すら、色褪せて見えた。
「しろ君」という個性が一番素晴らしいのに・・・・。
そんなことも思った。
中学を卒業して、高校に入学し、あたくしは演劇部に入部した。
そこであたくしには、先輩からありというコードネームを与えられ、
特に大した経験があるわけでもないのに、言われたことは何でも率なくこなすあたくしを
先輩たちは可愛がってくれた。
ある日。
新入生たちが何色か? という話題になった。
●●は赤だねとか、△△は紫っぽい印象だよね・・・・次々とそれらしい意見が出る中、
先輩たちはあたくしを見て、暫し無言になった。
どんな色にも染まるし、どんな色にも負けない、どんな色も持っていそうだけれど、
だけど・・・・何色かと問われると、単色で表すことができない。。。。
こんなにも我が強いあたくしを、先輩たちはそんなふうに表現した。
そして、この時もあたくしは、「しろ君ときいろちゃん」のことを思い出していたのだった。
ガラスに吹き付ければ、しろだって、立派に発色するわ・・・・そんなふうに。
昨日、微熱が高熱に移行せんばかりの状態だったため、夜は大人しく横になっていた。
テレビで「フジ子・ヘミングの軌跡」を見ていた。
あたくしは、彼女のように一流の才能があるわけではないけれど、踏ん張りが足りないばっかりに、
世間に認めてもらえない・・・・彼女の苛々が、すぐあたくしの波長と合致してしまい、
悪い癖なのだが、波長が合致すると、苦しい感覚や痛い感覚がどんどん流れ込んできてしまうので、
あたくしは泣きながらその番組を見ていた。
世で言う有名な俳優さんや脚本家さんたちにもちゃんと出会っている。
彼女が有名な音楽家たちと出会っているのと同様に・・・・。
そして、あたくしが少し距離を置いたその間に、恩師は亡くなってしまった。
全く以って、このあたりは彼女と一緒。
もう、あたくしを導いてくれる人なんかいない・・・・。
劇中、フジ子が呟いたことを、あたくしも何度も呟いた。
そして、このままじゃダメだと、居場所を模索し始めた。彼女が留学を思い立ったように。
仕事が来ない。ピアニストなのに・・・・。
仕事が来ない。俳優なのに・・・・。
何か、あれほど極端ではないもののほとんどが一緒で、物凄いシンクロをしてしまって、
その後に自分を恥じる。
あたくしは彼女ほど苦労もしていないだろう。
そして、あんなにも才能なんかないかもしれない。
努力もしていない。
でも、彼女がピアノを失ったら、呼吸ができなくなるのと一緒で、
あたくしが芝居をやめたら、やっぱり呼吸ができなくなってしまうような気がしている。
文字を書くことを差し止められても、同じ症状が起きるかもしれない。
芝居はともかく、書くことをやめたら、多分本当に、呼吸が止まってしまう気がする。
「フジ子、あなたピアノのない生活のことを考えたこと、ある? ピアノじゃなくていい、
絵描きとか、もっと他の職業とか・・・・ピアノのない生活の事、考えたことあるか?」
フジ子の母がそう問いかけているのを、あたくしも真正面に受け止めてしまった。
文章を書かないでいる生活を考えたことがあるか、と。
「ゴッホはね、画家になってから10年間、死ぬまでに800枚以上の絵を描いたわ。
でも、生きている間に売れたのは、たった一枚。
それでも彼は描き続けた。どうしてだかわかる?
・・・・彼は描かずにはいられなかったのよ。描くことがもう彼の息遣いだった。
あなたのピアノもそれと同じ。あなたの息遣いで色を付けていけばいいわ。
ゴッホのひまわりがあんなにも激しく個性的な色使いになったのは、
それが彼の呼吸そのものだったからなのよ。」
フジ子の叔母はひまわり畑で、まだ若いフジ子にそんなことを言う。
舞台に立てなかった間、あたくしは、事実、とてつもない頻度で過喚起発作を起こし、
どうにもならなくて、普通の生活すら追われた。
もっと彼女のように、「生きる」ことに必死になっていたら、あたくしの運命も変わっていたのだろうか。
そして、今からでも遅くないのだろうか・・・・?
あたくしには、明らかに「必死さ」が足りないと思う。
砂糖水だけで数週間生きる、ギリギリのところまで追い込まれてもいないし、
ありがたいことに、発作が起きる以外は五体満足だ。
書くに必要なだけの視力と握力もある。
演じるに必要なだけの感覚もまだある。
栄養だって、与えてもらっている。
ろくろく、働きもしないのに、母親はご飯を作ってくれる。
神に・・・・「生きろ」と嘗て言われた気もする。
ただ、フジ子のように、「生きていこうと思えばなんだってできるものよ。」と
笑顔で言うには、もう少し時間がかかりそうだ。
悟ってはいるのだが、富であるとか名声であるとか、キャリアであるとか、
そういうものへのこだわりが捨て切れていない。
不良ゲージツ家のあたくしは思う。
書かない、演じない人生を、思い描いたことは一度もない。
だって、それが当たり前のことだと思ってきたから。
中学の頃の、立志に当たっての文集、そして卒業文集にも、あたくしは実は
「書くこと」に対して、
既にプロ意識を持って対峙していたのであった。
今はどうしようもない「ごくつぶし」に成り下がったが、ピアノが弾けなかったフジ子のことを思うと、
今、生きるのをやめて、全てを捨ててしまうのを選ぶのは愚かなことだ。
あたくしは自らをもっと磨かなければならない。
しろでもきいろでもない「あたくし」が出来上がるまで、諦めちゃダメなんだ。
|