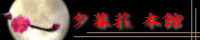♪雨がぁ・・・しとしと日曜日ぃ〜・・・・
♪僕は〜 ひとぉりでぇ〜
♪君のぉ〜 帰〜りを待って・・・・
コホン。
こんな歌を知っている、そこのあなた。<特に20代
年齢、ばれますよ?<詐称してるなら(爆)
あと、世間ずれしていると思われるので、
カラオケ屋で、大人の人が歌っていても、
一緒に口ずさまない方がいいです。
GS(グループ・サウンズ)時代を駆け抜けてきた大人たちがいっぱいいるところで
GSの曲ばかりを聴いて
だんだん、覚えてしまったあたしは
思わず口ずさむことで、
実際の年齢よりも、10歳も老けて見られたことがあります( ̄∇ ̄;)
そんな話はおいといて・・・・・。
今日は、正に、雨がシトシトの日曜日。
体はだるい。いつものこと。
だけどちょいと様子が違うのは
先週末から咲きはじめた金木犀の香りが
辺り一面に漂っていること。
あたしは、春の木蓮、そして秋の金木犀が大好きである。
歌にして詠んだり、
短編小説にもそのまま「木蓮」「金木犀」という表題で
発表した作品があるくらいに
私にとっては春秋を代表する植物だったりするのである。
春先、花見をしにいくのであれば
桜がある処より、木蓮のある処に行きたい。
秋口、紅葉を楽しみにいくのであれば
楓や蔦の色よりも、金木犀の香りを楽しみたい。
そういった感じで。
さて・・・・。
話はがらりと変わりまして、
今日はジャンル・文芸に恥じぬよう
和歌のことに少し触れようと思います。
あたしが今、熱中しているのは「現代短歌」と呼ばれる部類で、
それでなくても、まぁ、31音であればよしとしましょうみたいな
更にアバウトな処にいるのだけれど
「五行詩」ほど、散文的でもありません。
あくまでも、5・7・5・7・7という、定型律だけは守る。
後は何してもかまわない。ルールは1つだけ。みそひともじ。
自由の中に放り込まれると、人間はまず戸惑います。
だからわざわざルールを1つだけ設けたのです。
それが5・7・5・7・7というリズムなのです。
「和歌」には、他にも色んなルールがあります。
枕詞(まくらことば)、縁語(えんご)、連語(れんご)
係り結び(かかりむすび)、倒置(とうち)、対句(ついく)
掛詞(かけことば)、隠し題(かくしだい)、折り句(おりく)
挙げればキリがないくらいに、色んなルールや小技が存在します。
上記のはまだまだほんの1例で、
使えば現代短歌にも面白いふくらみを持たせてくれるワザも
けっこうあるんです。
で、本日は学生時代に折り句というワザを使って詠んだ歌が
この散らかった部屋の片隅から出てきたので、
その歌と、昔から有名な「伊勢物語」の中の1首を取り上げて
ことばの妙について話しちゃいましょう♪
この歌は、「折り句」というワザを使っています。
ある人に
「かきつばた」という5文字をそれぞれの句の一番上にいれて、
旅の心を歌に詠んでみなさいな。
といわれた作者が、咄嗟に作って詠んだものだとされてます。
(実際はどうだか知らないけど)
から衣の「か」、きつつなれにしの「き」、つましあればの「つ」
はるばるきぬるの「は」、旅をしぞ思ふの「た」
見事に、詠み込まれているのがわかります。
清濁は区別しないというのが「折り句」と「陰し題」共通のルールのようです。
それにしても見事ですね。
ちゃんと句の頭に決まった文字をもってきて、
オマケに「旅の心」というテーマまできちんと織り込んでます。
簡単に解釈いたしますと
「自分の着ているこの着物の様子からして、随分と遠い道程を旅してきました」
という感じですね。
それをただ詠むのなら、普通の人にもできるのです。
「万葉集」なんかは、農民から天皇まで歌を詠んだという何よりの証拠で
歌を詠むというのは、貴族の間だけでなく
広く庶民にも親しまれていたことが窺えるからです。
ただ、「折り句」「陰し題」というのは
相当、歌に長けていないと出来ない小技で、
作者(在原業平)が、いかに文学性に優れた歌人であったかというのは
最早、あたしなんかが言及するレベルの問題ではないのです。
すんごいんです(笑)。
それでですね。
多分、これは大学時代に詠んだ歌じゃないかと思うのですが、
丁度、塾講師のアルバイトでもしてる頃でしょう。
「折り句」なんていう高度な小技のことを思い出すんですから(笑)
高校生に古典を教えていたときに違いありません(爆)
そして、これは秋口に詠んだものでしょう・・・・<おそらく
それでもって、失恋してそんなに経っていない頃のモノかもしれないです。
「折り句」でもって、「きんもくせい」を散りばめた(つもりの)この歌。
「かきつばた」であれば、句ごとに文字を割り当てられますけど
「きんもくせい」は6文字。オマケに「ん」から始まる句なんて作れない(爆)
そんなわけで、このような句割で構成されました。
自分では、ギリギリだな・・・・と思います。
和歌に入るか、短歌に入るかのギリギリ。
レベル的にも、修辞的にも、誉められたものではありません。
まぁ、「創る(詠む)ことに意義あり」という理念の時代の作品ですので、
そのあたりは大目に見てやってください。
こうして、作品そのものには何の手も加えず、
そのまま出しちゃったんだから(笑)<恥ずかしかったけど。
昔の作品というのは、何でか恥ずかしいものですねぇ。
短歌に限らず、小説やら、詩やら
特に、自己陶酔の極限に達しようとしている時代のヤツなんかは
何があっても門外不出。
怖くて公表なんかできやしない。
いま現在、創っているモノをどうして公表しちゃっているかというと
怖くないからです。単に。
これを10年後、あたしが見たならば
やっぱり恥ずかしくて
表を歩くのさえ憚られるのかもしれません。
でも、やっぱり公表するのは
是であれ非であれ、
「批評」されることに意義があると見出せたからだと思います。
非ならば非で、何がどういけなかったのか
自分で自分の作品を分析できるだけの力がなくてはいけません。
それを培うために
傷つくのを覚悟で、公表に踏み切っている次第なのです。
「雑」に掲載する作品にしても、そう。
あたしのことを全く知らない人が、あたしの作品をどう読むのかを試すには
絶好の機会なのです。
そんなこんなで、
今日も、また部屋の片付けは出来ませんでした。
片付けようとしたら、昔の作品を見つけてしまい
金木犀の香りがしたので、
この事は、今日の日記に相応しいではないかと
掃除よりも優先させてしまったわけです( ̄∇ ̄;)
まぁ、たまには文芸らしく
このような事を書くのもよいのではなかろうかという
自称/作家・歌人・エッセイストなあたしの
暴挙でした♪ ちゃん♪ちゃん♪