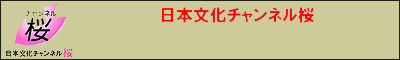目次|過去|未来
| 2004年04月12日(月) | 都をどり |
先日、祇園に都をどりを見にいった。庭園の桜が池に舞い散っている。
はるの日の うららにさして 観る舞は
観劇前の点茶の、點前は小喜美。一服頂いてから、着席。満席の大盛況。地方からも観光バスで来ている。横浜からの観光バスはベンツであった。なぁにベンツといって驚くな。向こうじゃベンツのトラックも走ってらい。日本のトヨタ・日産と同じ車の会社じゃないか。
それぞれに歳を重ねて、以前にも増してまんまるな顔の芸(舞)妓、あごのしゃくれた芸(舞)妓、どうしたらそんなおでこにと思ってしまう芸(舞)妓、さまざまが舞い踊る。よくもこんなに個性的の顔が集まるもんだと踊りそっちのけで鑑賞。
その中でも、アイドル歌手と浮き名を流した佳つ乃はやっばり際立って目立つ。
神戸の知人推薦の小亜希もなかなかよろしいな。
「二条城大広間の雪見」にそろって出ておりました。その襖繪には、鷹(豹のまちがい。訂正04/06/10)と虎が描かれている。京都における江戸幕府の本拠地としてあった二条城の大広間の控えの襖繪は、ここに登城する*大名達を威嚇するためのものだったという。
都をどりを通して、各時代のさまざまが見て取れる。それは色彩にもおよんで、「紫」ひとつとっても、紺桔梗・藤鼠・紅掛花色・藤色・二藍・藤紫・桔梗色・紫音色・滅紫・紫紺・深紫(こきむらさき)・浅紫・薄色・半色(はしたいろ)・菫色(すみれいろ) 杜若(かきつばた、別名 江戸紫(桃屋のあれではありません))。まだまだある…。芸妓の着物はさておいて、日本人の色彩感は、総じて各時代を通じて、けばけばしくなくシックであった。
嘉永六年(1853)、プーチャーチン使節団の一員として長崎に渡航したゴンチャロフも、「その中(接待の役人達に)に、どぎつい鮮明な色がない事」「赤も黄も緑も原色のままのは一つもなくて全てがその二色、三色の混和色の穏やかな軟らかい色調である…正装の色調はヨーロッパ人のそれと同じである。私は老人が花模様緞子(どんす)の袴をはいているのを5人ばかり見たが、これもくすんだ色であった」
また 安政5年(1858)、日英修好通商条約提携のため来日した、エルギン卿使節団を乗せて来た船の船長オズボーンの訪日記にこんな事が書いてある。
「日本の役人や、ジェントリは、大抵着飾っていたし彼等自身の流儀に従って、服装によってかなりのダンディズムを発揮していた。だが日本では、衣服の点では家屋と同様、地味な色合いが一般的て、中国でありふれている、けばけばしい色や安ぴかものが存在しない事に我々は気がついた。ここでは上流婦人の外出着も、茶屋の気の毒な少女達や、商人の妻のそれも生地はどんなに上等であっても、色は落ち着いていた。
そして役人の公式の装いにおいても、黒、ダークブルー、それに黒と白の柄が最も一般的であった。
彼等の家屋や寺院は同様に、東洋のどこと比べてみてもけばけばしく塗られていないし、黄金で塗られているのはずっと少ない。この日本人の趣味の特性は、われわれが日本を訪れた際の第一印象のひとつで、多くの第一印象がそうであるように、結局正しいと言う事が解った」。
「一口に言うと最新の流行色が全部揃っていた」と書いている。
今あげた二人の他に、多くの訪日した異邦人の認識は、この世界でも奇跡と思われる類い稀な独自の発達をとげた文明が、我々が来た事で壊れてしまわないかと言う危惧だった。そうして、それは見事に適中し、今日 あらゆるものが西洋化されてしまい、日本人としての矜持を持たない人々であふれている。
昔日本人と今日本人のわずかな共通項は、「言葉」である。冒頭にあげた句、
はるの日の うららにさして 観る舞は
はある有名な句をもじって作ったものだが、日本人なら、この大和言葉だけの句を読んで即座に理解できる事だろう。だが今後、タレントや流行作家の詩や文章を載せ、万葉集を教えない教科書でそだった日本人もどきは、ついに毛唐にも日本人にもなれないだろう。
参考文献:
*美と宗教の発見 梅原 猛
逝きし世の面影 渡辺 京一 葦書房
日本の伝統色彩 長島 盛輝 京都書院